
この記事の目次
はじめに
世界経済の中心であるアメリカ。
当然のごとく、仮想通貨市場もアメリカの動向に大きく左右されています。
昨今はBTCのETF(※1)(上場投資信託)がSEC(アメリカ証券取引委員会)に認められるかどうかが、非常に大きなニュースになっており、市場はその動向を見守っています。
先日、「今年(2019年)中の承認はない」とSEC主要メンバーが語ったとのニュースが流れた時には、市場が反応して価格が下がるなどの影響があったばかりです。
スタートアップ企業に流れる資金が7兆円以上と言われるアメリカの投資市場。
成長著しい中国ですら、投資市場の規模は、未だ半分にも満たない2兆円前後だと言われています。
このように、世界経済の中心地であると同時に、投資大国という一面も持つアメリカですが、今年2019年には、ユニコーン企業(※2)と言われる多くのベンチャー企業が多数上場すると言われています。
- SpaceⅩ(宇宙開発)
- Airbnb(民泊)
- UberとLyft(ライドシェア)
- Slack(ビジネスチャット)
- Pinterest(写真投稿サイト)
- Dropbox(オンラインストレージサービス)
などがそれに当たります。
Airbnbの評価額は200億ドル。Pinterestの評価額は110億ドル。そして、Dropboxの評価額は104億ドルと言われていて、上場後はさらなる成長が見込まれているのです。
アメリカ投資市場の抱える問題

投資を受ける側の問題
こうしたユニコーン企業の上場に沸くアメリカの投資市場ですが、全く問題がないわけではありません。
それどころか大きな問題を抱えていると言えるのです。
その一つが、過去20年間におけるアメリカ国内の上場企業数の減少です。
アメリカ国内の上場企業数は、1996年の8,090社をピークに減少の一途をたどっており、2017年には4,336社とほぼ半減しています。
また、IPO(新規公開株)の件数は、2014年には2001年以降最多となる291件に達したものの、2014年を境に再び減少に転じている状況です。
一方、アメリカ国内の上場企業の平均時価総額は、1996年の18億ドルから、2017年初には73億ドルと4倍に拡大しています。
また、時価総額50億ドル以上の企業約140社が総時価総額の半分以上を占めていて、時価総額上位1%の企業が全体の約29%を占めているのです。
M&Aや中小企業の上場廃止などが主な要因で、上場企業数は減少する一方、上場企業の時価総額自体は増加しており、市場に占める大企業の割合が増加していることがうかがえます。
これらは、2000年頃のIT(ドットコム)バブル崩壊後や、2009年に起こったリーマンショック後に成立した法規制が原因です。
資本市場の健全な発展にコンプライアンス強化が必要不可欠である点は、議論の余地はありません。
ですが、様々な法規制が投資回収コストやリスクの増加を生んでいるのは間違いありません。
さて、ここまでは投資を受ける側の問題でした。
もう一つの問題は、投資をする側の問題です。
投資をする側の問題
SECの規則により、『適格投資家制度』というものが設けられています。
適格投資家制度とは、
- 過去2年間において20万ドル(または配偶者と合わせて30万ドル)超の収入がある。
- 単独または配偶者と合わせて100万ドル(個人住居の価値を除く)以上の純資産を有する。
この2つの条件を満たした人を、『適格投資家』として認めるというものです。
そしてこの『適格投資家』に認められない人は、あるレベル以上の投資に参加することができないのです。
『適格投資家制度』の目的は、
- 未登録の有価証券に投資する経済的リスクに耐え得る企業および個人を特定する
- 過剰リスクと潜在的な詐欺から一般投資家を保護する
ことにあります。
確かに投資家保護は、投資市場を守るために必要な制度ではありますが、行き過ぎた投資家保護の規制は、富の集中化を招きます。
事実アメリカでは、『適格投資家制度』をクリアした人や企業に富の集中化が起こっています。
こうした問題が仮想通貨バブルとともに、顕在化してきたのです。
そうした背景の中でのアメリカ仮想通貨市場

アメリカの投資市場が抱える、規制が生んだ2つの問題。
市場の硬直化と、富の集中。
仮想通貨はそれらの問題を打破する可能性を秘めていました。
クラウドファンディング的な要素を持ったICO(Initial Coin Offering)は、市場に新たな資金調達方法をもたらしました。
それと共にICOは、『適格投資家制度』をクリアしていない投資家層も参加できる効率の良い方法として、市場に受け入れられて行きました。
しかし、規制や投資家保護が十分でないICOは、詐欺まがいの案件が乱立し、大半の人や企業は大事な資産を失うことになりました。
そして世界各国でICOの規制強化の動きが始まり、国によってはICOそのものが禁止されて行きました。
ICOが規制された理由は、先にもお伝えした通り、詐欺まがいのICOが乱立したことが主たる原因です。
しかしそれ以外にも、本来エコシステムの運営に利用するトークンが、投機的価値があると認識されたことも大きな原因の一つになっています。
言い換えると、本来は金融商品ではないものが、金融商品のように取引されることが問題になった訳です。
そこで、エコシステムに使われるユーティリティ・トークンではなく、最初から金融商品としての価値を持たせた、セキュリティ・トークンが作られるようになりました。
ICOからSTOへ

セキュリティ・トークン(Security Token)とは、証券トークンのことです。
セキュリティ・トークンと聞くと、「安全なトークンのことなのかな?」と思いがち(最初に聞いた時、私はそう思ってしまいました(笑))ですが、違います。
セキュリティ・トークン(証券トークン)とは、現実にあるアセット(※3)をブロックチェーン上でトークン化し、取引できるようにしたものです。
端的に言うのなら、「取引可能な資産によって裏付けされているトークン」と言い換えることができます。
具体的には、株券や不動産、債権や為替などのデリバティブ商品をトークン化することになります。
先にもお伝えしましたが、ユーティリティトークンを使ったICOが問題になったのは、あやふやな価値のままトークンが発行されたにも関わらず、証券としての基準が非常に曖昧であったことです。
対して、セキュリティ・トークンは証券として発行されていますので、証券法によって適切に規制されるものになります。
また現在動いているプロジェクトも、証券法を遵守するように動いています。
このように法律を遵守しつつ、金融商品をトークン化することを、STO(Security Token Offering)と呼びます。
STOの特徴
STOはICOとIPOの中間的存在になります。
現実のアセットをトークン化して販売するというのは、STO独自のものです。
それに対して、以下の点はICOと同じです。
- トークンを販売して資金調達を行う
- 投資家の参加資格に制限がない
一方で以下の点はIPOと同じになっています。
- フレームワークの規制に則って通貨を発行
- 規則の履行によるスキャム(詐欺)コインの排除
このようにSTOは、ICOやIPOの良いところを取り入れています。
ですが今後、セキュリティ・トークンがどのように扱われるのかに関しては、まだ不確実な部分は存在します。
セキュリティ・トークン化するメリット

金融商品をトークン化することで得られるメリットは、以下のものが考えられます。
流動性の向上
通常の金融商品は取引時間が限られています。
株や為替は、市場が開いている時間にしか取引ができません。
これに対して、トークン化された場合は、仮想通貨の取引と同じように、24時間365日の取引が可能になります。
スマートコントラクトを使った自動化
例えば、規定のKYC(Know Your Customer:顧客確認)プロセスを通過した人にのみ、セキュリティ・トークンへのアクセスを許可する。
こうした契約条件をスマートコントラクトに設定することで、自動化が可能になります。
スマートコントラクトには、基準を満たさないアクセスは許可しないと設定しておくことで、外部からの侵入を防ぐことも可能になります。
低コスト化
先の自動化によるコストの削減や、証券取引にかかるコンプライアンスコストの削減も、規制に準拠したシステムを構築することで、可能になります。
それ以外にも、以下のようなメリットがあると考えられます。
- グローバルな資金が入りやすい
- 資金調達のハードルを低く設定できる
こうしたSTOへの波が今、アメリカでは起こっているのです。
セキュリティ・トークンの発行が多いアメリカ市場

STOやセキュリティ・トークンに活路を見出したい理由は、最初にお伝えしたアメリカの投資市場が抱える問題があるからです。
その問題を解決する可能性を秘めたセキュリティ・トークンの一つの形として、法定通貨と連動するステーブルコインがあります。
ステーブルコインとは、法定通貨とペッグ(固定相場制)を導入した仮想通貨を指します。
仮想通貨は価格の変動が大きいため、決済などの取引には使いづらく、預金としても増える分には良いですが、減ってしまっては意味がありません。
BTCは最も時価総額が高く、単価も40万円前後ですが、価格は全く安定していません。
事実、2017年末の価格から1/5以下になっています。
そこで出てきたのが、価格が安定した仮想通貨であるステーブルコイン(StableCoin)です。
ステーブルコインは、価格が安定しているからこそ決済や送金、預金に利用されやすいメリットがあります。
デメリットとしては、マネーロンダリング(資金洗浄)に使われる危険性があることと、投資対象としては全く旨味がないことです。
通貨が安定している欧米諸国や日本では、ステーブルコインを使う機会はあまりないと言えます。
一方で、自国通貨が安定していない途上国や、国の政策によってドルが買えない国の人々にとって、ステーブルコインは非常に価値の高いものになっています。
これはSTOのメリットでお伝えした、グローバル資金の流入が起こっていることになります。
事実、以前に紹介した中国取引所のほとんどは、Tether(USDT)が取引の中心になっていましたし、米ドルの代わりにステーブルコインが流通している国もあるようです。
今お伝えしたTether (USDT)は、一番最初に発行されたステーブルコインで、ペッグしている通貨は米ドルです。2018年6月に、275億円分のUSDTが発行されました。
Tether以外だと、TrueUSD(TUSD)、Gemini dollar(GUSD)、USD//Coin(USDC)が米ドルとペッグしたステーブルコインです。
またPaxos Standard(PAX)というコインもスタートアップの準備中です。
これらステーブルコインの発行元が、これからご紹介する各取引所になります。
アメリカ取引所一覧を見る際の基準
では国内取引所や韓国取引所、中国取引所一覧のように、紹介する取引所のデータを表にまとめていきます。
表に記載するデータは以下の通りです。
| 仮想通貨交換業者名 | CoinMarketCap(以下CMCと略)の表記に準じる |
| サイトURL | CMCの表記に準じる |
| 登録開始年月日 | 設立年を記載 |
| 取引所形態 | 中央集権型 or 分散型 |
| 対応言語 | |
| 取扱通貨 | 取扱種類数:種類 通貨ペア:種類 以下取引量ベスト10ランキング 順位. 種類 / 通貨ペア / ボリューム |
| レバレッジ | 有り or 無し |
| ペア通貨 | 法定通貨 & 仮想通貨の種類 |
| 手数料 | 手数料 |
| 独自トークン | 有り or 無し |
| 支払方法 |
|
| 調整取引量 | CMC調べ(順位) |
それでは始めていきましょう。
アメリカ取引所①:Gemini(ジェミニ)

| 仮想通貨交換業者名 | Gemini |
| サイトURL | https://gemini.com/ |
| 登録開始年月日 | 2014年10月 |
| 取引所形態 | 中央集権型 |
| 対応言語 | 英語 |
| 取扱通貨 | 取扱種類数:5種類 通貨ペア:15種類 以下取引量ベスト10ランキング 順位 種類 / 通貨ペア / ボリューム
|
| レバレッジ | 無し |
| 手数料 |
|
| 独自トークン | 無し |
| 支払方法 |
|
| 調整取引量 | $3,813,452(83位) |
Gemini(ジェミニ)の特徴
Geminiは、仮想通貨界で有名なウィンクルボス兄弟が作った取引所です。
ウィンクルボス兄弟と言えば、Facebookのマーク・ザッカーバーグに勝訴し賠償金6500万ドル(約75億円)を得たことで、アメリカでは有名な双子です。
この賠償金のエピソードは、映画『ソーシャルネットワーク』でも取り上げられ、主人公のマーク・ザッカーバーグの敵役として、ウィンクルボス兄弟も登場しています。
ウィンクルボス兄弟は、その賠償金を元手にBTCなどの仮想通貨に投資を開始します。
そして2014年には『Gemini(ジェミニ)』の創業を開始しました。
ウィンクルボス兄弟と言えば、SEC(米国証券取引所)にBTCのETF(上場投資信託)の認可申請を何度も行なっています。
申請はことごとく却下されていますが、何度却下されようとも諦めないその姿勢は、執念すら感じさせるものです。
Geminiの取引所としての特徴は『セキュリティ第一』でしょう。
ほぼ全ての資産をコールドストレージで保管し、法定通貨に至っては公的金融機関で管理しています。
利用者は2段階認証や強度のパスワード設定が求められます。
全ての従業員に監査と内部統制を行うなど、その徹底ぶりは見事です。
Gemini(ジャミニ)のステーブルコインの特徴
2018年9月に『Gemini dollar(GUSD/ジェミニ・ダラー)』というステーブルコインをニューヨーク州金融サービス局(NYDFS)が承認しました。
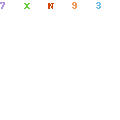
GUSDの特徴として、外部の事業者間での安全なデータ連携が可能になっており、アプリで監査が可能担っています。
パブリックチェーン上で許可制スマートコントラクトを動かすことで、安全性・監査性を備えるアプローチを取っています。
GUSDは、ETHのERC20に準拠したもので、すでに上場済みです。
GUSDが上場している仮想通貨取引所は、Gemini、HitBTC、Bibox、OAX、LATOKENなどがあります。
ただ残念なことに、Geminiの日本人登録は不可となっている模様です。
アメリカ取引所②:Poloniex(ポロニックス)

| 仮想通貨交換業者名 | Poloniex |
| サイトURL | https://poloniex.com/ |
| 登録開始年月日 | 2014年1月 |
| 取引所形態 | 中央集権型 |
| 対応言語 | 英語 |
| 取扱通貨 | 取扱種類数:62種類 通貨ペア:121種類 以下取引量ベスト10ランキング 順位. 種類 / 通貨ペア / ボリューム
|
| レバレッジ | 有り |
| ペア通貨 |
|
| 手数料 |
|
| 独自トークン | 無し |
| 支払方法 |
|
| 調整取引量 | $6,984,174(71位) |
Poloniex(ポロニックス)の特徴
Poloniexの特徴の一つとして、レバレッジ取引が可能である点が挙げられます。
また、取引ペアを見ても分かる通り、非常に多くのアルトコインに対応しています。
アルトコイン取引高1位の座はBinance(バイナンス)に明け渡しましたが、2015後半~2017年前半にかけて、非常に存在感のあるアルトコイン取引所でした。
そんなPoloniexですが、2018年9月にフィンテック企業大手のCircle(サークル)社が株式を取得、傘下に入ることが発表されました。
買収額は4億ドル(約420億円)と報道されました。
Circle社は、送金事業者として、SEC(米国証券取引委員会)に監督・運営されており、株主にはゴールドマン・サックス、デジタルカレンシーグループなどが名を連ねる優良企業です。
ところで、Poloniexは日本で言うところの『みなし業者』でした。
Circle社とは違い、SECの監督・承認を得ていないグレーゾーンの取引所だったのです。
そんなPoloniexを買収をすることは、Circle社にとっては大きなリスクでしたが、SECはこれを認めました。
また、Poloniexの無認可営業の件も追求しないと報道されています。
あくまでも推測ですが、Circle社はSECや株主のゴールドマン・サックスやデジタルカレンシーグループとも相談した上で、今回の買収に踏み切ったのでしょう。
こうしてCircle社の傘下に入ったPoloniexですが、系列的にはデジタルカレンシーグループにも、統合されたことになります。
Poloniex(ポロニックス)のステーブルコイン事業
Poloniexは今後、Circle社が2018年9月より発行しているステーブルコイン、USD Coin(USDC)を取引の中心に据えて、決済などに使っていくとしています。
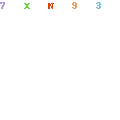
USDCはイーサリアムのERC20に準拠したもので、上場している仮想通貨取引所はPoloniex、LATOKEN、Kucoin、CoinEXなどがあります。
Poloniexのサイトは、日本語対応はしていませんが、ブラウザの自動翻訳で十分に分かりやすく表示されるように作られています。
また日本人の登録も問題なく行えますので、アルトコインをメインに取引されている方は、今後の動向に注目されてはいかがでしょうか。
アメリカ取引所③:BITTREX(ビットレックス)

| 仮想通貨交換業者名 | BITTREX |
| サイトURL | https://bittrex.com/ |
| 登録開始年月日 | 2014年2月 |
| 取引所形態 | 中央集権型 |
| 対応言語 | 英語 |
| 取扱通貨 | 取扱種類数:230種類 通貨ペア:326種類 以下取引量ベスト10ランキング 順位. 種類 / 通貨ペア / ボリューム
|
| レバレッジ | 無し |
| ペア通貨 | USD |
| 手数料 | 0.25% |
| 独自トークン | 無し |
| 支払方法 |
|
| 調整取引量 | $27,500,724(53位) |
BITTREX(ビットレックス)の特徴
今回の記事で、一番話題を探すのに苦労したのが、Bittrexでした。
ステーブルコインの取り扱いで言えば、USDTが軸にはなっているものの、他のコイン(BTC、ETC)の取引の方が活発でした。
上場しているもう一つのステーブルコインであるTrueUSD(TUSD)も70位あたりの取引量となっています。
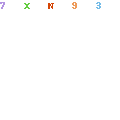
ニュースらしいニュースもほとんど無く、2018年9月に「Bittrex International」が「Bittrex Malta Ltd」の設立を発表したくらいです。
取扱通貨も一時期は、400種類に届こうかというほどでしたが、コスト面とセキュリティ面が問題になり、2018年2月に上場廃止にした通貨の数は80にのぼります。
同じアメリカの仮想通貨取引所ではありますが、Bittrexは世界展開を視野に入れて活動しているようです。
アメリカ取引所④:Kraken(クラーケン)

| 仮想通貨交換業者名 | Kraken |
| サイトURL | https://www.kraken.com/ |
| 登録開始年月日 | 2011年4月 |
| 取引所形態 | 中央集権型 |
| 対応言語 |
|
| 取扱通貨 | 取扱種類数:20種類 通貨ペア:73種類 以下取引量ベスト10ランキング 順位. 種類 / 通貨ペア / ボリューム
|
| レバレッジ | 有り(5倍) |
| ペア通貨 |
|
| 手数料 | 0% 〜 0.26% |
| 独自トークン | 無し |
| 支払方法 | 電信送金 |
| 調整取引量 | $28,123,984(52位) |
Kraken(クラーケン)の特徴
Krakenは、2014年に破たんしたMt.GOX社の債権者への支援を担当してくれたことで、日本には馴染みの深い取引所です。
ただ、今回特集したステーブルコインに関しては、USDTのみの取り扱いになっており、独自トークンの取り組みもありませんでした。
Krakenの特徴としては、EURベースの取引が多いことが挙げられます。
また、アメリカの取引所であるにも関わらず、日本円での取引(ペア:BTC)もあり、日本語対応もなされています。
それとKrakenは、セキュリティレベルが高い取引所として、格付けされています。
2018年11月に、有力なサイバーセキュリティ企業Group-IBが、世界中の取引所のセキュリティを格付しました。
この格付けは、保険料率を前提としており、リスク順に4つのグループに分類されます。
最も安全・確実な第1グループから、保険にかけられないと判断される第4グループまでに分かれます。
最優秀な仮想通貨取引所とされたのはKrakenのみで、その保険料率は1.25%でした。
2011年設立という比較的長い歴史のあるKrakenですが、歴史とともにその安全性も証明されたと言えるでしょう。
今回の企画には適合しませんでしたが、海外の取引所を選ぶ場合は、十分に選択肢に入るのではないでしょうか。
アメリカ取引所⑤:Coinbase(コインベース)

| 仮想通貨交換業者名 | coinbase |
| サイトURL | |
| 登録開始年月日 | 2012年4月 |
| 取引所形態 | 中央集権型 |
| 対応言語 | 英語 |
| 取扱通貨 | 取扱種類数:14種類 通貨ペア:32種類 以下取引量ベスト10ランキング 順位. 種類 / 通貨ペア / ボリューム
|
| レバレッジ | 無し |
| ペア通貨 |
|
| 手数料 | 0% 〜 0.3% |
| ステーブルコイン | USDC |
| 独自トークン | 無し |
| 支払方法 |
|
| 調整取引量 | $32,200,142(50位) |
Coinbase(コインベース)の特徴
coinbaseといえば、日本進出が決定し、2019年中にはオープンする予定です。
またcoinbaseは、世界中に拠点進出を行なっており、アジア、オーストラリア、ヨーロッパなど、40箇所に及びます。
そんなcoinbaseですが、今回取り上げているステーブルコインは、Poloniexと同じ、USDCになります。
それとともに、分散型取引所のベーストークンになっている0xが上場しており、取引もすでに開始されています。
ライバルであるBinanceとのシェア争いが、日々激しさを増しているのですが、少々気になるニュースがありました。
米大手仮想通貨交換所コインベースで複数の幹部の退社が相次いだようだ。
The Informationが2月13日に報じた。
The Informationは、相次ぐ幹部の退社により、今後コインベースが優秀な人材を引き付け、保持することが困難なる可能性があると指摘している。
引用:cointelegraph「米仮想通貨取引所コインベース 経営幹部が相次ぎ退社か」
この記事は、coinbaseから複数の幹部の退社が相次いでいると伝えています。
相次ぐ幹部の退社により、今後coinbaseが優秀な人材を引き付け、保持することが困難なる可能性があると指摘しているのです。
退社した経営幹部は、コンプライアンス担当のマイケル・ロジャー氏。
政策委員会メンバーであり、マネーロンダリング対策専門家のワデーハ・ジャクソン氏。
グロース部門のプロダクト責任者だったステージン・ペレ氏であるとのことです。
いずれもプロフィール情報から退社していることが認められています。
世界中に拠点を展開し、取引部門においては、coinbase proを作って上級者向けのサービスも開始しているcoinbaseですが、この記事はかなり気になります。
証券市場が大きくなりすぎて、弊害が発生している
STOでは通貨をパブリック・オファリング(=公開通貨)として発行します。これは、米SEC等のフレームワークの規制にのっとって通貨を発行することを意味します。
この方法では規制に準じたプロダクトだけが公開されるわけですから、当然有望なプロジェクトのみがSTOを行うことができ、スキャムコイン等は淘汰されていきます。
一方で、STOはクラウドファンディング的な要素を取り去ってしまうものともいえます。
その上さらに大きく懸念されているのが「誰が投資できるか」です。
例えばSECでは、特定以上の年収、資産を持つ個人・法人のみが投資できる、などといった規制があります。
こういった規制がSTOにも当てはめられた場合、ICOの良さが大きく取り除かれてしまいます。
アメリカ取引所についてのまとめ

今回、アメリカの取引所を取り上げてきましたが、アメリカ市場が抱える問題にあえてスポットを当ててみました。
ICOに変わってSTOに移行しつつあるアメリカ市場ですが、その理由を明確に説明するために、少々前置きが長くなってしまい、読みづらかったのではないかと反省しきりです。
また、STOの中心になっている企業の一部が、取引所の買収を視野に入れている点も、今回の記事をリサーチして分かった、新たな発見でした。
惜しむらくはSTOを推し進めている企業が、取引所とは別に存在するので、取り上げきれなかった点が悔やまれます。
個人的には、ドルを購入できない国のユーザーがステーブルコインを使っている流れが、仮想通貨本来の使い方のようにも思います。
仮想通貨が今すぐ、法定通貨に成り代わることはないと思っていますが、一部では新たな使い方が始まっていて、それが常識になりつつあります。
アメリカ市場が抱える問題も含め、仮想通貨というイノベーションがこれからどう育っていくのか、これからますます目が離せないと感じています。















































