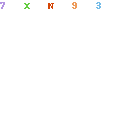
2017年に仮想通貨ビットコインが急騰したこともあり、仮想通貨が日本でも多くの人に注目されるようになりました。
その結果、取引をする人も増えました。
しかしそれと同時に、仮想通貨関係での逮捕者も増え、注目されるようになってしまいました。
安全に仮想通貨での取引をしていくためにも、これらの事件について知っておく必要があります。
そこで今回は、仮想通貨関係の事件や逮捕者などを紹介していきます。
この記事の目次
国内で逮捕された仮想通貨関係者まとめ

まずは、国内で起きた仮想通貨関連の事件や逮捕者についてまとめていきます。
同じような事件に巻き込まれることが無いように、知識として知っておいてください。
CoinHive(コインハイブ)事件
CoinHiveは元々、サイトを運営している人が、そのサイトを閲覧している人にマイニングさせて、仮想通貨による収益を受け取ることができるという仕組みを持つツールでした。
マイニングを行う際に自分のパソコンを使うのではなく、HTMLにJavaScriptコードを埋め込んでおくことで、サイトを閲覧した人のパソコンのCPUを動かしていたのです。
これにより仮想通貨のMoneroを得ることができました。
こうして得られた仮想通貨のうち3割がサイトの運営者に、7割がCoinHiveの運営側に送られていました。
このCoinHiveの仕組みは、広告などを表示する必要が無く、サイトの閲覧者がいればリアルタイムで収益があがるということで注目されていました。
CoinHive事件のきっかけ
CoinHive事件のきっかけは2017年9月下旬に、あるウェブデザイナーの男性(A氏)が自身の持つサイトにCoinHiveを取り入れたことでした。
そのまま1か月ほどCoinHiveを使っていましたが、A氏はあるエンジニアから「CoinHiveを運用するのはサイト閲覧者の同意が必要なのではないか」と言われ、サイトからCoinHiveを削除しました。
ここまででしたらただ単に、ある男性がCoinHiveを使い、1か月で使うのを辞めたという話でした。
2018年2月 略式起訴
しかし、その3か月後の2018年2月に、神奈川県警がA氏の自宅を家宅捜索し、同3月28日に、不正指令電磁的記録所得・保管の罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令が出ました。
この不正指令電磁的記録所得・保管罪は、ウイルス罪とも呼ばれています。
CoinHive事件では、閲覧者のパソコンのCPUを使ってマイニングを行うことをサイトに記載していなかったことから、反意図性、不正性を満たしているという判断で起訴されたのです。
正式裁判を請求
A氏はそれが不服として、正式裁判を請求しました。
この裁判では、
- CoinHiveは不正指令電磁記録に該当するのか
- 故意があったといえるのか
- 実行の用に供する目的があったのか
の3つが争点となりました。
検察側は、A氏がCoinHiveを使った際に、閲覧者に同意を求める仕組みにしなかったことから、閲覧者の意図に反する動作をさせるプログラムであるとしました。
しかし、CoinHiveが不正な指令を与えるプログラムに該当するとは明確な判断が下されず、不正指令電子記録には該当しないとされました。
無罪判決が確定後も訴訟が継続中
結果として、この裁判の判決は、無罪となりました。
この無罪判決によりCoinHive事件は一度終わりを迎えましたが、2019年4月10日に横浜地裁が判決を不服として東京高裁に控訴しました。
現状ではここまでとなっています。
Monappyのコインハッキング事件
Monappyは、仮想通貨Monacoinのウォレットサービスでした。
2018年9月、Monappyが盗難を報告
2018年9月1日に、このMonappyの運営は、このサービスからモナコインが盗難されたことを報告しました。
コールドウォレットに保管されていた全残高のうちの50%以上に問題はありませんでしたが、ホットウォレットだったモナコインはほぼ全てが盗難されました。
この時点でMonappyは外部からのハッキングによる盗難の可能性が高いとしてサービスを停止し、調査を開始しました。
ギフトコード機能の不備と判明
その後、調査を進めていくと、複数のユーザーが8月27日から9月1日の間に大量にギフトコードを発行していて、外部受け取り機能を使ってギフトコードを受け取る際に非常に高頻度でリクエストを行っていたことがわかりました。
その結果、1つのギフトコードに対して数回の送金が行われてしまっていたことがわかりました。
本来ギフトコードは二十二使用することはできないようになっていましたが、高負荷時にはギフトコードを連続で利用すると、通信と送金の時間差から複数回の送金が行われてしまったのが原因でした。
そして翌9月2日の午前3時に、この盗難はMonappyのギフトコード機能の不備を利用したものであると発表しました。
この不備は、高負荷時には、1つのギフトコードに対して複数回の送金が行えてしまうというものでした。
これがMonappyのコインハッキング事件の全容になります。
Ask Monaにウイルスを作成してモナコインをハッキングした事件
この事件は、2017年10月10日頃にモナコインを利用しているユーザー向けの掲示板である「AskMona」に、「モナコインの相場を確認できるソフト」という名前でウイルスの入ったソフトが公開され、ダウンロードできるようにされたのがきっかけです。
このソフトをダウンロードした東京都の会社員男性のPCがウイルスに感染し、ウォレットの秘密鍵が読み取られてしまいました。
そして、男性が保有していたモナコインが移動させられることになりました。
この件で2018年1月30日に不正指令電磁的記録作成・提供の疑いで、大阪府貝塚市の高校三年の男子生徒が逮捕されました。
SENER(セナー)事件
SENER事件は、SENER社という架空の会社への出資金を仮想通貨で集めていた詐欺事件になります。
SENERという会社は2007年にアメリカで創業したとされていて、自社PVやイベントなどまで行っていました。
そしてこの会社が高い利回りで投資を募っているとして、その投資金を仮想通貨であるビットコインで集めていたのです。
この際の利回りとしては、投資金額と日数によって変わってもきましたが、50,000$の投資をすると180日以上経過すると月々20%が最大とされていました。
これは非常に高い利回りとなっています。
魅力的な条件に多くの人が投資
これに魅力を感じた多くの人が実際に投資をしてしまったのです。
実際に見せ金として配当が貰えていたことも信用を高めていた一因となっています。
その後、突然配当が停止し、返済もされなくなってしまったことから事件性が出てきました。
この事件では、「マルチ商法」のような手口で約6,000人から現金約5億円、仮想通貨約78億円相当を集めていたとみられています。
また、この事件の犯人として中心的な役割を担っていた8人が逮捕されています。
仮想通貨のAI自動売買トレードシステムを提供するRe:Japanプロジェクト
Re:Japanプロジェクトは「日本全国940名に10億円の地域振興金を分配する超BIGプロジェクトが発足」というキャッチコピーのプロジェクトです。
このプロジェクトの責任者は石塚幸太郎という人になっています。
このプロジェクトに参加するためにはメールアドレスやLINEの無料登録が必要となっていした。
この登録によってはお金は受け取ることができず、登録者にはさらに「ジャパングローバルクラブ」というコミュニティーへの参加権が販売されました。
これは、AIによって仮想通貨のトレードを自動的に行わせ、その配当金を分配するというものでした。
この参加権の金額は138,000円だったと言われています。
これに参加することで、毎月106万円の分配が受けられ、返金保証もあるということで、参加する人が出てきました。
しかし、実際には配当金や返金はありませんでした。
これらのことから、仮想通貨投資詐欺であるとして田口聖也が逮捕されました。
ノアコインの泉氏は逮捕寸前?訴訟された内容
ノアコインは現在では正式にはノアアークコインという名前になっている仮想通貨です。
このノアコインは元々、フィリピンの出稼ぎ労働者が安く国に送金することを目的にしていた仮想通貨でした。
フィリピン人が出稼ぎによって稼ぐ金額は年間で3兆円になるとされていて、フィリピンのGDPの10%を占めるほどでした。
そしてフィリピンでは、この出稼ぎのお金の国際送金の際の手数料が社会問題となっていました。
その問題を解決するために作られたのがこのノアコインだったのです。
またノアコインでは、フィリピンを発展させるために国土開発することも目的としていました。
ルソン島にアミューズメント施設である「ノアシティ」、ミンダナオ島にリゾート施設である「ノアリゾート」を建設する予定としています。
保有するだけで配当がもらえる仮想通貨
このノアコインは、通貨を保有しているだけで配当金がもらえるという形式をとっていました。
この配当金は、年々減っていくものの、1年目には20%もらうことができました。
さらに注目されるきっかけとなっていたのは、その配当金を40年間もらい続けることができるという点でした。
この配当金をもらうために多くの人が注目し、購入するようになりました。
フィリピン政府は無関係
しかし、このフィリピンの国家プロジェクトとされていたノアコインでしたが、実際にはフィリピン政府とノアコインは無関係であることが明らかになりました。
40億〜80億円もの資金調達に成功
また、日本とフィリピンに限定してICOを始めたところ、40億~80億円もの資金調達に成功したと言われています。
この資金はほとんど日本からのもので、それは泉忠司氏が宣伝をしていたからのようです。
ですがこの泉氏の宣伝には詐欺まがいと言われるものも多かったのです。
プロジェクトは一時停止・延期
これらの過剰な広告に対してフィリピン政府から警告を受けたためプロジェクトは一時停止し、延期することが発表されました。
この際に事前予約していた人のうち希望者には全額返金することになりました。
しかし返金を希望した場合には、再びプレセールに参加することはできないとされてしました。
これらのことから、ノアコインは詐欺ではないかと言われています。
泉氏は4つの商材で訴訟対象に
泉氏はこのノアコインだけではなく他のプロジェクトにも関わっていたため、4つの商材が訴訟の対象になっています。
株式会社ONE MESSAGEおよび泉忠司氏「仮想通貨バイブルDVD」および「パルテノンコース」の購入代金の返還請求 東京地方裁判所に提訴 平成31年(ワ)第11049号
株式会社ONE MESSAGEおよび泉忠司氏に対し「仮想通貨バイブルDVD5巻セット(VIPコースを含む)」および「パルテノンコース(ハイスピード自動AIシステム及びこれに付帯するサービス)」の購入代金の返還を求めています。
引用:消費者機構日本
この訴訟の理由は、宣伝する際に「最短最速であなたを億万長者にします」といった絶対に儲かると取れる言葉を使っていた点が詐欺行為に当たるとされたためです。
ノアコインについてもっと詳しく知りたい人は下記の記事をご覧ください。
仮想通貨取引は追跡可能で犯罪者が逮捕しやすい理由

最初の仮想通貨としてビットコインが誕生すると、知らない人も多く、あまり表に出てこないことから、全体の90%が闇取引やマネーロンダリングに使用されていました。
しかし、本来の目的は送金やクロスボーダー決済に使われることでした。
そのため、これらの不正を防ぐことを目的として、取引をIPアドレスと結びつけることで仮想通貨取引から追跡を行えるようにしたのです。
こういった詳しい知識が無い場合、現実の紙幣などと同じように匿名であると思い不正などに利用しますが、専門家からすると追跡を行うことができるものであるため、逮捕がしやすくなっているのです。
仮想通貨の逮捕者から学ぶ仮想通貨を守る為には

仮想通貨は実際に手に取ることができません。
そのため、現実のお金のように金庫などに入れて保管するということができません。
だからこそ、仮想通貨を守るためには所有者自身がセキュリティの意識を持っておく必要があるのです。
具体的には、まずはパスワードに関しては複雑で桁数の多いものを使用し、他のサービスなどで使っているパスワードは使わないということが大切です。
簡単なパスワードは容易に予測されることも多いため、他のサイトの情報が盗まれることで仮想通貨のパスワードまでばれてしまうことを防ぐ必要があります。
また、ファイルをダウンロードする際には、安全であるかどうかを確かめる必要があります。
AskMonaでの事件のように、ウイルスが入ったファイルをダウンロードしてしまうと、それを開いただけで情報が盗まれることになります。
ウイルス対策にセキュリティソフトを導入しておくことも必要です。
こういった自分でもすぐに出来るセキュリティ対策をしていくことで、盗まれる可能性を回避することができます。
まとめ
数年前と比較すると、仮想通貨の知名度は飛躍的に高まり、人々の身近なものとなりました。
しかし、十分な知識を持たずに仮想通貨取引を始めてしまったことで、仮想通貨に関する犯罪の被害者となってしまう人が増えているのも事実です。
知識があまりない初心者をターゲットにした詐欺もあります。
仮想通貨には取引を追跡できる仕組みがありますが、犯罪に巻き込まれないのが一番です。
仮想通貨には危険な面もあるということをしっかりと理解した上で、セキュリティ対策をしっかりと整えながら、仮想通貨取引をしていきましょう。










































