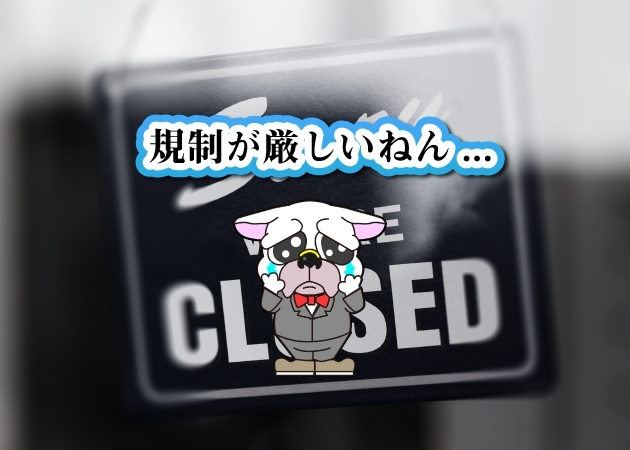
仮想通貨ステーブルコインBasisは巨額のICOにより、大手のベンチャーキャピタル社からも期待の声が上がっていましたが、公式サイトによりプロジェクトの撤退が発表されました。
一体何故これほどまで期待されていたプロジェクトが撤退にまで追い込まれたのでしょうか?
ここではステーブルコインBasisのICO内容や仕組みの開設と、原因の一端であるICO規制に関することをまとめました。
この記事の目次
ステーブルコインBasis(ベーシス)とは
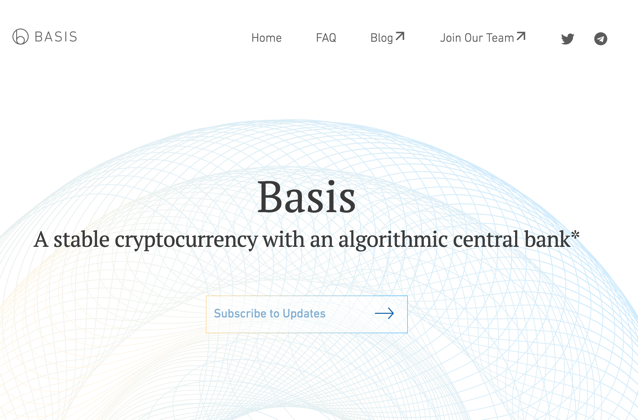
ボラティリティ問題の解消
仮想通貨は共通の問題点として、ボラティリティの高さがよくあげられています。
これは通貨としての価格変動性が高いことを指し、通貨として価格が安定していないことを意味します。
将来的に仮想通貨を決済手段として利用する際、やはりボラティリティが高い通貨と言うのは足かせとなってしまうことが懸念されました。
ステーブルコインは仮想通貨で発生するボラティリティのない(価格変動がない)仮想通貨のことを指します。
Basisはステーブルコインを実現させようと、1ドルの価格と連動させることを目指しました。
通貨の価格を安定させるために配給量を調整する高度なアルゴリズムを用いる画期的な技術が話題となり、Google Ventures(グーグル・ベンチャーズ)を始めとした大手のベンチャーキャピタルからも期待されていたプロジェクトでした。
ステーブルコインBasis(ベーシス)の仕組みとは

Basisは三つのトークンを利用することにより、Basisiの配給量を調整しています。
それぞれのトークンを活用することにより、通貨の価格を安定させるような仕組みです。
では、三つのトークンは具体的にどのような役割を持っているのかを紹介します。
Basis(Basecoin):ベーシス
Basisのコアにあたるトークンです。
米ドルと結びつけることにより、常に価値が変わらないようになっています。
米ドルとのペッグを維持するために供給量が調整されます。
主に交換の媒体として用いることを目的としています。
Bond tokens.:ボンドトークン
短期間の債権と呼ばれるトークンです。
供給を縮小させる際にブロックチェーンにて競売にかけることで、Basisの配給量を調整します。
Basisが1ドル未満の際にのみ発行されるので、購入時は必ず1Basis未満となります。
条件を満たせば1Basisと交換することができます。
条件はBasisの供給拡大期となる等といった場合です。
このように供給が不足した際はBondトークンにより投資家の購入意欲をかきたてることにより、通貨の安定させる役割を持ちます。
ブロックチェーンにより供給量が定められているトークンです。
Bondトークンと同様にペッグはせず、Basisが新規に発行された際の配当によって価値が決まります。
Basisの需要が高まった際は、Basisの価値が上がることとなります。
新たなBasisが発行された際、Bondトークンが全てBasisに償還されているかつShareトークンを保持しているとBasisを受け取ることができます。
このように余ったBasisをBasis所有者に配布させて、Basisに投機的要素を持たせるためにShareトークンが導入されることとなりました。
ステーブルコインBasis(ベーシス)のプロジェクトが撤退した原因とは

米国規制ガイダンスにより、仕組み上の問題が発生
現状、ICOは無法地帯と言われる程詐欺が多い状況にあり、各国では規制を強めるような動きが出ています。
Basisは米国の規制ガイダンスが発表される中、Basis上で発行される二つのトークンが証券と判断されることが避けられないと公式サイトで発表しました。
具体的な原因について解説します。
規制対象となる二つのトークン
Basisにはステーブルコインを実現させるための二つのトークンがあります。
プロジェクトが撤退する原因となった大きな要因は、Basisの特徴となる「Bond」と「Share」トークンに問題が発生した点です。
BondはBasisが1ドル未満となった際に発行され、Sharaは余ったBasisを配布するような仕組みとなりますが、これらによって発行されるトークンが証券扱いとなることが明確であり、規制が避けられない状態となりました。
どうにか規制に沿いながら運用する方法を検討しましたが、Basisの特徴を生かすことは難しく、ユーザや投資家にとっても魅力がないプロジェクトとなることが避けられないことが判明しました。
あくまで自主撤退
今回のプロジェクト撤退は、米SECから警告を受けたのではなく、仕組み上の制限からの自主的な撤退となります。
しかし、今後ICOの規制ガイダンスが発表される中、規制に引っかかるようなプロジェクトはBasisだけとは限らない状態です。
Basisのプロジェクト解散のような事態は規制が強まるにつれて増えていくことが予想されます。
ステーブルコインを含む詐欺的なICOが増えたことによる規制強化

2017年は仮想通貨元年と呼ばれた年であり、ICOの件数は次々と数を増やしていきました。
しかし、その一方資金集めを目的とした詐欺的なICOも増加しており、ICO=詐欺というイメージが強まる程に状況は悪化しています。
その為、各国では投資家を保護するためにICOの規制を強化する方向性を強めています。
具体的には各国でどのようなICO規制がされているか概要レベルではありますが解説します。
ICO禁止(中国・韓国)
中国は仮想通貨に関する規制が厳しく、ICOを禁止としています。
これはICOの9割以上は詐欺にあたる違法な資金調達である為、投資家を保護する名目で禁止としています。
中国でのISO禁止と言う大きな動きをきっかけに、各国でICOの規制が動き出しています。
しかし、中国ではブロックチェーン技術の評価自体はされており、ブロックチェーンという技術自体には肯定的な姿勢も見せています。
また、韓国も中国と同様にICOを禁止としています。
しかし、韓国では仮想通貨の投資が盛んであり、韓国内の大手ITも国内のICOを断念し、シンガポールといった海外でのICOを実施しています。
政府としてはブロックチェーン産業を育成したいことから、ICOの禁止を解くような動きが見られているものの、2019年3月時点もICO禁止令は解除されておりません。
中国と韓国の規制について詳しくは下記の記事をご覧下さい。
ICO規制(アメリカ)
アメリカ証券取引委員会(SEC)はHowey Testという基準を設け、トークンが有価証券にあたるかどうかの判断基準を設けています。
これにより認可を受けないICOは証券取引法規制の規制対象となることを発表しました。
Howey Testは以下の基準です。
- お金による投資となるか?
- 投資から利益を期待できるものか?
- 共通企業に対する投資か?
- 他社の努力により利益を生み出すか?
アメリカの規制について詳しくは下記の記事をご覧下さい。
ステーブルコインBasis(ベーシス)が廃業!今後のステーブルコインはどうなる?

大手のベンチャーキャピタル企業からの期待の声が上がっていたBasisですが、米国規制ガイダンスの規制に引っかかることにより、廃業へと追い込まれる結果となりました。
今後はICOによる規制が強まる方向性にあり、Basisのように廃業へと追い込まれるプロジェクトが次々と増加していくことが大きく懸念されます。
ICOの規制は避けられぬ現状であり、各国でもその動きは強まっている状況です。
そもそもなぜICO規制されるのか

ICOとは仮想通貨における資金調達のことを指しますが、現状ICOには大きな問題があります。
通常、株式のIPOでは企業は証券取引所への上場基準を満たしているかどうかの厳重なチェックが入りますが、ICOの場合はこのようなチェックが入らず、事業が独自のトークンを直接インターネット上で販売を行います。
その為、必ずしもICOした仮想通貨のトークンが上場させる保証もなく、第3者の監視もないことから事業者が自由にICOを実施することができます。
これにより開発資金を集めたものの、開発が全く進まなかったり、ひどい場合は姿を晦まして資金を持ち逃げする詐欺目的のICOが多発している状況です。
このようにICOが無法地帯になっていることを問題視し、中国や韓国ではICOを禁止にしたり、各国でもICOの規制を強化するような動きが見られています。
アメリカでは仮想通貨におけるトークンをHowey Testを用いて証券かどうか判断し、もし証券であれば規制の対象とするよう、ICOの規制を強めました。
今後、各国が同じような規制を取り組んでいった場合、規制に引っかかるような仮想通貨が次々と増加し、大暴落するような危険性が非常に高いです。
今後は証券ではないと認定されている仮想通貨であればプロジェクトが頓挫するようなことがなく、安心かつ大きく期待できる仮想通貨となります。
ICOが規制されることによって仮想通貨の可能性が狭まっていくのはやむを得ない状況ではありますが、この規制が一概にデメリットとも言い切れません。
投資家にとっては詐欺ICOに投資するリスクが減ることになるので、ありがたい事ではあります。
しかし、実際のICOはホワイトペーパーによるプロジェクトの目的や企画内容を公表しており、中身の伴っていないようないい加減なICOは投資家に相手されなくなることも考えられます。
つまり、投資家間で詐欺まがいのICOに乗らずに選別できるようになれば、自然とそのような詐欺まがいICO案件は数を減らすことも可能性としてはあります。
ですが、現状は詐欺に引っかかってしまうような投資家が多いことは事実です。
やはり詐欺が増えている以上、ICOの規制が必要だというのが現実です。
- ビットコイン詐欺の手口を完全解説!発言や勧誘・詐欺に合わない為の対策まとめ
- 【最新有】ノアコインは詐欺確定?上場先は?現在価格が悲惨?泉忠司の謝罪文やwiki的経歴・評判・口コミ・今後の将来性まとめ
- 【衝撃】ICO割れが起きる原因とノアコインがICO割れした理由を徹底解説!
- ICOの成功率は50%!ICOの約半数は全く資金調達できていない実態が明らかに
- ICOとIPO(新規公開株式)の違いや共通点・デメリットの対象法を徹底解説!
- 【厳選】ICOの詐欺割合と本当にあったICO詐欺一覧3選!
- 騙されるな!仮想通貨詐欺の手口やカラクリが巧妙過ぎる。騙されない為に知っておくべきポイント4選
- AIトレード(AI Trade)は詐欺か?口コミから見る評判で確信に迫る!登録方法とログイン方法、使い方も写真付きで解説!
ステーブルコイン自体は将来性有望であるものの、ICO規制がネックとなる

ステーブルコイン自体は、現状期待されている仮想通貨であり、既にいくつかのプロジェクトの開発が進んでいます。
現状、仮想通貨はほとんど投資目的でしか利用されておりません。
しかし、ステーブルコインにより仮想通貨が実用的になれば、一気に仮想通貨は普及すると考えられます。
ICOの規制によってBasisのように撤退せざるを得ないプロジェクトが増加することも予想され、厳しい状況に立たされることが予想されます。
しばらくはICOの規制を強化する方向性とはなりますが、影響度合いを見て規制を緩和するなりといった動きがされていくと予想されます。
仮想通貨の可能性は狭まるが規制は必要。今後の課題とは

Basisのような期待されていたプロジェクトがICOの規制により、プロジェクト撤退にまで追い込まれたのは衝撃的な事実ではあります。
今まで無法地帯と言われていたICOの規制により、このような優良なプロジェクトが撤退せざるを得ない状況になるのは非常に残念なことではあります。
しかし、ICOの詐欺が増え続ける現状では規制はやむを得ない状況です。
難しい問題ではありますが、上手くICOの規制と付き合っていかなければならないのが今後の仮想通貨の課題となります。










































