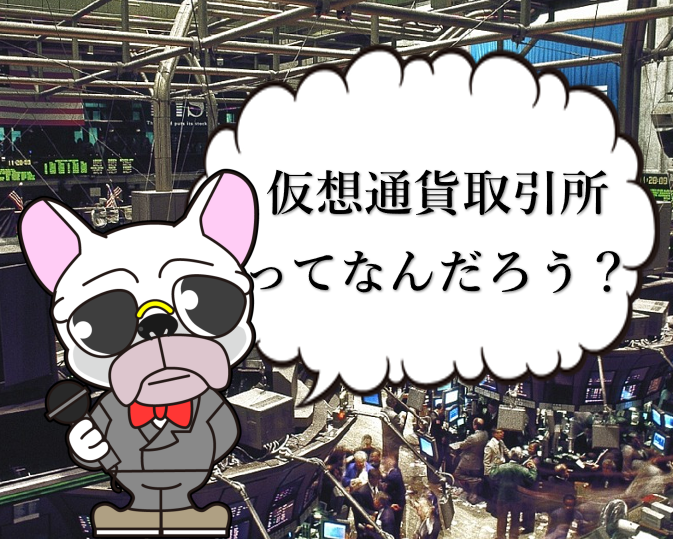
2017年12月に、爆発的にその名を世間に広めた仮想通貨。
BTCの急騰を耳にした若年層の投資未経験者が一斉に「仮想通貨取引所」の口座を作り始めました。
いわゆる「出川組」と呼ばれる人達ですね。
中には仮想通貨取引所と販売所の違いを知らずに、口座を作った人もいるとか。
しかし、仮想通貨を購入する為には、仮想通貨取引所の口座を作成しなければなりませんね。
では、仮想通貨取引所とはそもそも何か?販売所と取引所の違いは?
はたまた、みなし業者と仮想通貨交換業者の違いは何なのか?
と思っている人もいるでしょう。
この記事では、仮想通貨取引所とはそもそも何か?について掘り下げていきますので、
もう知っている人、あるいは知らない人もぜひ読み進めて下さい。
この記事の目次
仮想通貨取引所とはそもそも何か?
結論から言えば、仮想通貨取引所とは、紙幣や硬貨といった現物が存在しないデジタル通貨を交換できる銀行です。
例えば、銀行でお金(紙幣)を預けて振り込みをしたり、お金を引き出しますよね?
銀行がやっているかやっていないかは別として、基本的に銀行からいつでも紙幣を取り出すことが出来ます。
つまり、仮想通貨取引所とは、仮想通貨(銀行でいう紙幣)を買いたいと思ったら利用する窓口の様なものです。
具体的にはユーザーから注文を受けてビットコインなど様々な仮想通貨を売買したり、購入した仮想通貨を口座で管理するなどの業務を行っている業者のことをいいます。
正に取引所は仮想通貨の「銀行」と言えますね。
しかし、取引所には実際の店舗窓口はありません。
ですから、取引所を利用するユーザーはインターネットを使って交換業者のサイトにアクセスして仮想通貨の取引注文を出すことで仮想通貨を手に入れることができます。
では、次に仮想通貨取引所が誕生した歴史について見ていきましょう。
仮想通貨取引所が誕生した歴史
ビットコインが誕生したきっかけとなったのは、ピザでの取引ですが、ビットコインが誕生した2009年からたった1年後、2010年には早くもビットコイン取引所が誕生しています。
世界最初の取引所であるビットコイン取引所は2010年2月6日にNY証券取引所の隣の建物に約5万ドル(約550万円)で開設されています。
その取引所の創設者はニック・パノス氏であり、彼は世界最初の仮想通貨取引所の名前を「ビットコインセンター(Bitcoin Center)」と名付けました。
その後、法定通貨との交換の必要性から「BitInstant(ビットインスタント)」がビットコイン財団設立者のチャーリー・シュレム氏により設立されました。
残念ながら、BitInstantは法定通貨をビットコインに交換できる役割を持っていましたが、2014年1月以降姿を消しています。
しかし、BitInstantが誕生して以降、次々に取引所の開設が続いており、今では正確な取引所の数は把握出来ない程(※)です。
日本にも仮想通貨取引所は約20社ありますが、世界から見るとまだ少ないかもしれませんね。
仮想通貨取引所の役割
さて、仮想通貨取引所の役割と歴史に紹介したところで、仮想通貨取引所がしている主な業務について紹介しましょう。
仮想通貨取引所の役割は主に以下の3つです。
- 仮想通貨の販売(販売所)
- 仮想通貨取引の仲介(取引所)
- ユーザーの口座管理
1と2に関しては、後述する「販売所と取引所の違い」で紹介しますね。
ユーザーの口座管理
販売所と取引所では共通して、顧客が購入した仮想通貨を銀行の預金口座の様に顧客の口座を取引所で保管管理しています。
取引所によっては、仮想通貨の定期購入サービスや、顧客の仮想通貨を借りて決められた期日に数%程度上乗せして返却するサービス等もあります。
この様に顧客の口座管理も取引所の仕事なのです。
が!
残念なことに、今の仮想通貨取引所のほとんどがセキュリティ性の問題上、信頼は下落しています。
故に、個人でハードウェアウォレットを使って資産を管理したり、Ginco等のモバイルウォレットを活用し自分の資産は自分で管理するというのが今の投資家の考えです。
ですが、仮想の通貨を仮想の空間で取引・管理を行う場所こそが「仮想通貨取引所」なのです。
そのままですねw
2017年10月~12月の期間(いわゆる仮想通貨バブルの時期です)
BTC価格が上昇し口座作成申し込みが殺到し、口座登録完了まで通常3日程で完了するものが、1週間以上の時間を要していました。
この仮想通貨バブル期間中、特に会員数を大幅に増やしたのが、CoinCheck社です。
通称出川組と呼ばれる人達ですね。
CoinCheck社はこの時、仮想通貨交換業として莫大な利益を上げていました。
一説によれば、1000億円以上の利益を上げていたとか。(2018年3月決済では626億円)
しかし、莫大な利益を上げてからしばらくしない内に「CoinCheck社NEM580億円分ハッキング事件!」が発生しCoinCheck社は営業停止に追いやられました。
この被害の要因は、顧客の資産を常にホットウォレットにて保管し、セキュリティも脆弱のままであったからと言われています。
ですが、580億円もの大金が仮想通貨取引所から盗まれたことは、日本だけでなく世界中に衝撃が走りました。
その為、仮想通貨の価格は一気に大暴落。
2018年12月にCoinCheck社は全面的に営業を再開させましたが、以前のような盛り上がりはもうありません。
立て続けに起きたハッキング事件を皮切りに、各社体制を整え仮想通貨交換業業界は、リスタートしています。
これが、2017年~2018年が仮想通貨元年と呼ばれる由縁です。
仮想通貨取引所と販売所の違い
では先述した仮想通貨取引所と販売所の違いについて説明しますね。
一般的に仮想通貨を購入する場所のことを「取引所」と呼んでますが、
厳密に言うと「取引所」と「販売所」の2種類があります。
仮想通貨取引所
取引所の主な業務は、仮想通貨を「買いたい人」と「売りたい人」をマッチングさせることです。
いわゆる仲介役ですね。
仲介を行う際、両者から手数料を受け取って利益にしています。
しかし、販売所に比べて手数料は安く設定されている取引所が多いです。
これを市場引取や取引所取引と言ったり、板取引とも呼ばれたリと呼び名は様々。
こういった場所を提供する交換業者を、仮想通貨の「取引所」と呼びます。
仮想通貨販売所
逆に販売所の主な業務は、業者が直接ユーザーと仮想通貨の売買取引をします。
例えばユーザーから日本円を受け取って、その時のBTCレートをもとに、それに応じた額のBTCと交換するといった業務です。
業者は顧客に通貨を販売する時と買い取るときに数%の手数料を取ります。
このような相対取引のみを行う業者を仮想通貨の「販売所」と言います。
例としていえば、CoinCheck社が正に販売所と言えますね。(手数料が高いですからw)
仮想通貨取引所と金融庁の関係性
お次は金融庁との関係性。
先に言いますが、仮想通貨取引所(販売所も含めて)と金融庁はとても大きく関係しています。
まず金融庁が公式で発表している仮想通貨取引所の定義から見ていきましょう。
下記は法律で定められている仮想通貨交換業の定義の内容です。
仮想通貨交換業の定義
あ定義本体
『仮想通貨交換業』とは、『い』のうちいずれかを業として行う(※1)ことをいう
い 仮想通貨交換業の内容
ア:仮想通貨の売買or他の仮想通貨との交換
イ:『ア』の行為の媒介or取次ぎor代理
ウ:『ア・イ』の行為に関して、利用者の金銭or仮想通貨の管理をすること
※資金決済法2条7項(法律の一部を抜粋)引用:みずほ中央法律事務所
上記の様に定義されているということは、仮想通貨交換業は「金融業」と言えます。
この辺に付いてはまだまだグレーな所も多いですが、仮想通貨取引所は金融庁の管理下に置かれています。
ですので、仮想通貨取引所は、金融庁の指導と管理の元に運営をしていかなければなりません。
逆に金融庁は、取引所を指導・管理し、顧客の資産の安全性が確保されている取引所かどうか判断します。
当然、いい加減な運営をしている取引所に対し金融庁は業務改善命令等を発する事ができます。
ですから、仮想通貨取引所と金融庁は大きく関係しているのが分かりますね。
仮想通貨取引所のみなし業者と金融庁公認の違いについて
このフレーズ、一度は見たことや耳にしたことがあると思います。
「みなし業者」と「金融庁公認」
仮想通貨取引所にとって、金融庁からみなし業者とされているのか、あるいは金融庁公認であるのか。
どちらになっているかによって、取引所を利用するユーザーに信用性を与える大きな武器になり得ます。
みなし業者と金融庁公認になるかは、申請式で平成29年に、金融庁による仮想通貨交換業の登録制度が開始されました。
現在、日本国内には20もの仮想通貨取引所がありますが、「金融庁公認」とされている仮想通貨取引所(※2)は以下の16社です。
※2.厳密には仮想通貨交換業者と言われています。
| 仮想通貨交換業者一覧 | |
| bitFlyer(ビットフライヤー) | ビットバンク(Bitbank.cc) |
| GMOコイン | ビットトレード(Bittrade) |
| リキッドバイコイン(旧QUOINE) | ビットポイント |
| DMM bitcoin | Zaif(ザイフ)(※取引所としては存在しています) |
| フィスコ仮想通貨取引所 | ビットアルゴ取引所東京 |
| BTCボックス | SBIバーチャルカレンシーズ |
| マネーパートナーズ | BITOCEAN |
| Bitgate(旧FTT) | Xtheta(シータ) |
参照:平成30年9月3日現在金融庁「仮想通貨交換業者登録一覧」
金融庁は、平成29年に登録事業運用開始後、登録された事業者しか仮想通貨交換業を運営する事ができないよう規制をつくりました。
しかし、規制開始以前に事業を始め、顧客を獲得していた取引所も存在しています。
金融庁は顧客保護、市場の混乱を避けるといった目的から「例外」を作りました。
この例外こそが「みなし業者」です。
現存するみなし業者の代表的な取引所が「CoinCheck(コインチェック)」ですね。
以前は16社程あったみなし業者も今ではたった4社が残るのみです。
| みなし業者一覧 | |
| コインチェック | みんなのビットコイン |
| バイクリメンツ | LastRoots |
上記の「みなし業者」には、期限付きで現在営業が許可されています。
つまり、金融庁が定める期日までに金融庁から正式な許可をもらわなければ、みなし業者は営業停止となります。
ここまでが、みなし業者と金融庁公認取引所との大きな違いです。
ちゃんと理解できています?相場が下落しない内に先に進みますよ?
仮想通貨取引所を選ぶ際のポイント
はい。
では「みなし業者」と「金融庁公認」の違いに理解して頂けたところで、仮想通貨取引所を選ぶ際のポイントを紹介しますね。
すでに利用している、あるいは利用しよう思っている仮想通貨取引所が「金融庁公認」となっていても、大事な資産を取り扱う取引所の選び方は知っておきましょう。
なぜならば、大事な資産は自分自身で確認して守ろう!ということですね。
まずは、仮想通貨取引所の安全性はどの程度確保されているのか、サーバーは強固なものになっているのか、取扱通貨の種類や数、取引手数料の安さ、そして最後に顧客のレビューを参考にしましょう。
内容をまとめますと、
- セキュリティ性の確保
- サーバーの強さ
- 取扱い通貨の数
- 取引手数料
- 評判
上記の中から最も重視すべき点は評判ですね。
すでに利用している顧客の評判をしっかりチェックしていれば、セキュリティやサーバーの強さ、取扱い通貨の数、取引手数料使い勝手の良さのほとんどが分かります。
評判については、TwitterなどのSNSでツイートされていますから、Twitterの検索画面で「○○ 評判」と検索したら沢山の評判が出てきますから、仮想通貨取引所を選ぶ際に参考にしてみてくださいね。
日本国内の取引所がどれほどセキュリティ性が高いのか、ランキングでも発表されていますから、気になる人は下記をチェックして下さいね。
仮想通貨取引所のまとめ
仮想通貨取引所とはそもそも何か?について説明しましたが理解できました?
仮想通貨取引所は仮想通貨にとっての銀行で、様々なサービスを行っている事がわかりましたね。
取引所にはそれぞれ特色が違いますから、自分に合った取引所を見つけていくことが重要です。
そして、取引所も1つに絞るのではなく、リスク分散の観点でいくつかの取引所を併せて使っていくことでより安全に仮想通貨取引を行うことができるでしょう。
取引所の口座を作る所からが大切な資産を守る第一歩になってきますので、妥協することなくしっかり選別していきましょう。








































