
仮想通貨などの投資取引を行う際だれでも目にする「ボラティリティ」という言葉。
では一体、このボラティリティの本質はどこにあり、どのように仮想通貨投資・トレードに生かせばいいのでしょうか?
- ボラティリティって何だろう?
- ボラティリティが高いものには投資しちゃダメ?
- 仮想通貨のボラティリティはどれくらい?
- 仮想通貨のボラティリティが高いのはなぜ?
この記事では上記のような疑問に応えます。
ボラティリティが高い理由についても、信頼度の高い業界の著名人の発言を引用しつつ解説しています。
是非最後までご覧ください。
この記事の目次
仮想通貨のボラティリティの意味とは

仮想通貨のボラティリティ(Volatility)とは、ビットコインやリップルなどの価格変動性を表した数値のことを意味します。
仮想通貨に限らず、一般に投資対象として扱われる資産は価値変動を繰り返しており、投資家はその価格差にベットすることで利益を得ます。
- ボラティリティが高い
→少額のベットで多額の利益を獲得可能 - ボラティリティが低い
→多額のベットでも少額の利益しか獲得できない
またボラティリティという言葉は、以下のような理解の上、投資対象の危険性を表す数値としても用いられます。
- ボラティリティが高い→その分損する可能性も高い
- ボラティリティが小さい→損する可能性が低い
ビットコインなどの仮想通貨は、ボラティリティが高い投資対象として認知されており、仮想通貨投資で「億り人」となった人もいれば、すべての資産を失った人も存在します。
ボラティリティという言葉は、どちらかといえば前者のようなプラスの意味よりも、後者のようなマイナスの意味でつかわれることが多いです。
- ボラティリティが大きい資産は危険
- 仮想通貨はボラティリティが大きい
いずれにせよ上記2点は事実ですので、仮想通貨投資を考えている方は、そのあたりも十分に検討する必要があるでしょう。
仮想通貨のボラティリティは2種類ある

そもそもボラティリティというのは「金融工学」上の専門用語で、数式的には以下の様に定義されています。(「σ」部分がボラティリティ)
上記の計算式は「株価の幾何ブラウン運動モデル」という計算方法です。
ただし、上記の計算式はあくまでも「モデル」。
実際の株価・仮想通貨のボラティリティを求める際には、B(t),σ,μなどに、ある数式をインプットする必要があります。
今現在、株価・仮想通貨のボラティリティを求める際に利用されている計算式は以下の2つ。
- ヒストリカル・ボラティリティ(HV)
- インプライド・ボラティリティ(IV)
計算式の解説をするとやや難しくなってしまうので、それぞれ”概念”の解説を行います。
ヒストリカル・ボラティリティ(HV)
ヒストリカル・ボラティリティとは、過去の値動きから求めたボラティリティの事です。
計算手順は以下の通りです。
- 過去の価格データ(値動き)をある一定期間ごとにピック
- ピックした各データの平均値を算出
- ある一定期間ごとに価格が何倍になっているか?を分析
- 分析結果をもとに、「それぞれの比率のぶれやすさ」を算出
この「比率のぶれやすさ」というのが「σ」の値であり、すなわちボラティリティとなります。
インプライド・ボラティリティ(IV)
インプライド・ボラティリティは、「オプション取引」の過去データから価格変動の激しさを予測するボラティリティ計算方法です。
ヒストリカル・ボラティリティが、「過去のデータから今のボラティリティを算出」するのに対し、インプライド・ボラティリティは「未来のボラティリティを予測」します。
オプション取引の性質上、取引において必要な情報は「今のボラティリティ」ではなく「未来のボラティリティ」であるため、オプション取引においてはインプライド・ボラティリティが用いられるのです。
取引所によってボラティリティの値は異なる
当たり前ですが、利用している取引所によってボラティリティの値は異なります。
それは計算方法が異なっているからではなく、計算に用いる「価格」が異なっているからです。
以下の画像は、過去6か月間におけるボラティリティの推移です。
大まかなトレンドは同じですが、ボラティリティの値が取引所ごとに異なっていることがわかりますよね。

上記は、アメリカドル(USD)を取り扱っている仮想通貨取引所を比較したものです。
日本の仮想通貨取引所におけるボラティリティの推移を確認したい方は、以下リンクをクリックしてください。
>>>ボラティリティの推移
仮想通貨と円・ドル・原油のボラティリティを比較

ここまで、「仮想通貨のボラティリティは高い」と繰り返しお伝えしてきましたが、実際、仮想通貨のボラティリティはどれほどの高さなのでしょうか?
ここからは、円・アメリカドル・原油などの主要資産とビットコインのボラティリティの高さを比較しつつ、上記の疑問に答えます。
ボラティリティの最高値で比較
ここでは、「ボラティリティの最高値」で各資産のボラティリティ大きさを比較します。
今回比較に用いる資産は以下の4つ。
- ビットコイン
- アメリカドル
- トルコリラ
- 原油先物
それでは以下の表をご覧ください。
| 資産名 | 最高ボラティリティ |
| ビットコイン | 34.34% |
| 米ドル | 1.63% |
| トルコリラ | 7.94% |
| 原油先物 | 4.28% |
※上記の表は日本円ペアの場合で表しています。
ビットコインのボラティリティが圧倒的に大きいことがわかりますね。
ボラティリティの推移で比較
続いてはボラティリティの推移を見てみましょう。
下記画像は、GMOコインがまとめた2017年8月~11月までの日次ボラティリティの推移表です。
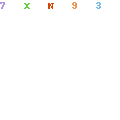
基本的に5%~10%の高いボラティリティを維持。
2017年9月中旬や、仮想通貨バブルが最高潮に達した2017年11月後半のボラティリティは、30%を超えるすさまじい数値を記録していることがわかります。
仮想通貨のボラティリティが高い理由

仮想通貨のボラティリティが高い理由には、いくつかの説があります。
もちろん、そのどれもが必ずしも正しいというわけではなく、信頼性や根拠に欠けるものも多いのが事実です。
そこでこの記事では、信頼に足る業界の著名人の発言、そして数字などのしっかりした根拠を持った情報から、「仮想通貨のボラティリティ」が高い理由を解説します。
仮想通貨のボラティリティが高い理由は下記の通り。
- 仮想通貨は本質的な価値を持たない
- 規制監督の欠如
- 資本の欠如
- 取引板が薄い
- ミレニアル世代の集団心理
これらは、ロサンゼルスの大手ソフトウェアコンサルティング会社である「ISBX」の共同創設者兼社長を務めるArthur Linuma氏の発言をまとめたものです。
同氏は、モルガンスタンレーの元Finraライセンストレーダーで、仮想通貨トレーダーとしても著名なエンジェル投資家という顔も持つ人物です。
仮想通貨は本質的な価値を持たない
例として、仮想通貨に比べてボラティリティが低い「株式市場」と「仮想通貨市場」を比較してみましょう。
株式を発行している企業は、様々な製品を開発したり、収入を得たり、数千という社員を雇用することで企業の安定性・評価を保ちます。
しかし、仮想通貨はそれらを一切行わず、配当もない。
すなわち、「価値の判断」が困難なのです。
- 今の仮想通貨価格は高いの低いのか?
- 割安なのか否なのか?
- どのような価値を秘めているのか?
それらのいわゆる「ファンダメンタル」的な評価基準があいまいなため、仮想通貨市場は人間の不安定な感情に支配されてしまうのです。
逆言えば、仮想通貨ユーザーに対して大きな影響力をもつメディアは、情報発信1つでその「市場の感情」を支配できるということです。
規制監督の欠如
仮想通貨最大の特徴である「中央管理者の不在」がデメリットになりえます。
仮想通貨は今現在、世界中で取引され知名度も高まり続けています。
日本・アメリカを含め、世界中の政府がその規制に奮闘していますが、規制が成熟しているわけではありません。(規制が一部にとどまっている)
このように、全体的な規制が進んでいない状況下では、容易な市場操作や大きなボラティリティが生まれやすくなるのです。
詳しくは後述しますが、仮想通貨市場拡大のカギである「機関投資家の参入」も、規制が整わない限り、当分ありえない話なのです。
資本の欠如
ベンチャーキャピタルやヘッジファンド、一部の富裕層の個人が仮想通貨ファンであり、投資を行っているという事実は否定できません。
しかし、それ以外の多くの機関投資家は、今のところ仮想通貨市場を傍観しているのみで、参入の気配はありません。
仮想通貨の先物取引やビットコインETFを含めた仮想通貨ETPなど、それらの勢いは限定的だといえるでしょう。
多くの金融機関・銀行の責任者は、仮想通貨・ブロックチェーンの有用性について肯定的であるものの、そこに大きな資本を投入する約束はしていません。
市場拡大が仮想通貨の直近の課題であり、機関投資家等の大量の資本が流入しない限り、ボラティリティは小さくならないでしょう。
板が薄い
仮想通貨取引を行う投資家たちは、ハッキングによる流出リスクを抑えるため、仮想通貨取引所に資産を保管するようなことはしません。
すなわち、多くの仮想通貨取引所の注文板には取引可能な資産がほとんどなく、いわゆる「板が薄い」状態です。
この板が薄い状態では、大量の資金を持ったトレーダーが大きな成行注文を行った場合、市場の方向操作が可能になります。
いわゆるスリッページと呼ばれるこの現象は、仮想通貨市場ではたびたび確認されており、それは株式市場の比ではありません。
このように、大きな力(お金)を持ったトレーダーに影響されるようでは、ボラティリティを小さく抑えることは不可能と言うことなのです。
ミレニアル世代の集団心理
仮想通貨の認知は世界的に広まっているものの、ブームが起こっているのは1980年代~2000年初期の間に産まれた”ミレニアム世代”です。
この世代のユーザーは「長期投資」の経験が無いため、比較的短期のトレードを行いがちです。
仮想通貨ユーザーの多くが短期トレードを行うと、それだけ価格変動機会も多くなるため、結果としてボラティリティを大きくする要因になります。
また、一攫千金を狙った、自己資本以上の過剰な投資を行う若者が多いことも、理由の一つです。
まとめ
仮想通貨のボラティリティについてご理解いただけたでしょうか。
一見、「損してしまう」といったネガティブなイメージが強い「ボラティリティ」ですが、実はそれと同じくらい「得する」可能性も高いのです。
ただ、トレードに関する知識や経験が浅いトレーダーが多いため、損する人が続出しているというわけなのです。
移動平均線やMACDなどの基本的なトレード知識をおさえつつ、少額トレードで経験を積むと、損せず、ボラティリティの高さを味方にできる日が必ず来ます。
※自己資本を超えるほどの過剰な投資は辞めましょう。








































