
バレンタインデーを機に、仮想通貨市場が活気付いています。
きっかけとなったのは、仮想通貨に否定的であったはずの、JPモルガン・チェースが独自コインを発行すると発表したことでしょう。
しかもそのプラットフォームがETH(Ethereum:イーサリアム)だったことから、市場が一気にETH人気になりました。
その上、CFTC(米商品先物取引委員会)にETHの先物取引でポジティブな内容の報告書が提出されたこと。
2019年2月28日からは、Constantinople(コンスタンティノープル)と呼ばれるアップデートが始まることなど、これらの好材料を受けて市場は一気にイーサリアムに引っ張られるように、上昇に転じました。
執筆時点では、その勢いはまだまだ続きそうです。
今回は、その価値を再び見直されつつあるイーサリアムについて、特集してみました。
今だからこそわかるイーサリアムの再検証と、その可能性を探っていきます。
この記事の目次
イーサリアム(ETH)のwiki的基本情報
| 仮想通貨名 | Ethereum(イーサリアム) |
| トークン名 | ETH |
| 公開月 | 2013年12月22日 |
| 開発組織 | イーサリアムプロジェクト |
| 開発者 | ヴィタリック・ブテリン |
| 発行上限 | - |
| 発行枚数 | 103,764,476ETH |
| アルゴリズム | Ethash |
| 中央機関 | - |
| 公式HP | ethereum.org |
| 公式ホワイトペーパー | Ethereumのホワイトペーパー |
| ブログ | Ethereum |
| @ethereum | |
| @ethereumproject | |
| ethereum community | |
| TelegramID | - |
| YouTube | Ethereum |
イーサリアム(ETH)とは/目的
イーサリアムそのものは、仮想通貨の名称ではなく、「イーサリアムプロジェクト」の実現のために必要なものとして提供されているプラットフォームの総称です。
この中で使用される通貨がイーサ(ETH)と呼ばれるものですが、イーサリアムを通貨として受け止めている人も多いため、ここでもイーサリアムを通貨として表現することにしますね。
イーサリアムは、ビットコインに次いで時価総額第2〜3位の仮想通貨であり、ヴィタリック・ブテリンによって2013年から開発され、2015年頃には日本でも取引が行われました。
スイスの非営利団体である「イーサリアム財団」によるイーサリアムプロジェクトにおいて資金調達され、開発されています。
現在もなお開発され続けていますが、イーサリアムを管理する中央機関のような団体は存在しません。
イーサリアムでは、ビットコインから提供されたブロックチェーンを利用するのではなく、新規のブロックチェーン上で、どのようなアルゴリズムでも包括できる「チューリング完全」である言語を装備しています。
これにより、契約を自動化するスマートコントラクトの為の基盤となることを目的としています。
イーサリアム(ETH)の価格が高騰するきっかけとなったJPMコインとは
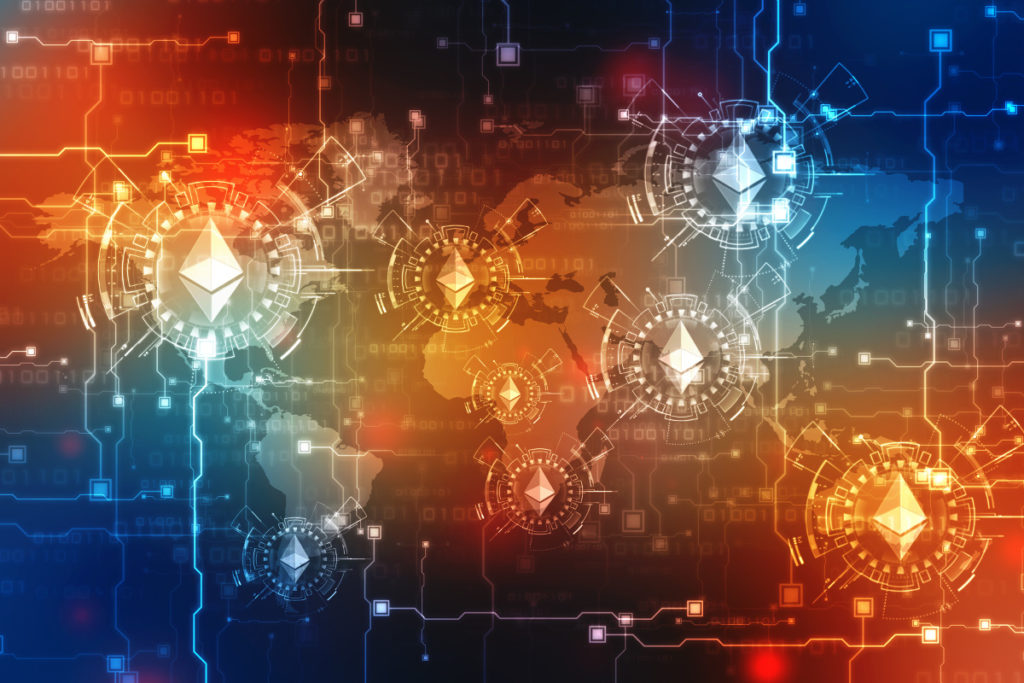
イーサリアムの再検証の前に、今回イーサリアムを見直す発端となったJPMコインについて少し触れたいと思います。
JPMコインは、ETHプライベート版ネットワークのQuorum上に構築されると発表されています。
つまりJPMコインは、ドルペッグ制のステーブルコインに似た性質を持たせた、プライベートトークンであり、本来の仮想通貨とは異なるものです。
JPMコインは、以下のことに使われるとされています。
- 大企業向けの国際送金
- 証券取引
- ドルの代替する通貨
アメリカの大手銀行の中で、JPMコインのようなデジタル通貨を発行すると発表したのは、JPモルガンが最初になります。
つまり先駆者としてのステータスを持つことになり、Fortune500(アメリカのフォーチュン誌が年1回発表する全米上位500社の総収入ランキング)の企業の80%で企業間支払いの市場シェアを占めることがJPMコインの強みとなると見られています。
JPモルガンCEOがBTCに対して批判的な人物だったことを差し引いても、今回のJPMコインの発表が、具体的なイメージで発信されていると思いませんか?
実は、今回発表されたJPMコインのモデルケースが、すでにイーサリアムのプラットフォーム上にあったとしたらどうでしょうか?
イーサリアムの「プラットフォーム・スマートコントラクト・DApps」の関係

JPMコインのモデルケースがETHのプラットフォーム上にあったことをお伝えする前に、まずはプラットフォーム・スマートコントラクト・DAppsの関係性についての説明したいと思います。
このプラットフォーム・スマートコントラクト・DAppsについては、多くのサイトで個々の説明はなされているものの、全体像のイメージというのは、つかみにくいように感じます。
そこで、理解しやすいように具体例を挙げて説明していきます。
まず全体のイメージですが、ここでは鉄道のイメージで説明していきます。
JRでも、私鉄でも、地下鉄でも何でもいいです。
ブロックチェーンは鉄道会社で、プラットフォームは線路のイメージです。
このように捉えた時、スマートコントラクトは駅になります。
例えば、東京から大阪に向かうのと、東京から仙台に向かうのとでは、当然経路も違いますし、路線も異なります。
目的地までの経路上にある停車駅が、スマートコントラクトであり、その経路は決まっています。
そしてその経路を走る電車が、DAppsになります。
「のぞみ」「ひかり」「こだま」で停車駅が異なるように、目的駅に着くためには、その駅に止まる電車に乗る(DAppsを使う)必要があります。
電車の停車駅が決まっているのと同じように、スマートコントラクトに記された通りに走るDAppsに乗るのです。
たどった記録は、プラットフォームを通じて、ブロックチェーンに記録されます。
この時ユーザーは、直接プラットフォームやスマートコントラクトには触れません。
プラットフォームやスマートコントラクトは、すでに決まっていますので、触れる必要はありません。
ユーザーが選ぶのはどの電車(DApps)に乗るのかだけになります。
プラットフォーム・スマートコントラクト・DAppsの関係性を表すイメージを表にまとめてみました。
| 名称 | イメージ |
| DApps(ディアップス) | スマートコントラクトの上を走る電車 |
| Smart Contract(スマートコントラクト) | プラットフォームを結ぶ駅で、DAppsを誘導する |
| Platform(プラットフォーム) | 駅(スマートコントラクト)を結ぶ線路 |
| Block Chain(ブロックチェーン) | 線路を運営する鉄道会社 |
上の表ように、プラットフォーム・スマートコントラクト・DAppsには、それぞれに役割があり、受け持つ範囲が異なります。
イメージを絵にするとこんな感じになると思います。

そしてこの中で、ユーザーが触れるのは電車であるDAppsのみです。
プラットフォームやスマートコントラクトには、直接触る必要はありません。
だから逆にイメージしづらいとも言えます。
とは言え、プラットフォームやスマートコントラクトに直接触れられても困ります。
契約内容などの重要項目が記されているのですから、触れられては困るわけです。
線路内に人が入り込んだら、安全点検のために電車を止めるのと同じです。
ブロックチェーンに記された契約内容を変えようとして、プラットフォームやスマートコントラクトに触れようとするのは、クラッキングになります。
このようにそれぞれが役割を持ち、それぞれの役目を果たすことで、契約内容を自動化しているのです。
ではここからは、プラットフォーム・スマートコントラクト・DAppsが果たしている役割を詳しく説明していきます。
イーサリアム(ETH)の特徴

ETHの特徴その1:DApps(ディアップス)
まずはDAppsからです。
DApps(ディーアップス:Decentralized Applications)とは、自律分散型のアプリケーションのことです。
DAppsの定義としては以下の4点が挙げられます。
- 中央集権管理を受けない自立分散型のアプリケーションであること
- オープンソースで提供され、アプリケーションの変更などは参加者の合意のもとで行うこと
- ブロックチェーンによって、デジタル情報が安全に分散保存(管理)されていること
- アプリケーションでやりとりされる価値をトークン化し、ネットワーク健全性の維持に貢献した参加者への報酬として与えること
このDAppsは特別なものではありません。
私たちが毎日確認しているBTCもDAppsの一つだからです。
上記の条件をBTCは全て満たしています。
そしてそれはETHも同じです。
単一障害点(Single Point of Failure)がない
まず1つ目の特徴として、単一障害点(Single Point of Failure)がないという点があります。
DAppsはブロックチェーンと同じように、P2Pネットワーク上に存在するアプリケーションです。
つまり、単一のサーバで集中管理する必要が無い、分散型のアプリケーションです。
どこかのサーバが止まったとしても、他のサーバが動いていれば、機能を停止することがありません。
アップデートに関しても、合意が得られなければ更新することも不可になっています。
トラストレスである
2つめの特徴はトラストレスであることです。
このトラストレスとは、「信用する必要がない」という意味です。
DAppsは中央の管理者が存在しないため、参加者同士で直接取引することができます。
例えば、仮想通貨の取引所ではユーザ同士で取引ができますが、取引所がその間に入っていて、取引手数料を徴収しています。
その代わりに、秘密鍵の管理を取引所に預けることになります。
この場合、クラッキング(悪意のあるハッキング)の危険性がつきまといます。
対して、DEXと呼ばれる『分散型取引所』では、取引所の提供という意味で手数料を徴収されますが、金額は中央集権的な取引所より安く設定されています。
DEXでは、秘密鍵の管理は取引を行う個人に帰結しますので、クラッキングのリスクが大きく低下します。
そしてこの場合、取引所を提供している業者を信用する必要はなくなります。
トラストレス、「信用する必要がない」とはこういう意味なのです。
Transperency(透明性)が高い
3つ目の特徴は、Transperency(透明性)が高いということです。
繰り返しになりますが、DAppsはP2P上に展開されたプログラムを利用して動作します。
そのプログラムはオープンソースで公開されていて、そのネットワークに参加している人であれば、誰でも閲覧することが出来ます。
一方で、一般のゲームアプリのプログラムは簡単に診ることはできません。
ある時、とあるゲームアプリのガチャの当選確率を、不正に操作していたのではないかという疑惑が出たことがあります。
DAppsであれば、プログラムの内容は公開されていますので、不正をすぐに発見することができます。
ガチャの当選確率を不正に操作するようなことは、できなくなるのです。
DAppsを語る上で注意しておきたいのが、『中央集権管理』と開発者とは異なるということです。
DAppsがアプリケーションソフトである以上、開発・運営・アップデートは必須です。
DAppsを管理・運営する上で、開発者や開発チームは絶対に必要なのです。
またそうでなければ、ユーザーは安心して使うことができません。
ですが、アプリケーションのアップデート等の際は、開発者が中心になって進めることが多いです。
その時に、この開発者を中央集権的だとする見方が起こり易いのです。
これはBTCや、ETHのアップデートでも起こることで、中央集権的な考えを混同した見方と言えます。
イーサリアム(ETH)の特徴その2:スマートコントラクト
Smart Contract(スマートコントラクト)は、日本語に訳すと『契約の自動執行』となるでしょう。
このスマートコントラクトの考え方は、BTCやETHが世にでるもっと前、1997年にアメリカの法学者・暗号学者のNick Szabo氏が発表した論文『The Idea of Smart Contract』に、その概念が記されています。
Szabo氏はスマートコントラクトの具体例として、自動販売機をあげています。
- 購入したいモノを販売する自動販売機に代金を投入する
- 購入したいモノのボタンを押す
この2つの条件(契約)が合致すると、自動販売機からは購入したものが出てきます。
ユーザーは出てきたモノを確認して、選んだ商品が出てきたかをチェックします。
非常に単純で簡単な仕組みとやり取りですが、間違いなくこれは契約の自動執行になります。
これをETH上のプラットフォームでどのように動かしているのでしょうか?
自動販売機と同じように、契約をプログラムで定義して、定義された条件に合致した場合は、取引が完了するようにします。
先にお伝えした鉄道のイメージでは、停車する駅としない駅を決めているのが、スマートコントラクトになります。
ブロックチェーン上のプラットフォームにスマートコントラクトを配することで、契約条件に合致した取引が行われた場合は契約完了となり、条件に合致しない場合は契約は執行されなくなります。
この時に取引に使われるのは、仮想通貨やトークンといったデジタル通貨になります。
このように、契約の執行が自動で行えるようにするのがスマートコントラクトの最大の特徴です。
このスマートコントラクトが一番使われたのが、ICO(Initial Coin Offering)です。
一般的にICOに参加する時は、ICOを行うプロジェクトが用意したスマートコントラクトの内容を信用(信頼)して、特定のアドレスに仮想通貨を送る。というプロセスを踏みます。
これは先ほど紹介した、自動販売機の例の1.になります。
そして、ICOのローンチ後にトークンが配布されることになります。
これが自動販売機の例の2.に当たります。
このようにスマートコントラクトを使うと、契約全てを自動化できる上に、条件に合う場合にのみ契約が執行されるので、契約相手を信頼する必要がなくなるのです。
これはDAppsでお伝えした、トラストレスと同じ意味です。
先ほどの自動販売機を例に言えば、ジュースの自動販売機から、タバコやお菓子が出てくることはありません。
私たちは、自動販売機に並んでいるサンプルを見て、それを信用(信頼)して商品を購入しています。
自動販売機に並んでいるサンプルと違うものが出てくると、疑っている人はまず居ません。
ですが、ごくたまに違う商品が出てきたり、商品が出てこなかったりするのです。
その場合は、自動販売機に書かれている連絡先に連絡を入れて、起こったトラブルを解決する必要があります。
実は、このような契約トラブルは、世の中に溢れています。
実際に契約が守られなかったり、契約違反があったりするトラブルは枚挙にいとまがありません。
例えば、最近は少なくなりましたが、一時期、食料品の産地偽造が多く取り上げられたことがありました。
この食料品の産地偽造を、スマートコントラクトを利用するとどのように変わるのでしょうか。
食料品の取引をスマートコントラクトで自動契約化する場合、産地偽造が無いようにするには、契約条件の中にトレーサビリティ(※1)が必要になります。
この場合、トレーサビリティのデータはブロックチェーン上に記録されており、誰もが閲覧可能です。
従来の販売経路では、店舗や流通経路を信頼するしかありません。
商品の価値を高めるために、生産者のシールが貼ってあったりしますが、そういったものにコストをかける必要もなくなるのです。
購入者が携帯のアプリなどで簡単にトレサビリティのデータを確認できるようにしていれば、その場で商品の産地、栽培や飼育過程、加工、製造、流通に至るまでの情報を受け取ることができます。
それは生産過程において、ブロックチェーンに刻まれるようになっていますので、新たにコストをかける必要はありません。
消費者は安心して商品を購入することができるようになり、産地偽造は不可能になります。
このように、スマートコントラクトを利用すると、産地偽装などの『契約のトラブル』を徹底して抑えることができます。
また自動で契約ができるので、中間にかかるコストを減らすこともできるのです。
スマートコントラクトはこのように、契約を自動的に行えるだけでなく、契約のトラブルを減らし、品質保証もコストの削減もできるようになるのです。
実際にこうした取り組みは、もうすでに実用化されています。
エチオピアのコーヒーの栽培・選別・精製工程をブロックチェーンに記録し、スマートコントラクトで品質保証をしています。
コーヒーがオークションにかけられる時、ブロックチェーンに記録されたデータが、品質保証となるので、購入者は安心して競り落とすことができます。
イーサリアム(ETH)の特徴その3:プラットフォーム
さて先ほど、「JPMコインのモデルケースが、すでにイーサリアムのプラットフォーム上にあった」とお伝えしました。
それはイーサリアムのプラットフォーム上に配されたスマートコントラクトとDAppsの中に、JPMコインとほぼ同じ条件を満たすものがあったということです。
JPMコインの条件は、以下の3つです。
- 大企業向けの国際送金
- 証券取引
- ドルの代替する通貨
「1. 」と「2. 」は、スマートコントラクトの契約条項を設定すれば済みます。
取引に参加するユーザーの条件を、スマートコントラクトに書き込めば良いだけです。
そしてポイントになるのが「3. ドルの代替する通貨」です。
ステーブルコインの中に、ETHで米ドルとペッグしたものがあります。
詳細は後述しますが、プールしたETHを米ドルとペッグする担保として保管し、ステーブルコインを発行しているものがあります。
それがETHのプラットフォーム上に既に存在し、そのプラットフォーム上にはスマートコントラクトとDAppsがあります。
このステーブルコインの仕組みを、JPMコインは真似ていくのだと推察します。
ETHをプールするのではなく、JPMコイン用にプールした米ドルを担保に、JPMコインはステーブルコインの性格を持たせたコインとなるでしょう。
このように、イーサリアムのブロックチェーン上には、様々なスマートコントラクトが存在し、その内容によって、自分たちが利用したい内容に変えることが可能です。
ETHのプラットフォーム、スマートコントラクト、DAppsはオープンソースですので、開発に関してはETH開発チームだけでなく、多くのエンジニア達の力を借りることが可能です。
こうした開発力の高さと使い易さも、ETHプラットフォームが選ばれた理由の一つでしょう。
今回はETH特集の第1弾として、JPMコインがETHプラットフォームをベースにしている理由や、ETHのスマートコントラクトやDAppsについて、解説してきました。
ただ、ETHの内容としては、まだまだ語り尽くせてはいません。
続きを順次アップしてまいりますので、楽しみにお待ちください。
イーサリアム(ETH)のアップデートの歴史について

2015年7月:Frontier(フロンティア)
最初のアップデートは、2015年7月に行われたフロンティアアップデートです。
イーサリアムの基本機能の実験的な導入により、実装された機能の不具合を修正しています。
2016年3月:Homestead(ホームステッド)
次のアップデートは、2016年3月ホームステッドアップデートが行われました。
このアップデートでイーサリアムはより安全性のあるプラットフォームへと進化しました。
そして、この時点で基軸通貨のイーサ(ETH)による取引が行われ、イーサリアムトークンのやり取りが多くの人によって行われました。
しかしこのアップデート中にイーサリアムのプラットフォームをベースとしたThe DAOというプロジェクトが攻撃を受けてしまいます。
その結果、緊急処置としてハードフォークが2017年7月に行われ、イーサリアムとイーサリアムクラシックと分裂することになりました。
2019年3月:Metropolis(メトロポリス)
第3段階でのアップデートハードフォークであり、以下の2つのアップデートにより構成されているものです。
- ビザンティウム
- コンスタンティノープル
このうちビザンティウムアップデートは2017年10月に行われ、コンスタンティノープルアップデートは2019年3月に実施され成功しています。
ビザンティウムでは、アルゴリズムのプルーフオブワーク(PoW)からプルーフオブステーク(PoS)への移行への準備処理が行われました。
コンスタンティノープルでは、現在開発にあたっていますが、実装することで処理が止まる不具合が見つかっていた為、度々延期になっていましたが2019年3月に無事に成功しています。
未定:アップデート4:Serenity(セレニティ)
セレニティは現状では最終段階とされるイーサリアムのアップデートです。
このアップデートによりイーサリアムプロジェクトの安全性がもたらされると言われており、このアップデートを経ることでプルーフオブワークからプルーフオブステークへの移行が実施される予定です。
セレニティアップデートに移行後はセキュリティに基づく分散型アプリケーションに向けたプラットフォームが形成される予定です。
イーサリアム(ETH)の評判・口コミ
ここから日本におけるイーサリアムへの評判及び口コミを見ていきましょう。
イーサリアムが並行チャネルを今まさに下抜けんとす、といった状態だったのでイナゴショートしたけど反応薄かったなw pic.twitter.com/S2HDgA7RtS
— おまつ (@dy_fv2) 2019年3月7日
期待する声の順位ではXRPやBTCに負けているものの、他のアルトコインに比べたらやはり今後に期待する声は多いみたいですね。
XRPが米国とラテンアメリカで最も人気な仮想通貨となる
Upholdでの米国とラテンアメリカが対象
①XRP 59.2%
2.BTC 27.3%
3.ETH 6%リップルは上場アンケートでも過半数51%の票を獲得!
日本で1位を記録したけど、今後は米国での人気が高まれば嬉しいね!https://t.co/ojRSSoIVsU— リクサルリビト (@Rikusaru_Ribito) 2019年3月8日
最近のイーサリアムはやはり期待高めといったところでしょう。
ETHとLTC最近強い。ETHには期待している。
あまりチャート詳しくないけど、日足のチャートはきれいって思う。— ヴァレンシア (@valencia3104) 2019年3月5日
ETH NEM ADA EOSは期待してます(^^)
— ヨッシー (@takamina1008) 2019年3月2日
#uniswap への流動性提供について
例えば
と期待するなら、
「日次取引量がプールサイズに対して5%以上」
という水準が維持されなければ、
単純に ETH と DAIを1年間ホールドしていたほうが 得 ということです。https://t.co/AjPynruXx4#DeFi
— kyoronut きょろナッツ (@kyoronut) 2019年3月2日
イーサリアムのハードフォークが無事完了して良かったです。
価格にはあまり影響がありませんが、今後に期待です!#ETH #仮想通貨— CoinsDon’tCry (@CoinsDontCry) 2019年3月1日
イーサリアムに期待する声がある一方で、アップデートに対する懸念点もあるようですね。
フィデリティの今後の動向には注目ですね✨
イーサリアムはこれからのアップグレードが懸念点になっているのか。。。何とか解決策を見出だして取り扱ってほしいな#イーサリアム#ETH https://t.co/Owgo4bkcYv— Arrietty🔮 (@Arrietty_gbl) 2019年3月8日
イーサリアム(ETH)が購入できる日本の取引所一覧

日本国内にある仮想通貨取引所では、イーサリアムはほぼ購入することができます、
現在イーサリアムが購入できる日本の取引所は以下の通りです。
販売所があるところでは、販売所での売買手数料は無料となっています。
取引所も無料やメイカー、テイカー別に手数料を設定しているところもあります。
| 取引所 | 通貨ペア | 取引所 | 販売所 | 可能レバレッジ |
| ビットフライヤー | BTC,JPY | 0.2% | 0% | - |
| GMOコイン | JPY | - | 0% | 5倍 |
| Zaif | BTC,JPY | M:0% T:0.1% | - | - |
| ビットバンク | BTC | 0% | - | - |
| DMMビットコイン | BTC,JPY | - | 0% | 5倍 |
| Liquid by QUOINE | JPY,USD,EUR,AUD,SGD,HKD, IDR,PHP,BTC |
0.025% 現物は0% |
- | 最大25倍 |
| BITPOINT | JPY | 0% | - | - |
| コインチェック | BTC,JPY | - | 0% | - |
| 楽天ウォレット | JPY,BTC,USD,EUR | 0.25% | - | 最大25倍 |
| Bit Trade | BTC | M:0.2% T:0.25% | - | - |
| BTCBOX | JPY | 0.1% | - | - |
※M:メイカー、T:テイカー
国内取引所でイーサリアムを購入するとなると、どこで購入した方が良いのか迷うところですが、おすすめは手数料も安くて、レバレッジも25倍まで設定できるLiquid by QUOINE(リキッドバイコイン)がおすすめですね。
もちろん、使いやすい取引所を利用するのが一番ですから、自分にあった取引所を選んでくださいね。
イーサリアムの買い方については下記をご覧ください。
イーサリアム(ETH)の今後を各著名人が予想

ヴィタリック・ブテリン氏
イーサリアムの開発者であるヴィタリック・ブテリン氏は、2018年11月に行われた「カンファレンスDevcno4」にてイーサリアムのスケーラビリティキャパシティは1000倍にまで到達するだろうと回答しています。
「ETH(イーサリアム)の次期アップデートである「セレニティ/Serenity」でPoWからPoSに移行し、スケーラビリティ向上、省エネルギー化が期待できる。
イーサリアムのスケーラビリティキャパシティは1000倍にまで到達するだろう」
マイケル・ノボグラッツ氏
仮想通貨の投資銀行として有名なGalaxy Digital社のCEO、マイケル・ノボグラッツ氏は、イーサリアムの今後を次の様に予想しています。
「アップデートが順調に進めば、イーサリアムは$1,500(約16万円)を超えるだろう」
数々の仮想通貨に精通するマイケル・ノボグラッツ氏だからこそ、イーサリアムの今後に何か展望を見いだしているのかもしれませんね。
イギリスの大手比較サイト:Finder.com
毎月仮想通貨の将来予想を発表しているFinder.comでは、イーサリアムの価格はやはり将来的に大きく上がるとしています。
2019年2月に発表されたイーサリアムの予想価格では、3月1日時点では115.40ドル(約12,800円)とし、おおよそ的中。
2019年12月31日時点では285.09ドル(約31,000円)までイーサリアムの価格が高騰するという予想を立てています。
イーサリアムは仮想通貨界には無くてはならない存在の為、今後はどうなるでしょうか。
イーサリアム(ETH)の今後の将来性について

イーサリアムの将来性は非常に大きいものとされています。
米国テキサス州に本社がある格付け会社「Weiss Ratings」によれば、5年後の2023年には、ビットコインを抜いて、「仮想通貨の王」になると予想建てを行っています。
スマートコントラクトが十分に機能した上では、国際間でのビジネスの契約において飛躍的な発展が期待できることでしょう。
また、独自に展開するプラットフォーム、スマートコントラクト、DAPPSにはやはり将来的に期待できるもの。
まだ、イーサリアムのアップデートは完全に完成している訳ではない為、今後にまさに期待といったところでしょう。












































