
仮想通貨は形がない電子データではあるものの、財産としての価値がある存在です。
そのため常に奪われるリスクをはらんでいます。
さらに数年前から仮想通貨取引所の仮想通貨の流出事件は度々ニュースに取り上げられるなど、銀行強盗のニュースを見なくなった昨今、新たな財産を脅かす問題として社会から見られています。
そんな不安に対応するため、仮想通貨では様々なセキュリティ対策が施されています。
それは度々起こる流出問題などに対応してどんどん強固なものへと進化して言っているのです。
今回、この仮想通貨のセキュリティ対策と言うテーマで実際に起こりうるセキュリティ上のリスクや仮想通貨取引所が実施している以下5つのセキュリティ対策について説明します。
- 二段階認証
- マルチシグ
- コールドウォレット
- ホットウォレット
- SSL
また、特にセキュリティ対策に力を入れている国内の仮想通貨取引所や、自衛手段の方法についても紹介していきます。
この記事の目次
仮想通貨をセキュリティ対策されていないところに預けた場合のリスク

仮想通貨はセキュリティ対策が必須です。
しかし、万が一仮想通貨取引所のセキュリティ対策が不十分であったらどんなことが起こるでしょうか?
以下の3つのリスクが挙げられます。
- ハッキングによるリスク
- 対象となる仮想通貨のブロックチェーンネットワークにおいて 51% 以上の採掘速度を有した場合(51%Attack)のリスク
- 51%Attackによる信用低下による取引所自体の破綻リスク
ハッキングによるリスク
まずハッキングによるリスクですが、これが基本的にニュースになるリスクです。
2018年には、国内の仮想通貨取引所で2つの大きなハッキングによる事件が発生しました。
コインチェックとザイフの事件です。
この二つについてお話しすると、
2018年1月、Coincheck(コインチェック)では約580億円もの顧客資産を流出するという事件が発生しました。
2018年10月には、大手の国内仮想通貨取引所として人気だったザイフもハッキング被害を受けたことにより入出金を一時的に停止しました。
コインチェックの流出事件では、実際に預けていた方の財産を失うという結果になってしまいましたし、ザイフに関しては仮想通貨取引の機会を逸するという結果になってしまいました。
このようにセキュリティ対策が疎かにされることによって、財産損失や機会損失のリスクがあるのです。
51%Attackのリスク
2つ目のリスクは、投資している仮想通貨のブロックチェーンネットワークにおいて 51% 以上の採掘速度を有した場合です。
このリスクは、「51%Attack(アタック)」「51%攻撃」などと呼ばれています。
直接取引所とは関係ないように見えますが、仮想通貨自体を運営している取引所もあるため51%Attackが行われてしまうと大きなリスクが生じます。
51%Attackにより行うことが可能となるリスクは以下の通りです。
- 不正な取引の正当化
- 正当な取引の拒否
- 採掘の独占
つまり、自分が預けていた仮想通貨が自由に操作され財産を失うリスクが生じるということなのです。
きちんとした仮想通貨取引所であれば対応できますが、セキュリティ対策が不十分であると簡単に財産が失われます。
仮想通貨取引所の破綻リスク
最後のリスクは、ハッキングや51%Attackによる資金の引き上げによって仮想通貨取引所自体が破綻してしまうリスクです。
ハッキングや51%Attackが起こると現在の法律では保護することができないため、突然取引停止となり財産を失いかねないというリスクがあるのです。
このように、ハッキングや仮想通貨の支配、そして信用低下による破たんなど、セキュリティ対策がなされていないまたは不十分であることによって、様々なリスクが発生します。
仮想通貨取引所が行っているセキュリティ対策

仮想通貨取引所では、利用者の財産や投資機会の損失を防ぐため多くのセキュリティ対策を施しています。
代表的なものとして、以下の5つがあります。
- 二段階認証
- マルチシグ
- コールドウォレット
- ホットウォレット
- SSL
これらは有効なセキュリティ対策として認知されています。
二段階認証とは
二段階認証とは簡単に言うと2つパスワードを加えた認証方法です。
1つのIDに対し二つの認証を与えることによって、セキュリティをより強固なものとします。
これは銀行のオンラインでも利用されている認証方法で、ログインに必要なIDやパスワードの他にもう一つワンタイムパスワードを設定するという仕組みになっています。
決まったパスワードの他に変動するパスワードが入ることによって、不正ログインのリスクを大幅に減少させることができるのです。
近年では国内のほぼ全ての仮想通貨取引所で実施されている認証方式になります。
以前は器具を使ったワンタイムパスワードが主流でしたが、近年は以下のようなアプリを利用したワンタイムパスワードを含む二段階認証が主流となっています。
- Google Authenticator(グーグルオーセンティケーター)
- IIJ Smart Key(アイアイジェイスマートキー)
- Authy (オウシー)
アプリで利用取引所のQRコードを読み込むことによって二段階認証が有効化されます。
マルチシグとは
マルチシグとは「マルチシグネチャー(複数の署名と言う意味)」の略称です。
文字通り、送金などの処理情報(トランザクション)の内容(送金先の口座番号や金額など)をデジタル署名により暗号化し、トランザクションの内容が改ざんされていないかをサーバー側で確認できるというトランザクション署名に複数のカギを使った仕組みになります。
これは仮想通貨取引所の他にウォレットでも採用されています。
従来の一つのデジタル署名だったシングルシグよりもセキュリティを手厚くすることが可能となっているため、仮想通貨を第三者から奪われるというリスクを防ぐことができます。
また、人為的に秘密鍵を紛失してしまうという悲しいミスに対しても対応しやすいものです。
コールドウォレットとは
コールドウォレットは直接的なセキュリティ対策です。
コールドウォレットは、オフラインの端末によってネットワークから切り離された環境に秘密鍵を保管します。
インターネットに接続しないため完全にハッキングを回避することができ、セキュリティ面は確実に向上します。
そのため多くの仮想通貨取引所ではコールドウォレットを採用し、顧客資産をオフライン上で管理することによって顧客資産を保護しているのです。
ややアナログ的な方法ですが、下手なオンライン上のセキュリティ対策よりもかなり確実な方法と言えるのです。
ホットウォレットとは
コールドウォレットの対局にあるのがホットウォレットです。
これはコールドウォレットと異なり、常にインターネットに接続されているウォレットです。
ホットウォレットを利用するメリットは、資金を移動させやすいなどの利便性にあります。
オフライン上で保管コールドウォレットは資金を移動させるのに手間がかかるため、長期的な保管にはコールドウォレットを利用し、日常的な取引や送金にはホットウォレットを利用することで、利便性とセキュリティ面を兼ね備えた保管が可能となります。
ホットウォレット単独で仮想通貨を保管していると、ハッキングなどにより全仮想通貨を失う恐れがあります。
SSLとは
SSL(Secure Sockets Layer)とは、インターネットで安全にデータをやりとりするためのプロトコル(信号送信の手順)で、暗号化と認証の機能があるWeb状の通信を暗号化してくれるセキュリティ対策のことです。
SSLを利用することで、第三者から通信内容を見られないようにしています。
もしも仮想通貨取引所のログイン時にSSLを使用しなければ、ログイン情報などのデータが第三者に読み取られる可能性が高くなり、不正ログインなどの恐れもあります。
そのため、SSLは基本的なセキュリティ対策の1つと言えるのです。
国内取引所でセキュリティ対策に力を入れている仮想通貨取引所

国内取引所でセキュリティ対策に力を入れている仮想通貨取引所について3つ紹介していきます。
- bitbank(ビットバンク)
- GMOコイン
- bitFlyer(ビットフライヤー)
bitbank(ビットバンク)
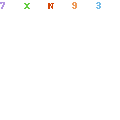
bitbank(ビットバンク)は、取り扱い通貨の全がコールドウォレットに対応しています。
また、わずかでもリスクがあると言われているホットウォレットを採用していないという点でセキュリティに十分な対策をとっている取引所と言えます。
マルチシグに関してはイーサリアム(ETH)には対応していないものの、5通貨に対応済みとなっています。
当然のことながら、SSLや二段階認証にも力を入れています。
GMOコイン
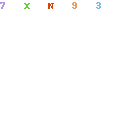
GMOコインは、運営母体がサーバーやセキュリティに関してのノウハウが高いネットのスペシャリストであるGMOインターネットグループが運営しているため、セキュリティ対策は万全です。
二段階認証、マルチシグ、コールドウォレット、SSLの全てに対応しています。
また、証券やFX取引の取引高が世界一と言う実績もあるため、他の資産管理のセキュリティ対策のノウハウを生かしていると言う点も頼もしい取引所と言えるでしょう。
bitFlyer(ビットフライヤー)
の購入_販売所_取引所【bitFlyer(ビットフライヤー)】-bitflyer.com_-1024x510.jpg)
bitFlyer(ビットフライヤー)は、二段階認証、マルチシグ、コールドウォレット、SSL全てのセキュリティ対策を採用しています。
特に、SSL評価はA+という世界有数の評価を獲得しています。
さらに不正被害にあった場合の保証も設けており、これらの点から、国内では最高水準のセキュリティ対策を行っていると言っても過言ではありません。
仮想通貨は自分で守ろう!自分でできるセキュリティ対策6選

仮想通貨取引所は非常に高いセキュリティが施されていますが個人は無防備であることが少なくありません。
そういった点に悪意ある人間は漬け込むのです。
最後に自分でできるセキュリティとして、
- 不正ログインが防げる二段階認証は確実に行う
- ハッキングされるリスクの回避のため無料Wi-Fiにはつながない
- 不正ログイン予防のためパスワードの使いまわしは行わない
- 万が一のリスクを回避するため取引所に預けっぱなしにはしない
- ハードウォレットやペーパーウォレットを利用する
- 仮想通貨詐欺に遭わないよう注意する
仮想通貨を保管するウォレットには様々な種類がありますが、コールドウォレットで代表的なUSBのような小型端末に保管できるハードウォレットや秘密鍵を紙に印刷して保管できるペーパーウォレットを利用して保管することで、ハッキングのリスクを回避することができます。
また、最後の詐欺についてですが、人は自分で思っている以上に簡単に騙されやすいものです。
うまい儲け話には安易に乗らないようにしましょう。
現在、オレオレ詐欺が横行していますが、仮想通貨に関連する詐欺も増え始めています。
これらのポイントについてしっかりと対策を行い、大切な仮想通貨を自分自身で守っていきましょう。
仮想通貨のセキュリティ対策のまとめ
仮想通貨取引所では過去の流出事件や取引停止など辛酸をなめてきました。
そのため非常に高度なセキュリティ対策を行い顧客の財産を保護しています。
しかし、個人の自衛が不十分だとそこから付け入られて財産や投資機会を奪われかねません。
システム的な面も大切ですが、詐欺のような儲け話に乗らないよう自分自身でも注意していきましょう。

















































