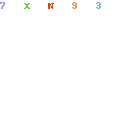
仮想通貨の情報を仕入れていると、TGE案件という特別な仮想通貨に出会いますよね。
例えば、ジャスミーやセントラリティ、Proxeus(プロキシウス)など。
そんなTGE案件が一覧で詳しく知ることが出来たら嬉しくありませんか?
また、ICOトークンは、将来的に価格が大きく上昇する可能性も高いですが、ICOの成功率は50%と言われている以上、価格が大きく下落しICO割れを起こす可能性もあります。
では一体TGE案件とICOとの違いは一体なんでしょう?
本記事では、TGE案件について徹底的解説しますから、最後まで記事を読むことでTGE案件のメリットに気がつくでしょう。
この記事の目次
TGE案件とは
TGE案件とは、Token Generating Eventを略して、TGE案件と日本では呼ばれています。
このTGE案件は、いわゆるスタートアップ企業が行うICO案件とさほど変わりはないです。
違いとしては第三者機関による、信用できる仮想通貨案件なのかの調査が行われているかということです。
例えば、個人投資家が仮想通貨プロジェクト自体の、信憑性を問うことが難しいとされてきました。
すがるところといえば、ホワイトペーパーや話題性だけで判断しなくてはなりません。
プロの投資家の意見を求める場合も、最初に行うことは、信頼できるICOレーティングサイトを探すことでしょう。
ただでさえ、海外中心で開催されるICO案件は実体さえ掴めず、非常に高いリスクを背負っていました。
ましてや、ICOプロジェクトのホワイトペーパーが英語表記では、どんなプロジェクトなのか把握することも難しいですね。
そして、プロジェクトの内容や集めた資金の流れが不透明ままで、上場さえ果たせなかったICO案件も数多くあります。
その一方で、仮想通貨プロジェクトの運営元が抱える問題も、指摘されていました。
何故ならICO開催にあたって、法的な問題やマーケティング戦略など、幅広い分野で解決できる人員も同時に求められるからです。
ですから、仮想通貨プロジェクトの運営元からすると適切な助言をしてもらえる窓口のような機関があれば、もっと開発に注力できるのです。
そういったICOにまつわる複雑な問題に取り組んでいるのが、CTIAというブロックチェーン関連のコンサルティングを行う組織です。
このCTIAが独自に調査を実施し、手掛けるICOがTGE案件と呼ばれています。
CTIAとTGEとの関係性
先述した通り、CTIAが調査したICO案件をTGE案件と言います。
CTIAは自社で構築した精査基準をもって、TGEプロジェクトを開催しています。
TGEに参加する一般ユーザーにも、KYC(※1)とAML(※2)の審査基準を設けているため、いわばCTIAが調査しているICO案件は総合的にプロジェクトに関わっています。
また、CTIAは仮想通貨やブロックチェーン関連のコンサルティング業務を行う新たな組織として、まだ確たる地位を確立していません。
そのため、単にICOの格付けを行う第三者機関とは異なり、TGEプロジェクトと密接な関わりがあります。
TGEプロジェクトを成功させなければ、CTIAの信頼性も同時に問われることとなるからです。
つまり、クライアントであるプロジェクト運営元と目指す目的は一緒であるということです。
CTIAの問題点
しかし、CTIAの活動は仮想通貨やブロックチェーンのプロモーションのような広告塔に過ぎないのでは?とされる問題点もあります。
クライアントから提出された信頼性を審査するという流れは、実際にはスイスの法律事務所とBlockhausで行われています。
TGE案件に参加するためのプラットホームとして、Blockhaus(ブロックハウス)というP2P取引所と提携しているからです。
つまり、TGE案件に参加できるかどうかの登竜門はBlockhausであり、情報としてまとめたものを、CTIAに提出している流れであるということです。
CTIA内でも厳重に審査されていれば、個々のプロジェクトの信憑性は高まります。
とはいえ、CTIA が手掛けたTGEプロジェクト自体の歴史も浅いため、なんとも判断しにくいものです。
CTIAは日本支社もありますが、本社はスイスにあり、代表取締役は日本人である手塚満氏です。

手塚満氏は世界にみて、日本のブロックチェーン技術が遅れていることを受け、普及活動にも力を入れているようです。
ですから、CTIAを立ち上げ、信頼できるTGE案件を人々に届けようとしています。
TGEとICOの違い
TGEとICOの違いは、CTIAはBCPフレームワークという精査基準を採用しているため、様々な側面から評価ができる点がICOと違います。

CTIAはBCPフレームを使用し、結果をプロジェクトに参加を希望するユーザー向けに分かりやすく、提供していこうという指針があります。
TGE案件の情報開示は、不安を感じながらもICOに参加していた人々にとって大きなメリットといえます。
TGEプロジェクトに参加する前に、リスクスコア情報を得ることができるからです。
さらに単一のプラットホームで、トークンセールに参加できるというTGE案件ならではの利点もあります。
全て、トークンセールプラットホームBlockhausアプリを通じて行われるからです。
ユーザー登録は、先述したKYCとAML審査をクリアしないとセールに参加できません。
しかし、今までのプロジェクトごとに、ホワイトリスト登録を期限内に行うという煩わしさはありません。
TGEとICOの大きな違いは、「信頼性」といいたいところですが、TGE案件全てがそうとはいいきれません。
今までになかったICO開催スタイルとして、運用が始まったばかりです。
TGE案件だからといって、価格の上昇が見込めるのは一時的なものでしょう。
ですから、長期的にみてどうなのかという考察はこれまで通り必要です。
仮想通貨TGE案件一覧
では、実際にTGE案件に関与している仮想通貨をそれぞれ見ていきましょう。
現在、CTIAの公式サイトに公開されている代表的なTGE案件は以下の5種類です。
- Singular Japan(シンギュラーブイジャパン)
- ARDA(アルダ)
- Proxeus(プロキシウス)
- PLAG(プラグ)
- Centrality(セントラリティ)
では、それぞれどんなTGE案件なのかを見ていきましょう。
TGE案件1:Singular Japan(シンギュラーブイジャパン)の特徴

公式サイト:Singular Japan
Singular Japanは、2016年始動のエンタメ系のブロックチェーンプロジェクトSingularDTVの日本向けサービスです。
つまり、SingularDTVが2019年に配信予定の、日本専用のチャンネルを通じて、提供されるコンテンツの総称を指すようです。
Singular Japanでは、配信用プラットホームをCentralityの開発キットで構築しているという特徴があります。
そして、Singular Japanトークンのアルゴリズムを、SNGJエコシステムと呼びます。
コンテンツを利用する為にSNGJトークンが消費される仕組みで、独自プラットホーム内で流動性をもたらします。
しかし何故、日本向けの新たなプラットホームをTGE案件として扱う必要があるのか?と疑問が残ります。
SingularDTVを中核とした、国ごとの配信用チャンネルを構築する目的もはっきりしていません。
よく揉め事となるクリエイター自身の作品を勝手に修正し、引用することで、裁判沙汰になるケースがあります。
どの国も著作権法はクリエイターを守るために法律がありますが、国によって、厳格に従うかはそれぞれです。
しかし、クリエイターはSingularDTVのTokit(※3)を利用して、トークンを作成するので著作権が守られるはずです。
ですが、2018年10月7日に2019年発売予定としている日本向けの配信専用コンテンツを取得していることから、着実に事業が進行しているのが伺えますね。
ニューヨークに本拠を置くBlockchainのSingularDTVは、地元の独立系プロデューサー、販売代理店のShiomakiを率いるために、日本で拠点を立ち上げている。
この新しいベンチャーは、決して生産されないかもしれないオリジナルの物語に焦点を合わせて、中低予算の日本の映画を育成し、そのコンテンツとその後ろの映画製作者を国際的なステージに導くことを目指しています。
TGE案件2:ARDA(アルダ)の特徴

公式サイト:ARDA
ARDA(アルダ)はモバイルを通じて、ダイエット・筋力トレーニングなど目的別でデータを収集し、AIを用いて適切な指導を行うことを目的としたプロジェクトです。
このビジネスモデルの元となっているのは、世界初の商業スポーツ研究所を設立したPerformance Labです。
今までスポーツ業界では、一流選手やプロのスポーツチームを専門家が個別にコンサルタントしてきました。
そして、ついにスポーツ業界でも、データ解析にAIを導入しようという動きがみられているようです。
そのため、独自のトレーニング・ヘルスケアアプリケーションを研究してきたPerformance Labが、ARDAの開発キットを採用して新サービスを立ち上げました。
既存のアプリとARDA(アルダ)との違いは、自分のトレーニング結果の情報を企業に提供することで、トークンが貰える仕組みになっていることです。
そして、個々のトレーニング情報を得た企業は、ユーザーの目的を達成させる為の商品を提案できます。
企業がユーザーに商品を提案することで、ユーザーは情報料として貰ったトークンで、好きな商品を購入し、特定企業と繋がりを作ることができます。
さらに、ARDA(アルダ)のプロジェクトを通すことで、スポーツ業界人だけでなく、一般ユーザーも専門家による指導を受けることが可能になり、今までになかった市場の開拓が期待されています。
ARDA(アルダ)プロジェクトの詳細は下記の動画をご覧下さい。(時間:3分23秒、日本語字幕なし)
TGE案件3:Proxeus(プロキシウス)の特徴

公式サイト:Proxeus
Proxeus(プロキシウス)は、既存の企業にブロックチェーンベースの新しいビジネスモデルを普及させようとするプロジェクトです。
2015年に始まったProxeusは、独自のシステムで法人登記を1時間37分で完了させたという実績があります。
スイスで実証実験が行われ、「フィンテック・アワード2018」を受賞し、ブロックチェーン技術の実用化が認められた期待のTGE案件です。
A more in-depth look at Proxeus' win at the FinTech Awards. #crypto #blockchain #XES #startup https://t.co/QIoi9yLHjG pic.twitter.com/HYkL2nPt9S
— PROXEUS (@proxeusapp) March 26, 2018
そして、Proxeusの開発ツールを利用することで、改ざん不可能な契約書や公的文書の作成、あるいは資産のトークン化できる特徴を持ちます。
Proxeusには、ProxeusCoreという基盤があって、その上にスマートコントラクトを導入したモジュールが作成される仕組みですね。
Proxeusが評価されている理由として、どの企業でもブロックチェーン技術導入モデルが、自社でも取り入れられるのかと、日々模索しています。
そして、比較的容易に導入できて、セキュリティも万全なものを企業は探しています。
そういった企業が求めるニーズを掴んだのが、Proxeusのプロジェクトです。
しかし、日本の企業でも検討の余地があるProxeusのシステムは、まだ周知されていません。
CTIAの盛大なプロモーションがなくとも、欧州を中心に広がり始め、数年後には全世界に自然と広がっていくでしょう。
Proxeusの仕組みについて、詳しくは下記の動画をご覧下さい。(時間:1分57秒、日本語字幕あり)
TGE案件4:PLAG(プラグ)の特徴

公式サイト:PLAG
PLAG(プラグ)は、企業のみならず個人でもブロックチェーンを基盤ツールに実装せずに、dappsにアクセスできるライブラリ(※4)です。
ライブラリとは、汎用性の高い複数のプログラムを再利用可能な形で一塊にしたものです。
要するに、プログラムが集まったものとして考えて良いでしょう。
つまりPLAGの開発目的は、dappsにアクセスできるライブラリを一から開発しなくても、既存のシステムのまま、ブロックチェーンベースのdappsにアクセスできるようなフレームワークを構築するのが狙いです。
そのため、開発言語は近年人気が上昇したpython言語を使用しています。
比較的、ブロックチェーン技術でシステム全体を変えようという企業より、今あるサービスを拡張したいという企業にはもってこいのツールのようですね。
PLAGの特徴として、ステーキング(※5)で報酬がもらえる設計があります。
しかし、PLAGの購入が殺到するかと思いきや、知名度の低さで上場もいつになるのか未だはっきりしていません。
TGE案件として、JasmyとCentralityの提携が話題になりましたが、異なるブロックチェーンを繋げる役目を果たすのが、このPLAGの技術です。
Iotが普及し始めると、PLAGのプラットホーム内のトークンも活発な動きをみせるかもしれませんね。
TGE案件5:Centrality(セントラリティ)の特徴

Centrality(セントラリティ)はTGE案件で、大きく話題を呼んだプロジェクトですね。
これまで発表されたTGE案件の多くを、先導してきました。
Centralityのプラットホーム内で作成したアカウントで、連携するdappsにアクセスできる利便性が特徴です。
利便性が高い理由はモジュールという柔軟性の高い、開発ツールを兼ね備えているからです。
例えば、ウォレットなどのアプリ同士の互換性については、以前からユーザーから不満の声がありました。
現在では、ひとつのウォレットでいくつかのトークンを保管したり、送金できるようにと改善に向かってきています。
しかし、互換性についての問題が全て解決したわけではありません。
Centralityプロジェクトによって、ようやく互換性の問題解決の具体的な道すじができたといえるでしょう。
TGE案件のまとめ
TGE案件について解説しましたが、ご理解頂けましたか?
TGE案件の多くが仮想通貨の中でも専門性の高い言葉が多く使用されている為、理解するには時間がかかるでしょう。
しかし、CTIAが公表するTGE案件はICOに比べたらとても少ないです。
ですから、1つずつ時間をかけて調べることで、今後期待できる仮想通貨を発見することが出来るかもしれません。
そして、TGE案件は常にCTIAの公式サイトで確認することができます。
仮想通貨投資を失敗しない為にも、一度CTIAの公式サイトを見てみると良いかもしれませんね。
























-150x150.jpg)















