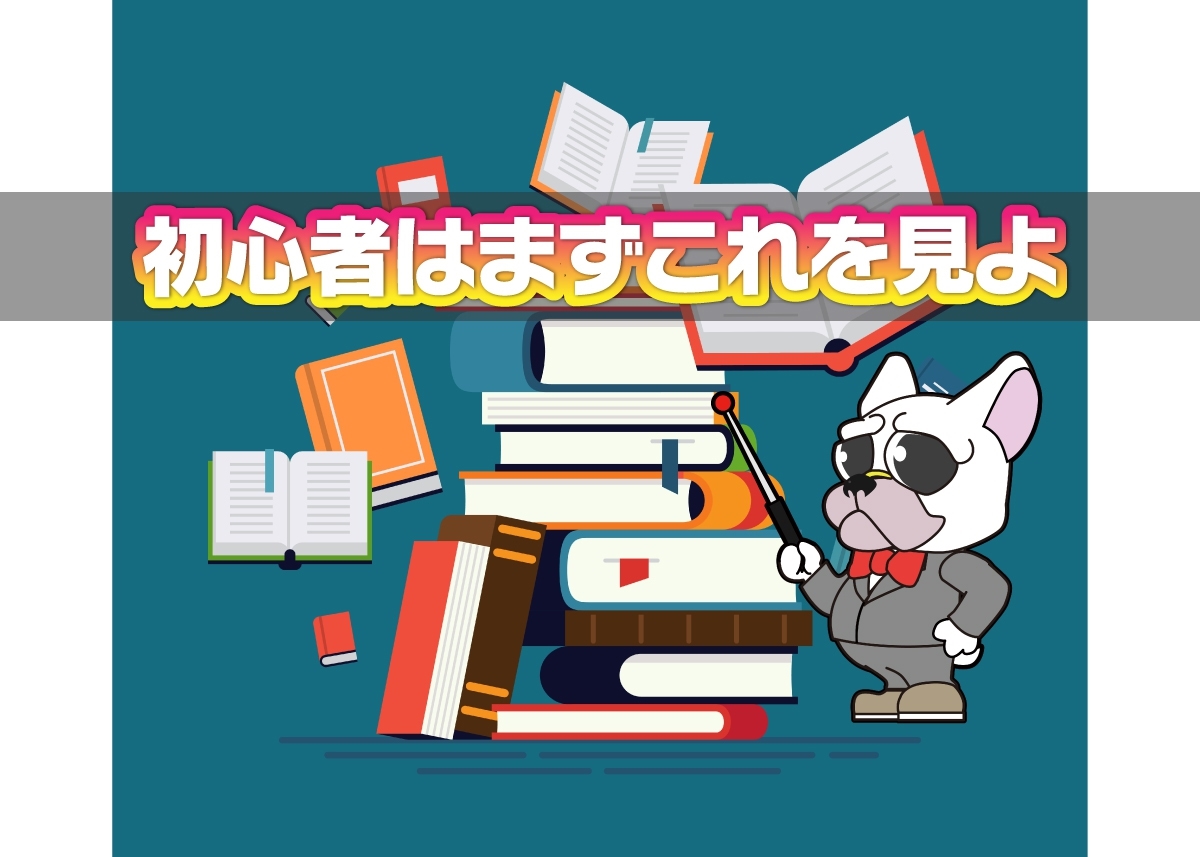
「仮想通貨」って最近よく見聞きする言葉ですが、いったい具体的にはどんなものなんでしょうか?
この記事では、今さら人には聞きにくい仮想通貨についてご説明します。
「ちょっと興味があるけどよくわからない」という方、必見です!
この記事の目次
仮想通貨を初心者にわかりやすく解説!

仮想通貨とはそもそも何?
仮想通貨とは、小銭(100円玉や50円玉など)やお札のような形を持っていない通貨のことです。
デジタル上のデータとしてのみ存在しており、国家が発行しているものではないという点もポイントです。
例えば、アメリカのドル、日本なら円ですが、それぞれ国の銀行が価値を保証したうえで貨幣を発行します。
しかし、仮想通貨は国や特定の機関が発行にかかわっているわけではありません。
インターネットを通じて、誰でもどこにいても利用できる新しい形の通貨であり、別名「暗号通貨」(クリプトカレンシー)とも呼ばれています。
ブロックチェーンや電子技術を駆使してインターネット上に存在しており、なんと日本政府にもきちんと認められている通貨なのです。
仮想通貨はなぜ期待されている?
ではなぜ仮想通貨に対する期待が高まっているのでしょう?
いくつかその理由をあげてみましょう。
手数料が安い
現金ベースの金融業者であれば、預金者が引き出す場合に備えて、多額の現金を前もって準備しておかねばならず、ATMや金庫・各支店などの設備も要します。
しかし仮想通貨ではそういった準備が不要なので、手数料を安くできます。
海外に送金する際、一般の銀行は数千円も手数料がかかるのに対し、仮想通貨ならばわずか数百円の手数料で済むのです。
スピード送金が可能
相手が個人・企業にかかわらず、送金先の情報を聞き、取引所やウォレットで情報を入力するだけで、いつでもすぐに送金が可能です。
銀行の場合、振り込みの時間帯によっては翌日の入金になるケースもありますが、仮想通貨なら通貨によって多少異なりますが、ビットコインの場合で言うと数十分で送金が完了します。
海外どこでも使える
仮想通貨を使用して決済できる店舗は、世界中でどんどん増え続けています。
例を挙げると、ビットコインで支払いできるお店なら、海外のお店でも日本とまったく同様に利用することができるということです。
この動きは今後もっと増えていくことでしょう。
非中央集権とは一体何?
仮想通貨の世界でよく見聞きする「非中央集権」とは、どういう意味なのでしょう。
まず「中央集権」という言葉は、もともとは政治の世界で多用されており、権力が中央に集まっていることを指します。
日本では「日銀(日本銀行)」が、法定通貨の供給量や紙幣の発行をすべて管理しています。
日銀というひとつの場所において権力が集中している、これが「中央集権」です。
対して「非中央集権」とは、言葉通り"権利が分散している"状態です。
仮想通貨が「非中央集権的」と表現されるのは、絶対的な管理者がいないからです。
ブロックチェーンとは一体何?
これもよく見聞きする言葉「ブロックチェーン」ですが、仮想通貨には欠かせないものです。
仮想通貨を使用する際の取引データ(履歴)のことを「トランザクション」と言い、それがまとまると「ブロック」と呼ばれます。
ブロックが連続して保存されるのが「ブロックチェーン」なのです。
ブロックチェーンは、システムを分散して管理するような仕組みになっており、金融機関を通さず、ユーザー同士でシステムを見張りあうように設定されています。
そのためにシステムエラーなど不慮のアクシデントにも強く、低コストで運用できるのです。
銀行のように特定された管理機関もない(=非中央集権)ので、サーバへの負担もかかりにくくなります。
仮想通貨の種類

ここからは、仮想通貨の種類について見ていきましょう。
仮想通貨1.0とは
初期のころできた仮想通貨のことを指します。
「通貨機能」だけを保持しており、ビットコインやモナコインなどがこれに属します。
仮想通貨2.0とは
通貨機能のみならず、仮想通貨1.0にはない付加価値があるものです。
例えばリップルの場合は、通貨機能にプラスして国際送金できるというメリットがあります。
アルトコインとは
ビットコイン以外の仮想通貨を「アルトコイン」と呼びます。
イーサリアムやリップルなど、全部で数千種類もあるとされています。
草コインとは
アルトコインの中でも時価総額が低く、まだユーザーも少ない流動性の低い仮想通貨のことです。
リスクも大きいコインですが、もし上手に見極めて安い時に大量に購入してその後価値が上がれば、大きく儲けることのできる仮想通貨です。
初心者向けの仮想通貨の勉強方法

インターネットで調べよう!
仮想通貨について勉強する際、一番手軽にできる方法がインターネットでの検索です。
「仮想通貨」「初心者」などで検索し、情報収集します。
インターネット上には、仮想通貨に関する情報も溢れていますから、自分の知りたい情報にも簡単にたどり着けるでしょう。
気になった仮想通貨やそれに関連するキーパーソンがいれば、ツイッターのアカウントをフォローするのもいい方法です。
しかし、すべての情報が正しいとは限りません。
どの情報が正しいのか、自分なりに見分けることも必要です。
ひとつのブログやサイトで書いてあっることが、ほかのサイトでも書かれているのか、情報に違いはないか、といった裏付けも行うようにすると万全です。
しかし、インターネットでは情報が多すぎて戸惑うという人もいるかもしれません。
セミナーに参加しよう!
最近は、全国各地で仮想通貨のセミナーも開催されています。
セミナーの情報はSNSで拡散されていますので、随時チェックしましょう。
オフラインで聞ける貴重な話もあるはずです。
しかし現在開催されているセミナーの多くが、参加者に何かを売りつける目的があるとも聞きますので、参加する際には十分気をつけてください。
主催者の情報や過去の口コミなどを事前に確認して怪しいようなら、参加は控えましょう。
書籍を読もう!
じっくりと読んで勉強するのには書籍が最適です。
本屋によっては「仮想通貨コーナー」が設置されていることもあり、注目の高さがうかがえます。
注意するべき点は、書籍は発行されてどのくらい経過しているか?という点です。
目まぐるしく移り変わる仮想通貨の世界では、書籍に描かれている情報が既に古いという場合もあります。
書かれている内容が現在当てはまるかどうかはわからない、ということは覚えておきましょう。
実際に通貨を買ってみよう!
「習うより慣れろ」という言葉もあるように、何事も実践が大事です。
やりながら学んでいく姿勢も必要でしょう。
ただし最初から大きな額で投資するのはリスキーですから、あくまでも少額で開始しましょう。
慣れてきたなと自分でも思ったら、ほかの仮想通貨も購入してみたり、金額を増やしたりと新たにチャレンジをしてみてください。
仮想通貨投資をするメリット

ここからは、仮想通貨投資のメリットについて詳しく見ていきましょう。
365日いつでも投資ができる
株式の場合は、証券取引所を利用しますが、証券取引所には終了時刻や休みがあります。
平日昼間にしか基本的には投資はできません。
一方、仮想通貨市場はインターネットの世界ですから、24時間一年中投資ができます。
平日は会社に行っていても夜だけ、土日だけなど自分の好きな時間に取引が可能です。
少額からでも投資ができる
いろいろな仮想通貨が存在していますが、多くのものは「最低取引価格」が低く、わずか数百円から投資ができます。
株式と比べると懐も痛まずにスタートできるのは魅力ですね。
将来性に期待できる
知名度は徐々に上がってきているとはいえ、日本では仮想通貨はまだ一般的ではありません。
しかし2016年に仮想通貨関連で法律も整えられ、2017年には資金決済法が改正されて、仮想通貨に関する条項も追加されました。
今後、仮想通貨はもっと知名度が上がり、決済手段としてメジャーになることが十分期待できます。
大勢の人が仮想通貨を電子マネーのように利用する時代が、近々到来するでしょう。
ですので今のうちに仮想通貨に投資し、その価値やどんなものなのかをよく把握しておくべきなのです。
ボラティリティが利益を生みやすい
仮想通貨は、ボラティリティが大きく、利益が生まれやすいと言われています。
ボラティリティとは価格の変動率を示す言葉で、価格が激しく上下するのなら「ボラティリティが大きい」、その逆なら「ボラティリティが小さい」という言い方をします。
ボラティリティが大きければリスクも伴いますが、それだけ価値が上がる可能性もあるわけで、大きな利益を生む結果にもなりえますね。
仮想通貨投資をするデメリット

ここからは、仮想通貨のデメリットについて触れていきます。
流動性がまだ低い
「流動性」とは、どのくらい仮想通貨が取引されているかということであり、流動性が高いほど通貨として価値が高いことになります。
仮想通貨は、株式と比べると日本での知名度がまだ低いので、決して流動性が高いとは言えません。
世界で最高の流動性を誇る通貨と言えばやはり「ドル」であり、いろいろな資産(通貨)とも交換可能ですが、それを考えると仮想通貨の中で流動性が一番高い「ビットコイン」でもまったく歯が立ちません。
流動性が低い仮想通貨であればあるほど「価値が不安定」なので、この点はデメリットです。
大きく損失を被る可能性がある
前述した通り、流動性が低いと価値が安定しません。
つまり価格の上がり下がりも激しい分、リスクも大きいと言えます。
ユーザーの多くが「もっと値上がりする」と考えれば「買い」の量が増えて価格が上昇し、「やばいな」と思えば売る人が一気に増加し、価格が下がります。
もちろん株式でもそういったことはありますが、仮想通貨の方が、ユーザーの心理状態による価値の上下はより大きいかもしれません。
税金が高い
あまり知られていないかもしれませんが、仮想通貨にかかる税金は意外と高いのです。
インターネットでは「仮想通貨の税率は最大で55%なんて高すぎる」との怒りの声も上がっています。
現在、仮想通貨で得た利益は「雑所得」(ほかのどこにも当てはまらない所得)としてみなされます。
またほかの所得と合算し、総額に応じて「所得税」がかかる総合課税の対象にもなっています。
所得税なら最大税率は45%ですが、雑所得の場合ですとその最大税率45%に加えて、住民税10%もかかるので合計で55%となってしまいます。
雑所得でも株式・FXでの利益なら、申告分離課税となり、所得の額に関係なく税率は一律で約20.31%となるので、いぶかしく思う人が多いのも当然のことでしょう。
仮想通貨投資におけるリスクについて

前章では、仮想通貨のデメリットについて触れてきましたが、リスクについても知っておきましょう。
追証(おいしょう)に気を付けよう!
追証とは「追加証拠金」の略です。
「追証(おいしょう)」とは「追加保証金」の略称で、委託保証金を追加で差し入れなければならない状態のことです。買い建てまたは売り建てた銘柄の含み損、担保にしている株の値下がり等によって委託保証金率が下がることにより発生します。
引用:SMBC日興証券株式会社
仮想通貨のFXで、証拠金を預ければその数倍~数十倍のお金を動かすことのできる取引のことを「レバレッジ取引」と言います。
しかし損失が大きくなってその証拠金より損害が多くなった場合、「追加で証拠金を入れる」=追証を取引所に入れるように時間に猶予が与えられます。
その時間までに入金されなければ、それ以上損をしないようにロスカット(強制決済)が行われる場合もあります。
追証を迫られるか、ロスカットされるかについての措置は各取引所により異なりますので、仮想通貨で投資する場合は自分の利用する取引所の制度について前もって知っておくようにしましょう。
通貨の将来性を見極めて投資をしよう!
仮想通貨はその将来性をしっかりと見極めて投資するようにしましょう。
将来性が高いと期待が持たれる仮想通貨は多くの人が購入し、価値が上がります。
今は価値が低くても、この先知名度が上がり価値が上がるだろうと推測できる仮想通貨を買っておけば、その分利益も期待できますよね。
しかしその逆で、価値が低いまま価格も上がらずゴミ同然と化してしまう場合もあるのです。
将来性が高い仮想通貨を見極めるためには、しっかりと情報収集を行い、機能性がどれだけ備わっているか、多くの企業から注視されているか、そのコミュニティが強いか、といった様々な点を細かくチェックし将来性を分析する必要があるでしょう。
仮想通貨業界の専門家達の将来予想も参考に!
2019年になってから仮想通貨の価格は下火になっていますが、世界中の仮想通貨の専門家及び経営者の人達が独自の予想を出しています。
下記ではそれぞれジャンル別に2019年以降の予想をまとめていますので、仮想通貨の勉強に+で参考にして下さいね。









































