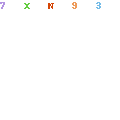
近年、仮想通貨をめぐる市場が盛り上がりを見せています。
仮想通貨が価値あるものと考えられているは、単に儲かるからだけでなく、仮想通貨に取り入れられている「ブロックチェーン」というシステムが注目されているからです。
そのブロックチェーンの応用が進んでいる領域の一つとして、トレーサビリティが挙げられます。
この記事の目次
なぜ今ブロックチェーンに注目が集まっている?
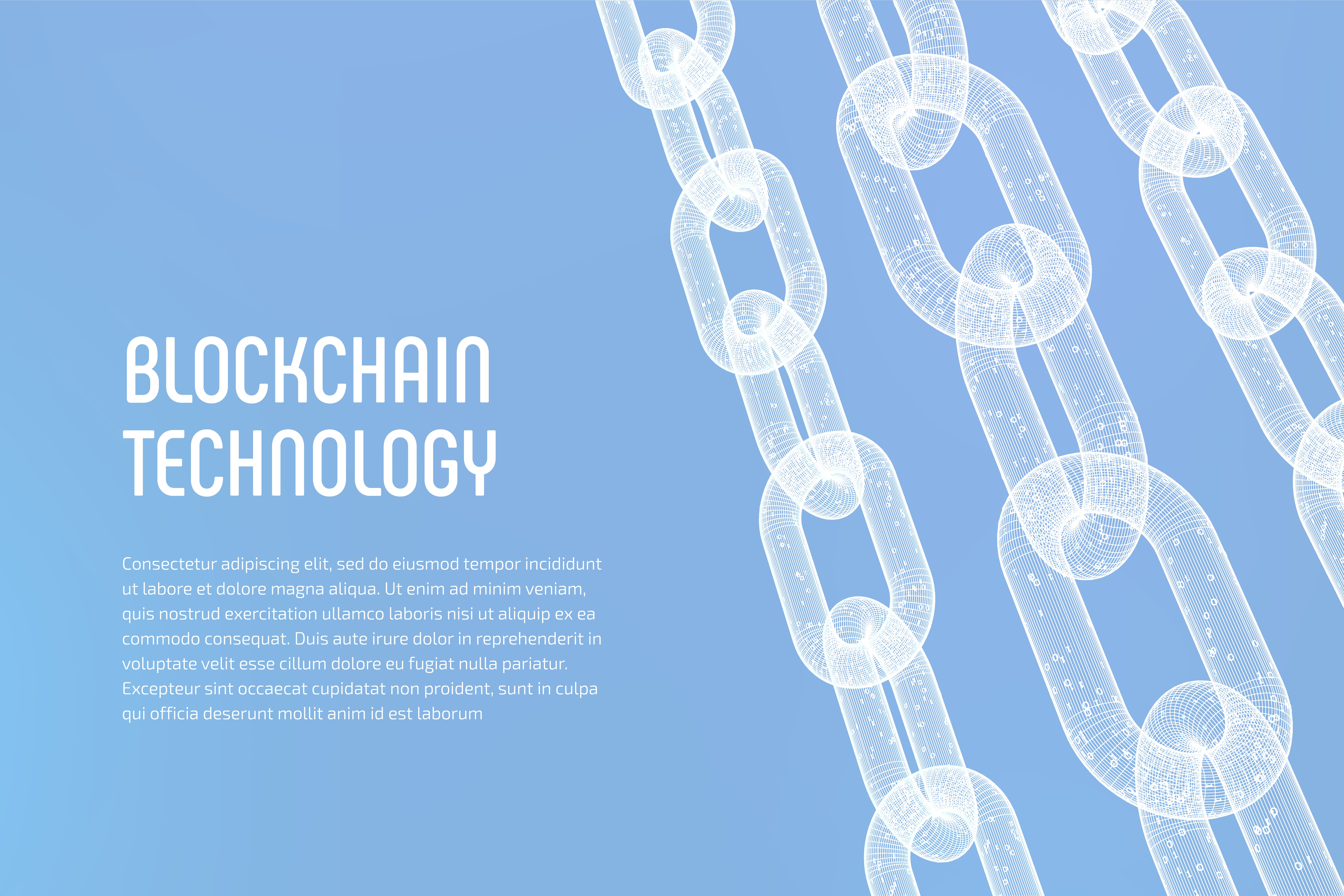
ブロックチェーンは「分散型台帳技術」と言われ、ビットコインが生み出されて今に至るまでの全取引の記録をしています。
ビットコインの取引は、ノードと呼ばれるネットワークの参加者全員が、約10分ごとに世界中で行われた取引情報を記録し、二重支払いのような不正がないか管理しています。
このような技術が、様々な産業の分野で活用できるのではないかと注目が集まっています。
そもそもブロックチェーンとは

ブロックチェーンとは、ごく簡単に言えば「記録を残す仕組み」です。
ビットコインの根幹をなすものとして、P2Pネットワーク上で動くシステムです。
P2Pネットワークとは、インターネットにおいて一般的なサーバーを中心にネットワークを形成するのではなく、サーバーをもたない自律分散型のネットワークです。
一つ一つの記録をブロックとよび、そのブロックが連続的に繋がり、鎖状にネットワークを形成することをブロックチェーンと言います。
ブロックチェーン業界の市場推移

仮想通貨や金融領域にとどまらずブロックチェーンの活用が進んでいます。
矢野経済研究所の発表によれば、2019年の市場規模は倍増しており、今後も年率100%以上の成長が見込まれるとしています。
矢野経済研究所は5月22日、国内ブロックチェーン活用サービスの市場規模が2019年は昨年対比112%増の171億円に達する見込みだという調査結果を発表した。3年後の22年には1235億円に達すると予測しており、17年から22年の年平均成長率は108.8%とみている。
ブロックチェーンは、当初仮想通貨の基盤技術として金融機関から注目されてきたが、17年後半からは、幅広い業界でサプライチェーンや権利証明などについての実証実験が積極的に行われている。
引用:ITMedia
ブロックチェーン技術を使用したビジネスの事例

ウォルマート
ブロックチェーン技術の小売業への利用を目指すのは、世界最大のスーパーマーケットチェーン「ウォルマート」です。
2018年3月、ウォルマートが「スマート・パッケージ」と呼ばれるブロックチェーンを利用した配送システムの特許を出願しています。
ウォルマートは特許出願書の中で、オンラインショッピングにおいて小売業者が抱える「セキュリティ」の問題について述べています。
ウォルマートがブロックチェーンを利用した購入商品転売用マーケットプレイスに関する特許を申請した。
米国特許商標庁(USPTO)が17日に公開した特許出願書類で明らかになった。
引用:コインテレグラフ
例えば、腐りやすい食品を発送する際に、その食品に対して適切な環境下で配送されるかどうか、小売店にとっては重要です。
小売店から配送業者を介して顧客の手に渡るまで、配送中の商品が置かれている詳細な情報を正しく記録することができれば、責任の所在が明らかになり、サービスの向上にもつながります。
株式会社デンソー(DENSO)
一方、日本の企業の自動車業界でブロックチェーンを活用しようとしているのは、自動車部品シェア世界第二位の株式会社デンソー(DENSO)です。
デンソーが独自のブロックチェーンプロダクトを発表したのは、2019年1月8日から11日までラスベガスで開催された世界最大級の技術展示会CES2019です。
CES2019では、IoTやVRと共に、ブロックチェーンが「テックトピック」として選ばれていました。
自動車業界でブロックチェーンを活用しようとしているのは、自動車部品シェア世界第二位の株式会社デンソー(DENSO)だ。
デンソーが独自のブロックチェーンプロダクトを発表したのは、2019年1月8日から11日までラスベガスで開催された世界最大級の技術展示会CES2019。
CES2019では、IoTやVRと共に、ブロックチェーンが「テックトピック」として選ばれていた。
デンソーが見据えているのは、自動運転車におけるセキュリティの確保です。
車載するデータをブロックチェーン化することで、車の状態や、周囲の状況に関する情報を改ざんから保護することができます。
仮に自動運転車が事故に巻き込まれた場合、ブロックチェーンに記録された「改ざん不可能なデータ」が、法的に車の持ち主や自動車メーカーを守ることになります。
自動運転車の実用化に向けて議論となっている「車がハッキング被害に遭う可能性」に対しても、一つの答えを提示することになると考えられます。
ブロックチェーンが守るのはセキュリティだけではありません。
車を売りたくなった場合、車載のブロックチェーン上に走行記録やメンテナンスの記録が残っていれば、その車が持つ正当な価値を元に売買できます。
これまで、「走行距離の改ざん」は、中古車売買では注意すべき不正の一つでしたが、ブロックチェーンを活用することができればそのような心配は不要になります。
実際のブロックチェーン活用によるトレーサビリティの事例

トレーサビリティ(traceability)は、trace(=追跡する)とability(=できる)が合体した単語です。
したがって、日本語では「追跡できるようにする」という意味になります。
何を追跡できるようにするかというと、原材料や生産過程に関する情報です。
消費者や関係業者が、製品の情報を手軽に追跡できれば、安心して製品を取引・購入することができます。
つまり、トレーサビリティを確保するということは、製品の出どころをはっきりさせ、偽装を許さないようにするということです。
トレーサビリティは、主に食品や工業製品、医薬品などの分野で使われる単語です。
原材料の状態から加工されて消費者に届くまでの製品情報をまとめて管理するシステムを、トレーサビリティ・システムと呼びます。
このようなブロックチェーントレーサビリティ技術の活用事例を挙げます。
製造業のトレーサビリティ
自動車など、部品の数が多く、生産の関係者が多岐にわたるものでは、どの企業・工場がどの部品のどの生産過程に関わっていたのかを明確にすることが重要です。
消費者が安心して自動車を購入・利用するため、製造業のトレーサビリティを確保する必要があります。
「ルイ・ヴィトン」は、「ConsenSys」「Microsoft」と共同でブロックチェーンプラットフォーム立ち上げを発表しました。
「AURA」と呼ばれるこのブロックチェーンプラットフォームは、商品追跡のために取り入れます。
ブロックチェーン企業のConsenSysが、LVMHとマイクロソフトとの提携のもと高級ブランド業界向けのコンソーシアムチェーン「AURA」を発表しました。
AURAはLVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)の子会社であるLouis VuittonやDiorの商品追跡に活用されることが決定しており、今後LVMH傘下の他のブランドにも使われることが検討されているといいます
引用:CRYPTO TIMES
「AURA」プラットフォームは、JPモルガンの「Quorum」ブロックチェーンプラットフォームをベースとして、イーサリアムのブロックチェーン上に構築されます。
AURAブロックチェーンを活用する事によって、従来不可能だった販売時からの記録追跡(トレーサビリティ)を可能にする事ができ、高級ブランド商品「ルイ・ヴィトン」などの真贋証明機能が期待されています。
食品のトレーサビリティ
小売店などに並ぶ食品のトレーサビリティを確保することは、消費者が安心して食品を消費する上で重要です。
消費者にとって、食品がいつ・どこで・誰によって生産されたのか、透明性が担保されていることが望ましいと言えます。
食品のトレーサビリティを確保することで、害のある食品の流通を減らし、悪質な生産者を特定・排除することが可能です。
ヨーロッパにおいてマヌカハニーのトレーサビリティをAMB-NETというブロックチェーンで改革するのはH!VE Honeyという企業です。
この提携によって、H!VE Honeyと協力関係にあるマヌカハニーの生産者は、消費者に対して高い品質を証明可能になり、他のノーブランドの蜂蜜と差別化することが可能になりました。
世界で最も不正や詐欺・偽装が多い蜂蜜のサプライチェーンにおいては、現在流通している多くの蜂蜜が水で薄められていたり偽物であったりします。
消費者が蜂蜜のQRコードをスマートフォンでスキャンすることで、品質管理や原産地などの確かな情報を得ることができ、自分の健康に対してより良い意思決定が可能になります。
物流のトレーサビリティ
物流業界で、搬送商品のトレーサビリティを確保することは、流通効率を高める上で重要です。
不良ロットの発生先の特定が容易になり、誤出荷についても原因の分析に役立ちます。
IBMとマースク(Maersk)はオランダの関税局と米国国土安全保障省と協力して自社のブロックチェーン技術を積極的にテストしています。
IBMと海運大手マースク(Maersk)が共同で運用するブロックチェーンプラットフォームに、さらに2社の大手海運会社が加わった。
現地時間7月2日の発表によると、世界第5位の海運会社ハパック ロイド(Hapag-Lloyd)と日本郵船(NYK)、商船三井(MOL)、川崎汽船(K-Line)のコンテナ船事業を統合したオーシャンネットワークエクスプレス(Ocean Network Express:ONE)が「TradeLens」ブロックチェーンに参加した。
ブロックチェーン技術は暗号署名に基づいているため、貨物の輸送中に誰かが商品を誤って盗まれたり、改ざんされたりすることが難しくなり、輸送中に消費する時間を短縮することができます。
同社は、消費者の抱える問題に対する対処と取引記録や戦略計画・分析データを保存するために、ブロックチェーンにどのようなデータを保存するのかを明らかにするプログラムを設計しました。
これからのブロックチェーンビジネスはどうなる?

もちろん、ブロックチェーンのトレーサビリティにも問題視されている点があります。
最も始めに入力する情報が補償されている必要がある
まず、「最も始めに入力する情報が補償されている必要がある点」です。
記録された情報が改ざんできない点においてブロックチェーンは優れていますが、そもそも最初に記録される情報自体が間違っていては本末転倒になります。
実物とデータが一致している必要がある
次に、「実物とデータが一致している必要がある点」です。
例えば、ある果物が産地でデータ入力されて工場へ輸送された後、小売店へさらに輸送される間、検品やICタグ等で管理されます。
ただ、最終的に消費者がこの果物を購入するまでの流通過程において、ICタグをはがしたり、箱の中身を入れ替えたりするケースもあります。
そのため、流通プロセスにおいて、箱の未開封状態を保証するといった「実物とデータの一致」をする工夫があれば上手くいくと考えられます。
大量処理ができない
そして、「大量処理ができない点」です。
ブロックチェーンは仮想通貨ごとに異なりますが、取引量が増加した時に処理性能が落ちて時間がかってしまう「スケーラビリティ」が問題となってきます。
最近では、各仮想通貨を開発した企業がアップデートなどを行いながら、スケーラビリティ問題を改善しているケースが多いですが、世界中の取引量を記録した時の膨大な取引処理が可能だという保証がされていません。
今後ブロックチェーン技術が発展してくとともに改善されるとは考えられますが、現状では各仮想通貨のブロックチェーン上における取引処理性能に差があります。
しかしながら、既存のトレーサビリティ・システムでは、各製品に対して個別に作業履歴を残す作業が必要でした。
製品のサプライチェーン上で関わる業者の数は多岐にわたり、それらを一貫して管理するのは困難です。
業者によっては取引履歴を紙で管理するというところもあり、取引履歴の改ざんが容易であるという課題も残っています。
ブロックチェーンの持つ、”書き込まれた情報は改ざんできない”という特性が、現在のトレーサビリティ・システムの課題を解決するかもしれません。
まとめ
国内ブロックチェーン活用サービスの市場規模は年々増加傾向にあり、今後はさらに様々なビジネスシーンで活用され増加していくことが予想されています。
食品・工業製品・医薬品など、身の回りにあるものに対する信頼性が高まれば、私たちはより安心した暮らしが送れるようになります。
そのため、ブロックチェーンを活用したトレーサビリティ・システムの研究・開発は、私たちにとって重要な課題であるといえるでしょう。








































