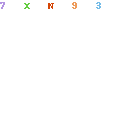
仮想通貨ヘッジファンド(投資信託)がついに日本上陸!ディジアセとは!?
仮想通貨などのデジタル資産を投資先としたヘッジファンド(投資信託)※1が、2018年10月15日に日本で公募を開始しました。
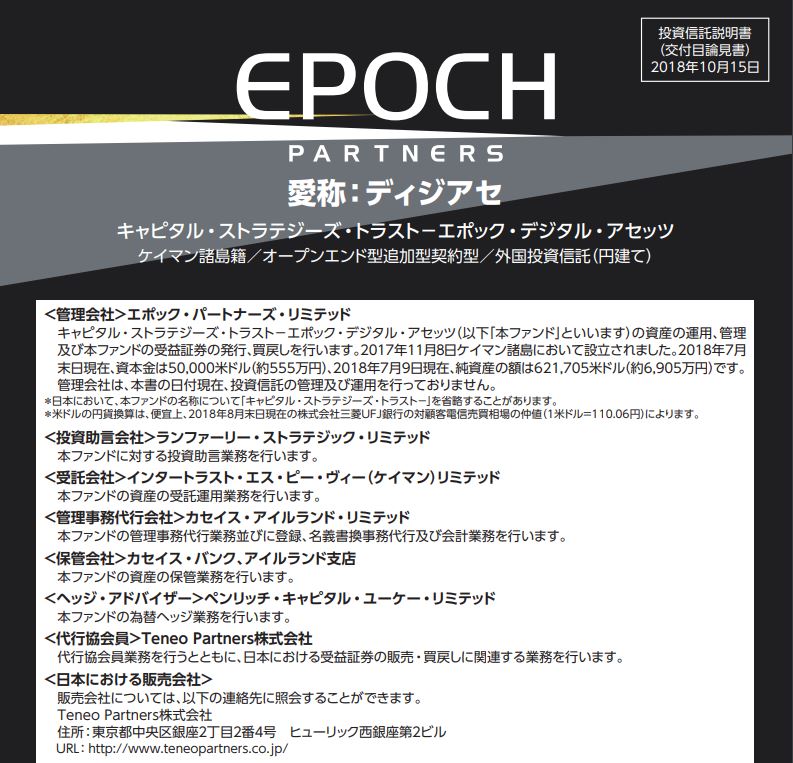
※1.投資信託とは、投資家から資金を預かり、預かった資金を運用して得た利益を投資家に分配する金融商品のことです。
厳密にいえば「ヘッジファンド」と「投資信託」は異なりますが、この記事においては同じものと理解していただいて問題ありません。
このヘッジファンドは「ディジアセ」と名付けられ、以下のような運営体制を取ります。
- 管理会社:エポッグ・パートナーズ・リミテッド
資産の運用、管理、受益証券の発行、買い戻しを担当。
- 投資助言会社:ランファーリー・ストラテジック・リミテッド
ディジアセに対する投資助言業務を担当。
- 受託会社:インタートラスト・エス・ピー(ケイマン)リミテッド
資産の受託運用業務を担当。
- 管理事務代行会社:カセイス・アイルランド・リミテッド
管理事務代行業務、登録、名義所管事務代行、会計業務を担当。
- 保管会社:カセイス・バンク(アイルランド支店)
資産の保管業務を担当。
- ヘッジ・アドバイザー:ペンリッチ・キャピタル・ユーケー・リミテッド
為替ヘッジ業務を担当。
- 代行協会員:Teneo Partners株式会社
日本における受益証券の販売、買い戻しに関連する業務を担当。
以上からもわかる通り、ファンドの管理会社はエポッグ・パートナーズ・リミテッド社(Epoch Partners Limited社)であり、日本における証券の販売、買い戻し業務はTeneo Partners株式会社が担当するということですね。
Teneo Partners株式会社は第1種、第2種金融商品取引業を金融庁から得ており、すでに日本で運営を開始している正式に認可されたヘッジファンドです。

投資案件は詐欺目的で行う所が多いですが、ディジアセのヘッジファンドは信頼性がとても高いと言えますね。
>>>仮想通貨トリビアで調査した詐欺目的の投資案件の数々はこちら
日本で進出したディジアセ(ヘッジファンド)の狙いは?
日本におけるヘッジファンド(投資信託)の認知度は諸外国と比較して極端に低く、相対的に金融リテラシーが低いことが分かります。
下記の画像は、関西学院大学「岡村ゼミナール」が調査した、日本における投資信託の現状と今後の課題です。

そんな日本でヘッジファンド(投資信託)を公募することは大変珍しいのですが、ディジアセには【ある狙い】があります。
それは「従来の仮想通貨投資家層とは異なる層からの資金を呼び込む可能性がある」というものです。
日本ではあまり認知されていませんが、多くの投資家はヘッジファンド(投資信託)を利用しています。
理由はシンプルに、ヘッジファンド(投資信託)は数十年の長い歴史があるため信頼感と浸透率が高いからです。
逆に、仮想通貨は最近流行りだした投資商品ですから、ヘッジファンド形式の投資に対応するか会社が少ないです。
その為、従来のヘッジファンド(投資信託)で投資を行ってきた投資家にとってはなかなか仮想通貨に手がだ出せない状況でした。
仮想通貨市場はこの1年衰退し続けており、そのソリューションとして一番重要なのが「機関投資家の仮想通貨業界参入による市場拡大」とされています。
>>>【仮想通貨市場の時価総額は将来1000%以上上昇する】とパンテラキャピタルトップが提言!したが、課題解決が重要であるとも指摘
ディジアセはまさにこのソリューションを具体化したサービスで、今まで仮想通貨投資をしていなかった従来の投資家層への仮想通貨業界参入を促すことによって、仮想通貨市場の拡大を実現できるのではないかと期待されています。
ディジアセが取り扱う「デジタル資産」とは?
ディジアセの目的として公開された「投資信託説明書」では以下のように記されています。
本ファンドの投資目的は、多様なデジタル資産投資戦略に投資する集団投資ビーグルに分散投資することにより長期的な資産の成長を達成し、絶対的なリターンを最大化すること。
本ファンドはこれらの値動きが激しい、しかし潜在的に収益性が高いと思われる資産の値上がり分の多くを獲得することを目指す一方、これに伴うリスクを管理することを目指す。
文中の「デジタル資産」とは主に以下の8つを指します。
- 仮想通貨
- トークン
- ICO
- 仮想通貨マイニング
- 仮想通貨レンディング
- ブロックチェーンその他の分散型技術(DLT)関連投資
- 人工知能(AI)
- スマート・テクノロジー
しかし、ディジアセはそれ以外の分野にも積極的に投資する方針ですから、今後が楽しみのヘッジファンドですね。
※免責事項
当記事は記事内にあるような投資信託や仮想通貨の購入を推奨するものではなく、購入に関する一切責任を負わない他、商品に関する問い合わせやリスク事項の確認は販売会社に問い合わせ下さい。
【参考文献】







































