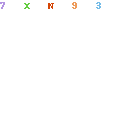
仮想通貨について調べたことのある方や、仮想通貨ニュースを日ごろからチェックしている人であれば、必ず目にしたことがある「ICO」という言葉。
そこで、この記事ではICOの意味や日本・海外におけるICO規制の現状を解説しています。
以下のような疑問・要望にも応えられる内容となっていますので是非ご覧ください。
- ICOってそもそも何?
- ICOって儲かるの?
- ICO詐欺の見分け方を知りたい!
この記事の目次
ICOの意味とは?

仮想通貨でいうICOとは、【Initial Coin Offering(イニシャル・コイン・オファリング)】の略名です。
日本語で簡単に言い換えると、
【新規仮想通貨公開】の名前で広く知れ渡っています。
ICOと似ている言葉としてIPO(新規株式公開)がありますね。
ICOとIPOの違いや特徴に関しては以下の記事で詳しく解説していますが、どちらも「事業遂行のための資金調達」を目的に実施されることが主です。
日本のICO規制の現状

日本におけるICO規制について、気になるのは「ICOが禁止されているのか否か?」ですよね。
結論から言うと、日本におけるICOは法律的に禁止されているわけではありません。
2019年4月現在では、ICOを直接規制する法律は存在しておらず、現行法でカバーリングしているというのが現状です。
適用される可能性のある現行法としては「消費者契約法」や「金融商品取引法」などがあげられます。
ただ、ICO規制に関連する法整備は各国の急務とされており、日本の金融庁も2019年度中の国会にてICOを規制する法案の提出を目指しています。
2018年12月の報道では、金融庁が来年の通常国会にて、金融商品取引法、資金決済法の改正案の提出を目指しており、今回のICO規制で投資家に対する勧誘を制限し、個人投資家保護を図る方針であることが明らかになっています。
新しい規制では「投資型」のICOに参加できるのはリスク判断をはじめとする、いわゆる「目利き」ができるファンドなどの「プロの機関投資家」に限定します。
個人投資家が参加できるのは「決済型」のICOのみで、「決済型」のICOにおいても、仮想通貨業界が「実施内容の審査基準」といった自主規制ルールを整備する可能性もあるということです。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
ただ、日本でICOを行う際に注意しなければいけないのが「改正資金決済法」です。
改正資金決済法では、「仮想通貨に該当する商品を取り扱う場合、発行体は金融庁に対し仮想通貨交換業の登録を行う必要がある。」と定められています。
すなわち、発行体が発行したトークンが、法律用語上の「仮想通貨」に該当するのであれば、発行体は仮想通貨交換業の登録を行う必要があるのです。
一部の法律の専門家によると、発行体が発行したトークンが「仮想通貨」に該当する場合でも、改正資金決済法の規制を受けないケースがあるといいます。
それが発行体が「仮想通貨の信用取引」を提供する場合です。
【専門家の見解】
改正資金決済法の規制対象となるのは、「仮想通貨の売買・交換」を行う場合であり、「仮想通貨の信用取引」を行う発行・事業体は規制対象外。
仮想通貨交換業の登録は難しい
ここまでご覧いただいた方の中には、次のように考えている方もいるかと思います。

発行したトークンが仮想通貨に該当するとしても、仮想通貨交換業の登録をすれば済む話でしょ?
簡単じゃん!
実は、仮想通貨交換業の登録を実現するのは、ものすごく難しいことなのです。
発行体が仮想通貨交換業の登録を完了すまでの流れは以下の通り。
- 金融庁に仮想通貨交換業の登録申請を提出
- 金融庁が発行体の審査を開始
- 発行体が審査項目をクリア
- 仮想通貨交換業者として認可が下りる
難しいとされているのが「3.発行体が審査項目をクリア」で、これまで金融庁の審査をクリアした企業はわずか19社となっています。(2019年4月現在)
先日、関東財務局から仮想通貨交換業者としての認可を取得した楽天(楽天ウォレット)も、登録申請(2017年9月)から認可取得(2019年3月)まで約1年半の時間を費やしています。
日本の大手取引所として知られるCoinCheckも楽天同様、登録申請~認可取得まで1年半近くかかっています。
登録申請を行った数千の企業のうちわずか19社しか認可を取得できていない点や、楽天などの大企業でも認可取得に年単位の時間を要している点を踏まえると、
少なくとも、”登録は簡単なことではない”ということがお分かりいただけるのではないでしょうか。
海外のICO規制の現状

日本におけるICO規制に続いて、ここからは「海外のICO規制の現状」を紹介します。
仮想通貨規制で世界をけん引している「アメリカ」を含めた、以下5か国のICO規制の現状を解説していきます。
- アメリカ
- 中国
- 韓国
- 香港
- シンガポール
アメリカ
アメリカでは、2016年6月に発生した「The DAO 事件」をきっかけに、「認可されていないICO(による資金調達)案件は証券取引法の対象となる」と明言しました。
トークンが有価証券に該当するかどうかについては、「Howey Test」という基準が設けられており、ICOトークンの場合もHowey Testが適用されると考えられます。
Howey Test
1.It is an investment of money(金銭による投資か)
2.There is an expectation of profits from the investment(投資により利益を期待できるか)
3.The investment of money is in a common enterprise(共同事業に対する投資か)
4.Any profit comes from the efforts of a promoter or third party(他社の努力により利益がもたらされるものか)
アメリカ証券取引委員会(以後SEC)の現長官Jay Clayton氏(以後ジェイ・クレイトン氏)は12月6日に行った年末スピーチで、仮想通貨ICOの問題点について次のように言及しています。
デジタル資産とICO市場については、投資家保護が実質的に不足しており、
そのためICO詐欺や市場操作の機会も増えてきている。
また、「ICOは有効な資金調達法」だと認めつつ、「証券法は必ず遵守すべき」との見解も示しています。
私はICOが、起業家などにとって効果的な資本調達方法であると思っています。
しかし、(ICOにおいて)証券が提供される場合、証券法を遵守しなければならないという基本的な点変えることはありません。
中国・韓国・香港
中国・韓国ではICOは全面的に禁止されています。
周知のとおり、中国では仮想通貨そのものが全面的に禁止されています。(ICO禁止が発表されたのは2017年8月。)
ビットコインETFの検討が行われるほど仮想通貨に前向きな姿勢を見せる韓国では、以下2点を理由に仮想通貨ICOが禁止されています。
- ICOはバブル要素・リスクが高い
- 投資家が詐欺被害に遭いやすい
香港政府は2017年9月、中国のICO禁止の発表を受け「ICOの規制は行わない」との声明を発表。
ただ、ICOの仕組やトークンが、香港における”証券法”に抵触しないことが条件とされています。
シンガポール
シンガポールは、ICO関連の規制が比較的整っていることで知られています。
シンガポール政府は2017年7月、シンガポール金融管理局(MAS)管轄の元、ICO規制が開始されました。
香港などと同様に、証券性をもつトークンは証券先物法の規制対象とされています。
対して、証券性を持たないトークン(ユーティリティトークン)に関しては特に規制が敷かれていません。
ただ、決済・送金に利用できるトークンの場合は、資金決済法に抵触するケースがあるため、規制が完全に敷かれていないとは言い難いのが現状です。
ICOのリスク・危険性

仮想通貨業界はまだまだ投機的な側面が強いとされ、ICOに参加するユーザー・投資家も利益を得ることを目的としている方がほとんどです。
そのような方々は、自身の資産をICOにつぎ込むうえで、それに伴うリスクを把握しておく必要がありますね。
ICOを行う上でのリスクは主に3つ存在します。
- 詐欺・犯罪に巻き込まれるリスク
- トークン価値が暴落するリスク
- (例外)プロダクトが進行しないリスク
では1つ1つ解説していきます。
詐欺・犯罪に巻き込まれるリスク
前述した通り、ICOはIPOとくらべ比較的簡単に行うことができるので、資金調達を装った犯罪(詐欺)に利用さることが多々あります。
この点に関しては、日本金融庁だけでなく各国政府から注意喚起がなされており、規制が追い付かないと判断した国ではICO自体が禁止されるケースも存在します。(中国・韓国など)
ICOが実施しやすい理由は主に以下2点。
- 法律・規制の未整備
- 銀行・証券会社の審査が不要
これらの「手軽さ」が、”審査・初期費用の緩さ”という形で裏目に出てしまい、犯罪につながったというわけですね。
トークン価値が暴落するリスク
ICOで発行されるトークンはいわゆる「仮想通貨」ですから、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などと同様に、ボラティリティ(価格変動制)が存在します。
「ICOの実施により資金調達成功→プロダクトも成功」という流れであれば、トークン価値も上昇し、発行体・ユーザー双方に様々なメリットがもたらされます。
しかし、仮に「資金調達成功→プロダクト失敗」や「資金調達失敗」となった場合、トークン価値は下落し、含み損だけが発生する状況となってしまいます。
「仮想通貨長者」「億り人」などの言葉が生まれたように、初期段階の仮想通貨(ICOなど)に投資することには大きなメリットが存在しますが、
トークン価値の暴落により損失を被る可能性があるということも念頭に置きながら、自身の資産を投じましょう。
(例外)プロダクトが進行しないリスク
3つ目は「プロダクトが進行しないリスク」です。
これは、ICOに「投機目的」ではなく、純粋な「支援・応援」の気持ちで資産を投じた方向けのリスクになります。
先述した通り、ICOは基本的に、”発行体・事業体が開発したいプロダクトに必要な資金を調達すること”を目的として行われます。
しかし、仮に資金調達に成功したとしても、開発がうまく進むとは限りません。最悪の場合、プロダクトを担う企業が倒産するリスクもあるのです。
この、いわゆる「信用リスク」はICOだけでなく 株式投資・融資などにも存在するリスクですが、比較的小規模な事業体が発行体となるICOでは、必然的に信用リスクが増加します。
純粋な「支援・応援」の気持ちでICOに参加したユーザーでも、その期待を裏切られるリスクがあるということをお忘れなきよう。
ICO詐欺に遭わない方法

前述した通り、ICOには様々な危険性・リスクが存在していますが、魅力的なメリットが隠れているのもまた事実。
その隠れたメリットを手にするために、詐欺に遭わず且つICOに参加する方法を解説します。
ICO詐欺に遭わないためにはまず、ICO詐欺かどうかを見極める必要がありますね。
ここからは、これからICOを購入を考えている方に知っておいてもらいたい、ICO詐欺を見分ける方法以下4つをお伝えします。
- ICOを公開しているHPの翻訳が”日本語にしか”対応していない
- ICOトークンの買い取り保証がある
- ICOのホワイトペーパーを調べる
- ICOを行っている開発者や関係者を調べる
ICOを公開しているHPの翻訳が”日本語にしか”対応していない
これは、情報弱者の多い日本を狙った海外のICO案件に多く見られます。
2017年後半のバブル崩壊後、日本では仮想通貨の熱は一気に冷めましたが、それを逆手に取っている海外の詐欺グループは多いです。
要するに、なぜ、世界では比較的仮想通貨人口が少ないとされる日本の言語のみに対応しているのか、疑問に思う必要があるということです。
ICOトークンの価値織保証がある
ホワイトペーパーとは、事業者が今後サービスを展開していく為の、計画書の事です。
ホワイトペーパーには一般的に以下の事が主に記載されています。
- 概要
- 背景と目的
- ターゲット業界の課題
- プロジェクト(暗号通貨)による解決方法(サービス内容)
- 暗号通貨(またはプラットフォーム)の技術解説
- 資金調達方法(ICOによりどの仮想通貨が交換対象になるのか
- プロジェクトのスケジュール・ロードマップ
- 開発者や関係者
上記は、順番が違ったり、項目が増えたり減ったりするといった変動はありますが、主に記載されている事の多い項目です。
特に注目すべき点は、開発者や関係者メンバーです。
ICOとは、まだまだ広く知れ渡っていない為、壮大なビジョンや魅力溢れるサービスはいくらでも記載する事が出来る為、いくらでも偽装する事が出来ます。
また、公式サイトやホワイトペーパーが無いICOの場合は、そもそも詐欺の場合が多い為、購入はオススメしません。
検索を行う場合は、検索画面で【ICO ICOの名前】と、ICOの名前の部分に、気になるICO名を入れる事によって調べる事が出来ます。
ICOのホワイトペーパーを調べる
先ほど、ホワイトペーパーを見る上で開発者や関係者メンバーを見るのがとても重要だとお伝えしましたが、開発者や関係者は、本当に実在するか調べましょう。
検索するだけでなく、Twitterなどを駆使して調べる事によって、本当に実在する人物であるかを調べる事が出来ます。
ホワイトペーパーに記載されている人物画像と、実際に調べた人物画像が明らかに異なるまたは、実在しない場合であれば、詐欺である可能性が高いです。
ICOを行っている開発者や関係者を調べる
仮想通貨は、投資商品です。
投資である為、価値はいくらでも下がる可能性があります。
場合によっては、価値が無くなってしまう可能性だってあります。
情報弱者にとって、「価格が下がっても保証してくれるから大丈夫…」と思われるかもしれませんが、仮想通貨に現物があるわけではありません。
現物がない、仮想の通貨の為、事業者側は原価0円で仮想通貨を発行する事が出来ます。
その為、事業者側が、「価格1/10まで下がっても元値で買取保証します!」と謳っていたとしても、痛くもかゆくもないのです。
まとめ
ICO規制の現状や、ICO投資の危険性などについて、深くご理解いただけたかと思います。
後半部分では、「詐欺に遭わない方法を4つ」をご紹介しましたが、上記4つすべてに共通していることが「信頼を保証できる確証を得ろ」ということです。
嘘をついていないという確証を得ない限り、ICO投資はするべきではありません。
一部の情報・宣伝・流行りに惑わされずに、自分の目で見て、頭で考えることが重要ですよ。
ICO詐欺の見分け方については以下の記事でさらに詳しく解説してありますので、「絶対に詐欺に遭いたくない!!」と考えている方は是非ご覧下さい。









































