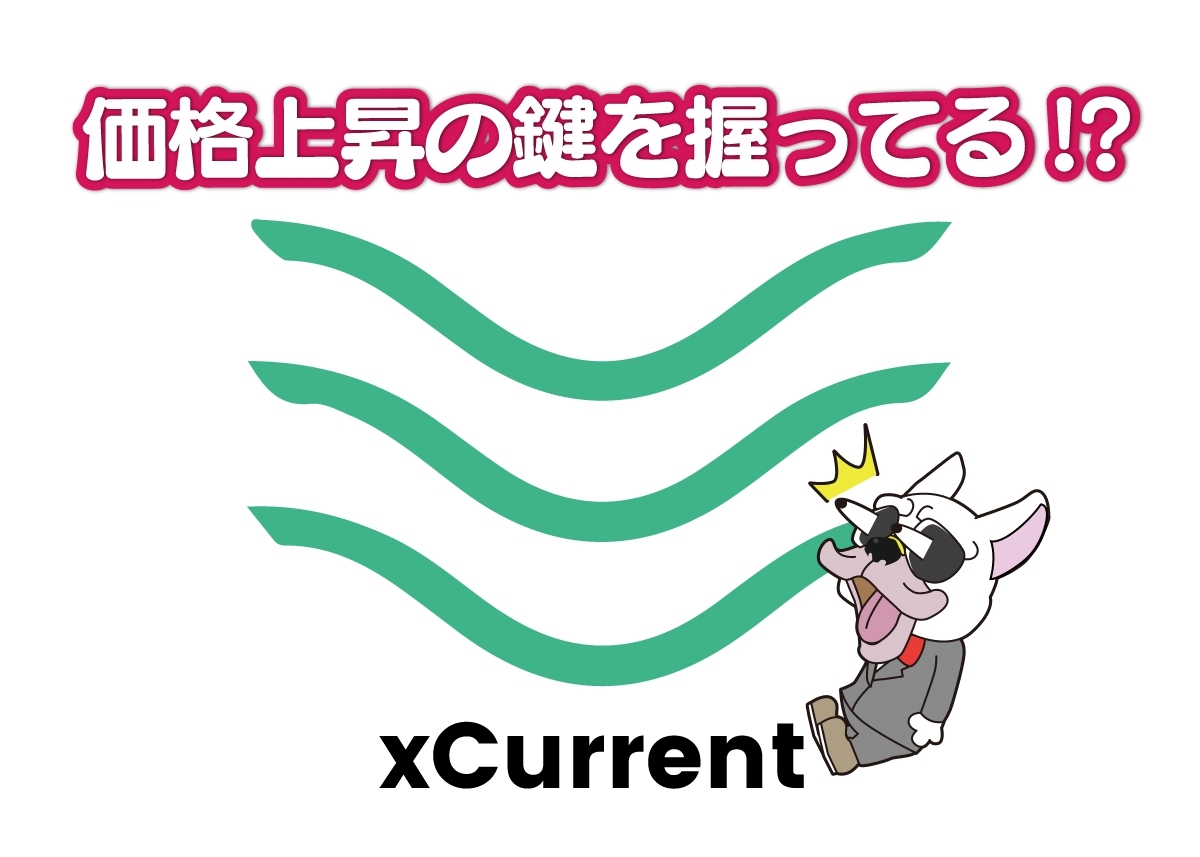
リップル(XRP)の価格が今後上昇を期待できる理由として、Ripple社のxCurrent(エックスカレント)システムには、やはり注目すべき特徴の1つですね。
本記事では、Ripple社のxCurrentについて、次の4つを紹介します。
- xCurrentとは/特徴
- xCurrentの仕組みとILPの関係性
- xCurrentのメリット
- xCurrentがもたらすRipple社の今後
以上のことを徹底的に紹介しますので、ぜひ最後まで読んで、リップル(XRP)の知識を増やしていきましょう。
この記事の目次
Ripple社のxCurrentとは/特徴
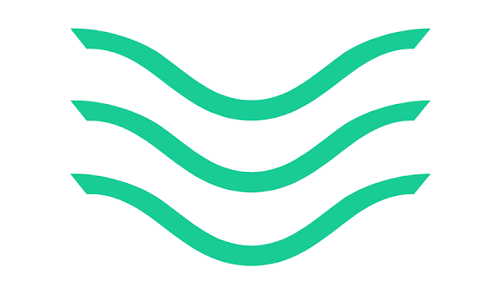
xCurrentとはRipple(リップル)社が提供する法人向けのソリューションのひとつです。
xCurrentの特徴は、国際的な送金を可能にすることです。
下記は、Ripple社が提供する公式動画です。英語字幕ですが、xCurrentについて分かりやすいので見てましょう。(時間:2分32秒)
そして、現在の国際送金(SWIFT)の課題は、次の3つがあります。
-
- 手続き完了までの時間
- 異なる通貨同士のスワップ
- 送金して着金するまでのコスト
以上の問題を解決する為に、Ripple社は、xCurrentという送金システムを開発しています。
つまり、個人間の国際送金を瞬時に行えるようになるには、最初に銀行同士で資金を自由に動かせる基盤が必要だということです。
そして、送金システムを構築するには、まずそれぞれの銀行のネットワークを統一した規格で、相互に情報を伝達させる仕組みが必要です。
xCurrentを知るには、まずILPについて知っておく必要がありますから、先にILPを見ていきましょう。
xCurrentのIPLをまず知っておこう!
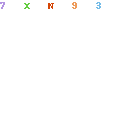
Ripple社では、独自の分散型台帳技術で実現を可能にしています。
実現可能に出来る理由は、異なる銀行もしくは企業間で、Interledger Protocol(インターレジャープロトコル)という標準規格を採用しているからです。
金融機関がRipple社の標準規格を導入するためには、リップルネットワーク(Ripple Net)に参加しなくてはなりません。
つまり、Ripple社のILPとは、通貨同士を複雑なスワップで交換したり、ブリッジ通貨を利用することなく、瞬時に送金ができる仕組みのことです。
xCurrentの仕組み
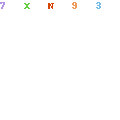
先述したILPの仕組みを踏まえてxCurrentの仕組みを説明すると、まず各銀行では、独自の仮想通貨を発行して提供していきたいという思惑があります。
しかし、地方銀行などの地域密着型で経営している場合には、独自の通貨を発行する資金やプロセスを考えると難しいのが現状です。
そこでRipple社のILPが、改めて注目されるようになりました。
Ripple社のILPは、銀行パートナーがネットワーク上に存在すれば、コストを抑えられ容易な手続きで国際送金ができるからです。
Ripple Netの参加者は、添付メッセージとともに決済リスク(※1)の一因である検証データを正確にxCurrentで処理していきます。
そして、xCurrentで処理をしていくことで、銀行間の送金着金時間と手数料を、大幅に減少させることに成功しています。
決済リスクとは、銀行同士が事前に情報を開示せずに、処理を進めると正確な処理ができないことを指しています。
国際送金では異なるネットワーク同士でのやりとりを強いられ、事前に検証するデータの照合に時間がかかります。
しかし、xCurrentでよく混同しがちなのが、ネィティブトークンであるXRPの存在です。
xCurrentはRipple Netに参加している銀行や企業は、XRPを必要としなくても送金ができます。
ですから、xCurrentはXRPの流動性にはあまり関係がありません。
簡単に言えば、まず基盤となる分散型台帳があって、目的別のリップル社製品(ここではxCurrent)を利用して送金をシームレス(※2)にしているということです。
xCurrentのメリット
xCurrentのメリットは、xCurrentを採用する銀行や企業が増えるにつれて、結果的に個人間での決済や送金を促すことに繋がることです。
例えば、Ripple社とSBIグループが10月4日にリリースした決済アプリMoney Tapは、xCurrent対応です。
そのため、決済アプリでありながら、異なる銀行口座でも瞬時に資金移動ができます。
つまり「Money Tap」のアプリケーション内であれば、国際送金であっても手数料に関係なく送金が可能です。
Money Tapを利用できる日本国内の銀行は現在(10月23日)では、3社のみに留まりますが、異なる銀行間でも手数料がかからないのは、xCurrentのシステムがあるからです。
ですから、xCurrentのシステムを使用したサービスは今後も広がっていくと考えることができるでしょう。
xCurrentがもたらすRipple社の今後
Ripple社のXRPの流動性を高める個人間決済をより浸透させるには、まず銀行同士が単一のネットワークで情報を共有するシステムが重要です。
そのため、Ripple社が2013年から活動してきた割に、中々XRPの価格が上昇しなかった理由だったといえましょう。
逆にxCurrentの仕組みだけを銀行が採用して、XRPの価格上昇に繋がらないといった意見もありました。
しかしRipple社は国際的な取引を、ネットワーク内でやっていくことが目的です。
ですから、ネットワークのセキュリティ保護の他に、法律も関わってくる為、Ripple社が飛躍するのに時間がかかるのは当然でしょう。
しかし、Ripple社が根気強く活動を進めていくことで、xCurrentが採用された決済アプリがリリース現段階では、メリット以外のなにものでもありません。
そして、日本では三菱東京UFJ銀行が早くから、Ripple社の国際的な動きに反応していました。
さらには、SBIグループが先導している「内外為替一元化コンソーシアム」に賛同する銀行や決済プロバイダが増えているのがその証拠です。
また、xCurrentは、資金の流れを透明性の高いネットワークで可視化できるマネーロンダリングも解決できると期待されていますから、Ripple社の今後には今後も注目ですね。








































