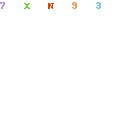
近年注目されている技術の一つにブロックチェーン技術があります。
このブロックチェーンはデータベースを構築する技術の一つです。
従来のように中央に巨大なサーバーがあり、それを各自でアクセスしデータを更新していくという中央集権的なデータベースの技術と異なり、ブロックによるデータ管理でユーザー各自が分散して同じデータベースを共有するという特徴があります。
このブロックチェーン技術にはパブリック型とプライベート型があるのですが、その違いを説明できる方は意外と多くはありません。
そこで今回、このブロックチェーン技術のパブリック型にフォーカスし、その特徴やプライベート型との比較、ブロックチェーン技術を活用した事例や課題について説明していきます。
これを読めばきっとブロックチェーン技術、特にパブリック型の知識を得ることができるのではないでしょうか。
この記事の目次
パブリック型ブロックチェーンとは

一切の中央集権的機関が必要ない
パブリック型ブロックチェーンはオープン型ブロックチェーンとも呼ばれるものです。
一切の中央集権的機関が必要ないデータ管理が行われているもので、Bitcoinに使われているPoW(プルーフ・オブ・ワーク)と呼ばれるデータ更新の同意に関する仕組みが代表的なものです。
文字通り、パブリック(広く開かれた)ブロックチェーンと言えます。
そのため公平性のあるデータ管理や取引が提供され、不正を行うことも難しく、セキュリティの高さも特徴的なブロックチェーンと言えます。
パブリックチェーンとは、管理者が存在せず、世界中の不特定多数のノードが相互に承認し合うブロックチェーンの仕組みです。
ビットコインをはじめとするブロックチェーンはパブリックチェーンの仕組みを採用しています。
引用: LIQUIDブログ
広く開かれ、透明性が高く、不正や改ざんは実質不可能
仮想通貨を暗号通貨と呼ぶ流れがありますが、この不正のできないセキュリティの高さからそう呼ばれているということも理解できるのではないでしょうか。
このように、広く開かれ、透明性が高く、不正や改ざんが実質不可能というデータベースの管理システムがパブリック型ブロックチェーンと言えるのです。
民主的で様々な特徴を持ち、将来性のある技術なのですが、様々な課題も持っており、それの解決が望まれている技術でもあります。
このパブリック型ブロックチェーンについて、これから順次解説を行っていき、理解を深めていっていただきます。
パブリック型ブロックチェーンの特徴

パブリック型ブロックチェーンの特徴について説明していきます。
パブリック型ブロックチェーンは主な特徴が3つあります。
- 中央管理者が存在しない
- ネットワークへの自由参加
- 取引承認を参加者で行う
中央管理者が存在しない
中央管理者が存在しないというのがパブリック型ブロックチェーンの最初の特徴です。
ブロックチェーンの取引情報は公開されていて、今読んでいる方でも操作を行えば閲覧が可能なくらい開かれたシステムです。
端的に言うと民主的なシステムと言えます。
この中央集権、中央管理をなくしたことにより、システム障害によってデータベースがダウンしてしまうこともなく、安定したシステム運営が可能となっています。
また、管理者が不正を行うあらゆるリスクの排除や、管理者が得る手数料の排除した上でネットワーク維持を可能にしたという点で画期的な特徴として挙げることもできるのです。
ネットワークの自由参加
ネットワークの自由参加も可能というのも特徴のひとつです。
管理者がいないため、P2P(Peer to Peer、ピアツーピア)という仕組みでネットワークを管理しています。
これは他の利用者(ピアと言います。)と対等にデータの提供および要求・ アクセスを行う自律分散型のネットワークモデルです。
Peer to Peer(ピア・トゥ・ピア または ピア・ツー・ピア)とは、複数の端末間で通信を行う際のアーキテクチャのひとつで、対等の者(Peer、ピア)同士が通信をすることを特徴とする通信方式、通信モデル、あるいは通信技術の一分野を指す。P2Pと略記することが多く、以下本項目においてもP2Pとする。
引用:Wikipedia
このパブリック型ブロックチェーンは、この仕組みを利用し取引データを共有・管理し合うことによって運営されており、取引情報は全て公開されているため、誰でも参加可能となっています。
取引承認を参加者で行う
取引承認やデータの更新の承認を参加者で行うのも特徴です。
管理者がいないため、参加者が取引の承認を行う作業が必要になるのですが、この作業のことをマイニングと呼びます。
この言葉は聞いたことがある方も少なくはないですが、マイニングとはこの承認作業のことを言い、仮想通貨ではこの承認作業を成功させた人に報酬を支払うという仕組みを採用しています(ビットコインであればビットコインを支払う)。
このマイニングは誰でも参加できるというメリットがあります。
このようなに民主的な仕組みの上に3つの特徴が備わっているのがパブリック型ブロックチェーンの特徴なのです。
パブリック型ブロックチェーンとプライベート型ブロックチェーンの違い

パブリック型ブロックチェーン以外にもプライベート型ブロックチェーンがあるということは冒頭でもお話ししました。
では、その違いである以下の3つの特徴を見ていきましょう。
- 中央管理者の有無
- 参加資格
- 承認
中央管理者の有無
パブリック型は中央管理者がいないということは先ほどもお話ししましたが、プライベート型は文字通り「私的な」という意味を持っているため、中央集権的なシステムという特徴があります。
そのためデータを集中的に管理している存在がネットワーク上にあるかないかという違いがあります。
参加資格
参加資格も異なります。
パブリック型は参加が自由ですが、プライベート型は参加するのに許可が必要です。
許可を与えるのは管理者であり、事前に決められています。
そのため自分(中央管理者)の望ましくない参加者や信用できない参加者をあらかじめ除外することができるのです。
承認
承認も異なります。
パブリック型は参加者誰もが承認作業に参加できますが、プライベート型は基本的に管理者と許可された参加者によって取引の承認が行われるというスタイルです。
参加者が選別されており、不正を行う者はいないという前提のもとに成り立っているのがプライベート型なのでマイニングが必要ありません。
それぞれのメリット
これらの違いからそれぞれのメリットを挙げてみましょう。
パブリック型はオープンで民主的なブロックチェーンのため、透明性が高い点や不正や改ざんがされにくい、そして一人が何かしらの原因でダウンしてもシステムは安定して動き、最悪ほとんどの参加者が紛争や天災でブロックチェーンに参加不能となっても残った参加者の中でデータは残り、ブロックチェーンも残った参加者だけで運営できるという堅牢性もあります。
プライベート型は、管理者が存在しているためシステム変更が容易であるという点、管理者等承認に参加する人数が少ないため取引やデータ記録が非常に迅速というメリットがあります。
このように堅牢性や透明性のパブリック型とシステム変更の用意さとスピードのプライベート型という違いでまとめることもできるのです。
パブリック型ブロックチェーンを活用した事例

パブリック型ブロックチェーンはすでに様々な場面で活用が行われています。
このパブリック型ブロックチェーンを活用した事例を3つ紹介し、具体的にどんなものに使用されているのかお話しします。
- ビットコインなどの仮想通貨
- 不動産のデータ管理のREX
- 美術品の売買履歴管理のverisart
これらはパブリック型ブロックチェーンの透明性や堅牢性に注目して作られた事例です。
ビットコインなどの仮想通貨

最初に紹介するのがビットコインなどの仮想通貨です。
仮想通貨は暗号資産という名前もある位、財産と密接な関係があります。
そのため、財産の移動(送受金、売買など)に関しては厳格な透明性と公平性、そして堅牢なデータ管理が必要となります。
そういった意味でパブリック型ブロックチェーンは最適と言え、そもそもこのビットコインの技術が現在の様々なブロックチェーン技術に応用されているといっても過言ではありません。
ちなみにビットコインに限らずイーサリアムやその技術を生かした様々なアルトコインは、ほぼすべてがこのパブリック型ブロックチェーンを採用しています。
不動産のデータ管理のREX
不動産のデータ管理のREXはアメリカの不動産取引を管理するネットワークです。
REXは本格運用が行われていませんが、アメリカにおける土地取引の履歴管理と言った不動産取引に関する情報を、ブロックチェーンによって分散管理するという方法を採用することによって公正で透明性があり、テロや内戦など不測の事態が起こっても土地取引のデータが保持されるというメリットを生かしています。
ちなみに従来のネットワークは土地取引に関する専門資格を有する専門家しかアクセスできませんでしたが、REXはパブリックに様々な参加者が利用できるとしています。
美術品の売買履歴管理のverisart

最後が美術品の売買履歴管理のverisartです。
取引履歴を厳格に管理すれば美術品の真贋も管理できるという考えの元、広く参加者を募り、その参加者たちの承認によって履歴が管理されていくという事例です。
パブリック型ブロックチェーンは、暗号資産や土地、美術品などの資産を管理するデータベースとして活用されている傾向があります。
パブリック型ブロックチェーンの課題

このように広く使われているパブリック型ブロックチェーンですが、主に2つの課題があります。
- システムの変更が困難である
- 取引の承認に時間がかかる
システムの変更が困難である
パブリック型ブロックチェーンは民主的な特徴がある一方、民主的すぎるという課題を抱えています。
システムを変更するという作業だけでも参加者の同意が必要であり、全員の同意がいるというルールを決めてしまった場合、システム変更すら不可能になるという恐れがあります。
そのため、実情に合わないブロックチェーンになって改良を試みようとすることも難しく、そういった事態に直面した時にどう対処するかというのが課題になっているのです。
取引承認に時間がかかる
もう一つが取引承認に時間がかかるということです。
参加者の承認が得られなければ取引のデータが記録できないため、例えばビットコインでは買い物の決済で相手に送金が反映されることでさえ10分以上の時間がかかってしまいます。
この取引承認に時間がかかる課題のため、様々な工夫がされ解決を試みようとする動きが存在するのです。
この二つの課題は深刻であり、純粋なパブリック型ではなく、複数の信頼性の高いノード(参加者)のみが合意形成を行うコンソーシアムチェーンと呼ばれるブロックチェーンを採用する事例もあります。
パブリック型ブロックチェーンのまとめ
パブリック型ブロックチェーンはブロックチェーンのタイプの一つで、データベースの管理を広い範囲で行うという特徴があります。
そして様々な場面で利用が行われており、今後もその流れは進んでいくものと言われています。
しかし、課題もあり、この課題をクリアしていった先に更なる展望が開けていく技術と言えるのではないでしょうか。












































