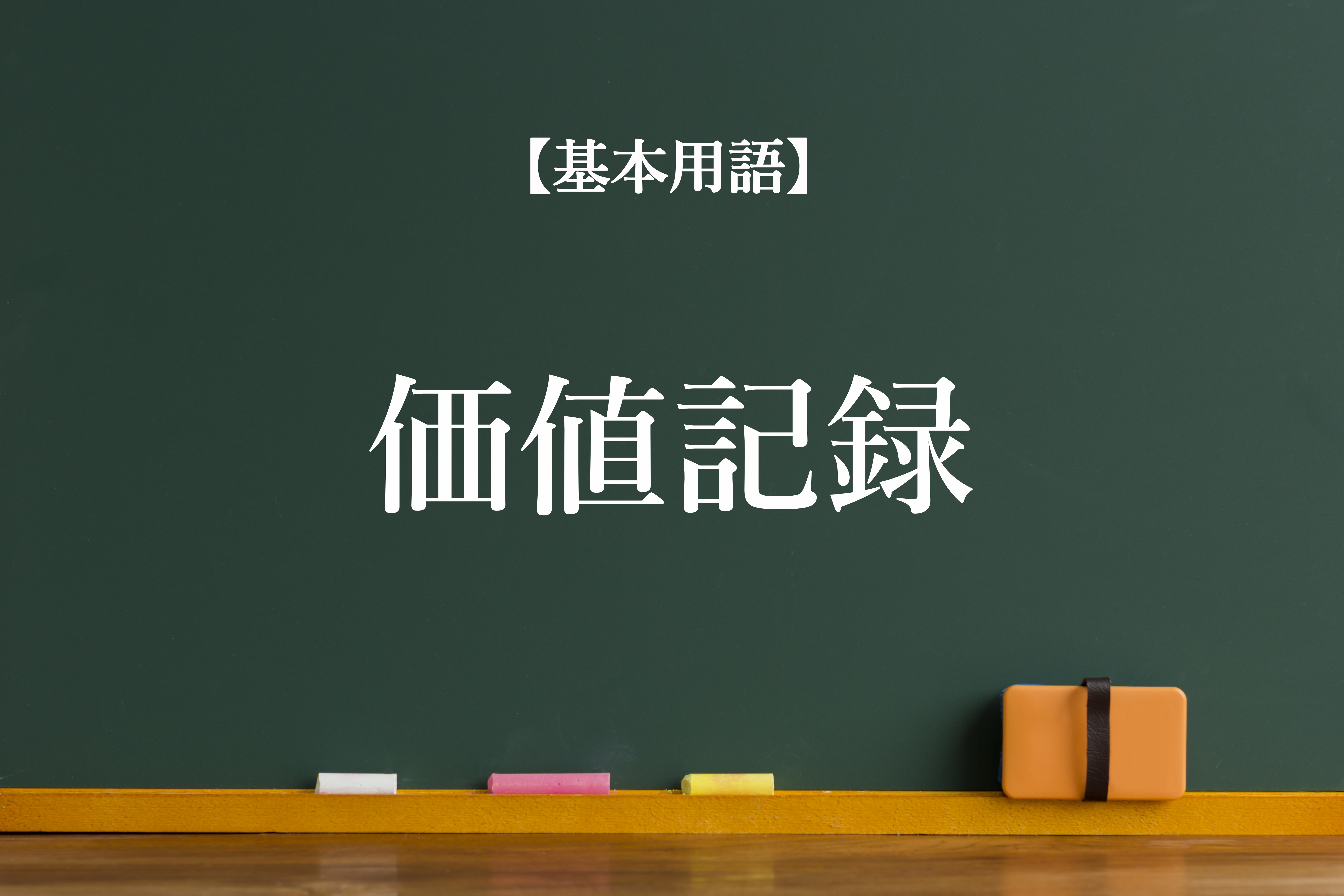
仮想通貨における価値記録の意味とは
価値記録とは、日本では「価値を持つ電磁的記録」と定義されています。
円やドル等の通貨でもなく、モノでもない「価値記録」の総称で新しい分類に属するとされています。
現在は「仮想通貨」「暗号通貨」といった言葉が社会に浸透しているため、価値記録と呼ばれることは少なくなっています。
通常「モノ」の売買には消費税が課税されていますが、価値記録は「通貨」や「モノ」ではなく「支払手段」として位置づけられているため、消費税は非課税となっています。
また、個人が価値記録を使用することにより生じた収入は、雑所得として区分され総合課税の対象となります。法人の場合は営業収入となります。
電子マネーも通貨そのものでないため価値記録の仲間と勘違いされやすいですが、価値記録とは違います。
そもそも電子マネーとは、サービス提供元でシステムへ事前に入金した金額を利用できるサービスです。
クレジットカードとは異なり支出をセーブできる利便性の高い「お財布」のようなシステムです。
価値記録の市場が活発化するとともにテロ資金対策やマネーロンダリング(資金洗浄)の観点から法整備の必要があったため、
2017年4月に仮想通貨に関する法「仮想通貨法(改正資金決済法)」が施行され、仮想通貨が法的に「通貨の機能がある」ものとして認定されました。
また、仮想通貨の売買取引所に登録制度が導入され、「仮想通貨交換事業者」として監督官庁である金融庁への登録を義務付けられました。
無登録の取引所や不正を行った取引所は、業務改善命令や業務停止命令などの警告や行政処分が行われます。
法整備が整ったことにより、投資家に安心感が生まれ市場のさらなる活発化が予想されます。
しかし、規制がない頃から自由売買をされていた投資家にとっては、利便性の低下や新規投資家の大量参入により価格の下落や資産減少の可能性が出てきたと懸念されています。







































