
Ethereumの特集も今回が最後となります。
今回はEthereumの将来性と、今後の市場価格について焦点を絞って行きたいと思います。
その分内容も濃いものとなり、かなりの長文になりますが、よろしくお付き合いください。
この記事の目次
はじめに

ETHは現在、時価総額でXRPと2位の座を争っています。
特に日本の市場では、XRPがBTCよりも保有率が高いという調査結果が出ていましたし、当トリビアでもその話題に触れさせていただきました。
ただこれは、投機的な背景があると考えられます。
「投機的な価値がある」と判断した上での保有であり、XRPがBTCやETHより優れているということではないと考えています。
事実、XRPは銀行間の送金に特化した仮想通貨です。
しかもトランザクションを担うノードは、XRPを統括する組織がその承認権を持っているという、プライベート(中央集権)的な一面も持ち合わせています。
対して、BTCはこれまでにもお伝えしているように、通貨としての売買に特化しています。
通貨の取引データ以外は、ブロックチェーンに記録できないようになっています。
そしてETHは、あらゆる契約に関する情報を、DAppsを通してスマートコントラクトで自動執行できるようになっています。
仮想通貨としてのETHは、このスマートコントラクトを実行する時のgas(燃料・手数料)として使われるのが主な目的です。
ですので、XRPやBTCと比較して、通貨としての価値が直接的に見えない(見え難い)一面を持っています。
そこでまず、ETHの通貨としての側面に目を向けてみたいと思います。
Ethereumの発行枚数について

法廷通貨は通常、その国の中央銀行が発行します。
日本であれば日本銀行が紙幣、貨幣を発行しています。
その証しとして、日本の紙幣であれば『日本銀行券』と印刷されています。
そして各国の通貨の発行枚数は、その国の都合で決めることが出来ます。
国の景気を良くするためには、多くのお金を市場に流通させる必要があります。
このように景気回復を図りたい時は、市場の動向を見て通貨の供給量を増やします。
と同時に金利を引き下げる等の政策を採って、市場に資金が流れ易い状況を作り、市場を活性化させるのです。
逆に、景気の動向を少し抑えたい時は、通貨の供給量を絞って市場を落ち着かせると同時に、金利を引き上げる等の政策を採る場合がほとんどです。
このように、法定通貨は各国の経済状況を見極めた上で、その発行枚数が決められています。
ただ、経済政策を誤ったり、外交政策での失敗があると、韓国のようにIMF(国際通貨基金)から警告を発せられたり、ベネズエラのようなハイパーインフレに陥ったりするのです。
一方、法定通貨に対して仮想通貨は、総発行枚数が決まっているデフレ通貨と、総発行枚数が決まっていないインフレ通貨に分かれます。
先述のBTCやXRPは、総発行枚数が決まったデフレ通貨で、ETHは総発行枚数が決まっていないインフレ通貨です。
以下に主要コインがどちらなのかと、総発行枚数を表にしましたので参考にしてください。
デフレ通貨
| コイン名称 | 総発行枚数(単位) |
| Bitcoin | 21,000,000 BTC |
| Ripple | 100,000,000,000 XRP |
| NEM | 8,999,999,999 XEM |
| Cardano | 45,000,000,000 ADA |
| Litecoin | 84,000,000 LTC |
| IOTA | 2,779,530,283 MIOTA |
| DASH | 18,900,000 DASH |
| EOS | 1,000,000,000 EOS |
| MonaCoin | 105,120,000 MONA |
インフレ通貨(発行枚数は現在値)
| コイン名称 | 総発行枚数(単位) |
| Ethereum | 97,000,000 ETH |
| Stellar | 100,000,000,000 XLM |
| Monero | 15,557,374 XMR |
| Lisk | 116,607,088 LSK |
デフレ通貨とインフレ通貨の違い
表の前で、BTCやXRPは、総発行枚数が決まったデフレ通貨で、ETHは総発行枚数が決まっていないインフレ通貨であるとお伝えしました。
なぜこの違いがあるのでしょうか?
基本的に、仮想通貨は使われることでその価値が高まります。
この流れはBTCが特に顕著です。
はじめは10,000枚がピザ2枚と交換される価値しか持たなかったBTCは、現在4,000ドル近い価値を持っています。
総発行枚数に制限があれば、使う人が増えれば増えるほど、皆が欲しがるわけですから、価値は上昇します。
発行枚数の制限があるのは、価値が下がってしまうインフレは起こらないというメリットが生まれるのです。
ただし、発行枚数に制限があるということは、マイナーへの報酬が無くなってしまうというデメリットも存在します。
マイナーの報酬がなくなってしまったら、マイニングする人がいなくなってしまいます。
マイニングされないということは、取引が承認されなくなるということになるので、マイナーの報酬がなくなるというのは、非常に大きな問題なのです。
ただ、BTCの総発行枚数2,100万枚が全て発行されるのは、約100年後の2140年と予測されており、まだまだ先の話ではあるのです。
一方同じデフレ通貨であるXRPは、もう既に総発行枚数を発行済みだと言われています。
ただ、総発行枚数全てが市場に流通しているわけではなく、総発行数の40%をリップル社が保管しているそうです。
内容が不確かなのは、リップル社からの正式な発表の有無に関係なく、その事実を確かめようがないからです。
対して、インフレ通貨であるETHはどうでしょうか。
発行枚数に制限が無いということは、通貨は発行され続け、価値は毎年下がっていくことになります。
ですが、法定通貨と同じように、市場価値を下げないようにコントロールできれば発行し続けることに問題はありません。
発行枚数の調整をハッシュレートやマイニングの難易度で調整するのは難しいでしょうが、一定の効果は期待できそうです。
また、通貨を発行し続けるということは、マイニング報酬はなくならないということでもあります。
ETHは、前回のハードフォークアップグレード(Constantinople)でマイニング報酬を減額(3ETH⇒2ETH)していますし、次のハードフォークアップグレード(Serenity)でマイニング方式をPoWからPoSに変更することを発表しています。
こうした方向性も、将来を見据えてのことだと思われます。
デフレ通貨とインフレ通貨はどちらが優れているというものではなく、それぞれの特性に合わせて、その方式を選んでいると考えた方が正しいと思われます。
BTCは通貨として使われることにその目的があります。
だから使い続けられるように、発行枚数に制限をかけたデフレ通貨になっています。
一方のETHは基本的に、スマートコントラクトのgas代(燃料費)に位置づけられており、そこで使われることが前提になります。
ETHの価値が上がりすぎて、それに吊られてスマートコントラクトのgas代が上がってしまっても困るわけです。
今ETHを持っている人や企業は良いですが、新規参入の人や企業に対してETHの価値が上がりすぎていたら、それは参入障壁になりかねません。
その意味からも、ETHはインフレ通貨方式を選んだのだと思われます。
通貨としてのEthereumの価値

下のグラフはCoinMarketCapのEthereumのチャートです。

今、Ethereumの価格は140ドル(15,400円)前後です。
この価格は、バブル期最高値(約1,390ドル:約153,000円)の1/10であり、The DAO事件が起きる前(約390ドル:約430,000円)と比較しても、1/3に落ち込んでいます。
事実、Ethereumの歴史を振り返ると、様々な問題にぶつかっているのが分かります。
前回もお伝えした『The DAO』事件(364万ETH:65億円)もそうですし、2017年11月には『My Ether Wallet』のParityのバグで95万ETH(2億7550万ドル:300億円)が凍結してしまったこともありました。
被害額で見ても、2018年1月に起こったNEMクラッキングによるコインチェック事件の被害総額580億円の半分以上に相当します。
普通の企業がこれだけの問題を起していたら、かなり厳しい経営状態に陥っていても何の不思議もありません。
ですが、Ethereumは生き残っています。それどころかそのプラットフォーム上には、他のブロックチェーンを圧倒するだけのDAppsが存在し、稼動し続けているのです。
そして今、Ethereumのプラットフォーム上では、新たな試みが始まっています。
その中でも特徴的なのが以下の3点です。
- DEX(分散型取引所)
- DAI(ETHプール型ステーブルコイン)
- DeFi(分散型金融)
DEX(分散型取引所)

DEX(Decentralized EXchange)とは分散型取引所のことです。
先日、世界最大級の取引所であるBinanceがBinance DEXをローンチして話題になりました。
(Binance DEXを詳しく知りたい方は、リンクをクリックしてください。)
今のBinanceやHuobi、Coinbaseなどの取引所は、すべて中央集権型の取引所です。
中央集権型取引所とDEX(分散型取引所)の違いは以下のようになります。
| 項目 | 中央集権型取引所 | 分散型取引所 (DEX) |
| 管理者 | 運営する企業・団体 | 顧客 |
| 顧客の資産管理 | 取引所 | 顧客 |
| 秘密鍵の管理 | 取引所 | 顧客 |
| 基軸通貨 | 法定通貨・仮想通貨 | プラットフォーム上のトークン |
| 取引手数料 | 取引額により変動する | スマートコントラクトのgas代 |
| 登録 | 個人情報が必要 | DEX参加のアドレスは必要(個人情報は不要) |
これまでに起こったGOX(クラッキング事件)は、そのほとんどが取引所を狙ったものです。
仮想通貨という分散型ネットワークの中で、取引が集中する取引所は、中央集権的な場所であるため、どうしても狙われてしまいます。
GOXを避けるために取引所は、高度なセキュリティを準備する必要があるわけですが、クラッカー達の手口は日に日に巧妙になり、イタチごっこになっています。
そこで、クラッキング耐性がある分散型ネットワークと同じように、取引の場所は提供するが、資産の管理は個人で行うようにしたのが、DEX(分散型取引所)です。
『取引の板だけが、インターネット(ネットワーク上)にある』という感じなのですが、具体的なイメージはし難いと思います。
DEXにはこのセキュリティ面以外にもメリットがあります。
- トラストレスである
- 国の規制に縛られない
- システム破綻がない
- 取引所側の不正がない
「トラストレスである」
この『トラストレス』とは、『第三者を信用する必要がない』という意味です。
例えば取引所を選ぶ時、その取引所を信用できなければ契約を結ぶことはありません。
あなたが今使われている取引所も、何らかの理由があってそこを選ばれたはずです。
その理由は、インターネットからの情報だったり、コミュニティからの情報だったり、誰か信用がおける人のオススメだったり、人によって様々です。
でも、そのどれもが「第三者を信用して契約を結んでいる」のです。
対して『トラストレス』は、この「第三者を信用する必要がない」仕組みができているので、「誰かを信用する」というコストをかけなくても済むのです。
国の規制に縛られない
DEXはネットワーク上には存在しますが、現実の取引所として何処かの国に存在するわけではありません。
つまり何処かの国の規制(法律)に縛られないと言えます。
Binanceが中国当局の規制を嫌い、本社を香港からマルタに移転させました。
また日本の金融庁は、日本人の海外取引所への登録を規制しようとしています。
でもDEXであれば、その国に属しているわけではありませんので、各国の規制に縛られることはありません。
システム破綻がない
これはセキュリティに属する部分もありますが、中央集権型の取引所は、システムメンテナンスが必要です。
メンテナンスを行うためには、システムを止める必要があります。
また、クラッキングされた時などは、資金流出を避けるために、システムを停止させる必要があります。
事実、香港を拠点とする取引所『BitMEX』のメンテナンス明けを狙った、BTCの価格操作があったと報じられたことがあります。
DEXは何度もお伝えしているように、ETHやBTCと同じように、ネットワーク上に分散しています。
ですので、不正を防げるだけでなく、システムを支える全てのノードが一斉に止まることはあり得ないので、メンテナンスのための停止が必要なくなるのです。
取引所側の不正がない
こちらもセキュリティに属する一面ですが、取引所の対応に不正がないとは言えません。
実際にクラッキングの原因の一つに、内部クラッキングがあるのです。
内部クラッキングとは、一部の社員がその権限を利用して顧客の資金を着服することです。
事実、有名なMt.GOX事件は、内部監査員のPasswordをクラッカーが入手したことで起こっており、その流出経路から内部犯行が疑われた経緯もある(※1)ほどです。
「Mt.GOX」の元代表マルク・カルプレス被告(33)=フランス・イスラエル国籍=の判決が15日、東京地裁で出た。
内部犯行が疑われた、顧客資金の着服に関する業務上横領罪は無罪となったが、自社システムに架空の入金データを記録した私電磁的記録不正作出・同供用罪で懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役10年)を言い渡された。
DEXは、その取引をスマートコントラクトとDAppsによって自動的に契約し、ブロックチェーンに記録を行いますので、不正が入る余地がないのです。
これらの理由から、DEXはかなり注目されています。
DAI(ETHプール型ステーブルコイン)

次の注目はDAI(ETHプール型ステーブルコイン)です。
Maker DAOは、ETHを一定量プールして担保(市場への裏付資産)としながらDAI(ステーブルコイン)を発行し、運用するプロジェクトです。
ステーブルコインは、法定通貨の価値とペッグ(連動)することで、仮想通貨特有の価格変動から切り離し、取引きをしやすくした仮想通貨です。
しかもこのDAIは個人で発行することもできるので、ETHプール分の元手だけでDAIを発行して資産運用することが可能なのです。
つまりETHを減らすことなく、DAIを発行して資産運用が可能になるということです。
これは極論ですが、スマートコントラクトのgas代としてのみ使われていたETHが、通貨としての価値もあると認識されたということでもあります。
実際に、ETHは上場して仮想通貨として運用はされていますが、その価値はBTCには遠く及んでいません。
DAIはETHの価格変動によって、プール量は変動させる必要がありますが、基本的にトラストレス(第三者の信用が不要)です。
USDT(テザー)やTUSD(トゥルーユーエスディー)、GUSD(ジェミニ・ダラー)のように、第三者を信用する必要がないのです。
つまりDAIは非常に信用に足るステーブルコインということができるのです。
それに加えてDAIは、スマートコントラクトに組み込まれた自動価格設定によって1DAI ≒ 1ドルが維持されます。
これは他のステーブルコインと違い、価格を維持するためのコストが必要ないということです。
DAIは他のERC20トークンのように自由に取引することができますし、DEXでの取引も可能になります。
市場ではまだ、DAIの価値は認められていません。
それは流通量を見ればわかります。
ですが、今後USDTよりもDAIが信頼されることになれば、ETHの価値はより一層上がることになります。
DeFi(分散型金融)

そして最後に、DeFi(分散型金融)です。
DeFiとは(Decentralized Finance platforms)の略で、ディファイと読みます。
DeFi(分散型金融)とは、ブロックチェーンを用いた、透明性が高く、また誰もがアクセス可能で、しかもトラストレスな金融プラットフォームの構築を意味します。
従来の金融システムは、中央集権的で非常に閉鎖的であり、遺産的だと言えます。
銀行を中心とした中央集権的な間接金融システムは、19世紀頃より始まり、わが国においては明治維新以降、政府が中心となって作られたシステムです。
それ以後、敗戦による財閥解体。
高度経済成長に合わせた組織変更。
IT革命による技術革新。
バブル崩壊による銀行の統廃合などなど。
時代の流れによって金融システムも変化してきましたが、それは銀行という組織の変化のみでした。
銀行を中心とした中央集権的な間接金融システムそのものは、変化していません。
DeFiは、この『銀行を中心とした中央集権的な間接金融システム』からの脱却だと考えていただくのが良いと思います。
ただDeFiは、未だ概念的・抽象的な部分が多く、具体的な説明が難しい分野でもあります。
繰り返しになりますが、DeFiが目指すのは、トラストレスなブロックチェーンを用いた、透明性が高く、誰もがアクセス可能な、金融プラットフォームの構築です。
透明性が高いとは、従来の金融システム的な不透明で閉鎖的なシステムではなく、個々のプライバシーが保護された上で情報が公開されている状態が前提です。
例えるなら、ブロックチェーンに記載されている個人情報が、プライバシー保護されている状態といえるでしょう。
誰もがアクセス可能とは、保護され公開されている情報に、インターネット接続されている環境であれば、ボーダレスに誰もがアクセスでき、自由に取引できる状態を言います。
プラットフォーム間で相互運用できるようになれば、ミドルウェアプロトコルを活用した新たなDAppsが生まれ、従来の不透明で閉鎖的な金融業界にイノベーションが起きることが期待されています。
このような条件を満たすには、各金融機関が現在活用しようとしているプラベートチェーンによるイノベーション(例えるならJPモルガンのJPMステーブルコイン)ではなく、パブリックチェーンによるイノベーションを目指していることが伺えます。
上記の条件を踏まえて、DeFi構築の条件をまとめると以下のようになると思われます。
- プロジェクトはパブリックブロックチェーン上に構築される。
- プロジェクトは金融産業である。
- プロジェクトのコードはオープンソースである。
- プロジェクトは堅牢な開発者コミュニティを持っている。
この上記の4条件を全てクリアできる組織は、Ethereumコミュニティ以外にはありえないでしょう。
唯一の問題は、金融知識を持ったビジネスサイドの人間を巻き込むことですが、Ethereumには、Fintech分野に長く携わってきた、ジョセフ・ルービン氏がいます。
ルービン氏は、ニューヨークに立ち上げたFintech企業ConsenSysのCEOを務めており、Ethereumの金融担当ともいえる人物です。
そこにEthereumの強みである、Web3.0の実現に向けた開発コミュニティが加われば、DeFiプロジェクトは大きく前進することでしょう。
Ethereumブロックチェーンのプラットフォーム上で始まっている新たな取組みの数々。
そのどれもが、新たな金融市場を構築する取組みです。
- DEX(分散型取引所)
- DAI(ETHプール型ステーブルコイン)
- DeFi(分散型金融)
この全プロジェクトおいて利用されている仮想通貨は、ETHです。
DEXと、DeFiではgas代として、DAIでは担保として、ETHが常に使われることになります。
この新たな取組みは既に動き出しており、DEXとDAIは実用レベルまで来ています。
つまり、この新しい取組みが形になればなるほど、ETHの使用量・流通量は増えることになり、その価値は増大することになるのです。

以上のことから、ETHを投資対象として見た時、DEX・DAI・DeFiの市場が広がれば広がるほど、ETHの価値が増大することになります。
あくまでも、DEX・DAI・DeFiの市場が広がればという条件付ではありますが、ETHの価値が大きくなる可能性は十分にあります。
この記事でお伝えしたいのは、将来的な可能性があるということであり、ETHの値上がりを保証できるわけではありません。
特にショートでの値上がりは、すぐには見込めないでしょうし、その動きを示す材料もありません。
ですが、ETHのプロジェクトで大きな動きがあり、それが市場に受け入れられた時、一気に値段が動く可能性は低くないであろうと考えられます。
今後しばらく、Ethereumの動きを注視されてみてはいかがでしょうか。
DEXを体験してみたいと思われた人は、EtherDelta取引所への登録をおすすめします。
イーサリアムプラットフォームを採用している分散型取引所(DEX(※2))です。
イーサリアムブロックチェーン上のトークン(ERC20トークン)は全てここで取引可能です。
基軸通貨はETHです。ETH以外のトークン対トークンでも取引可能です。
引用:coinpost
また、ETHを手に入れたい。
国内の取引所でETHの取引をしてみたいという方には、こちらをお勧めします。
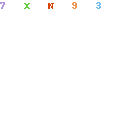
国内の取引所の場合、ETHを取り扱ってはいても、販売のみの取引所があります。
今回お勧めするbitbankは、ETHの取引ができる国内の取引所になります。
仮想通貨のインフラを牽引するEthereum

ここまでEthereumの将来性と、今後の市場価格についての考察を重ねてきました。
ETHは価値が下がり続ける、そう発行枚数に制限のないインフレ通貨であり、また『The DAO』事件をはじめとする様々な問題に直面しながらも成長を続けてきました。
今も、先の章で取り上げた【DEX】・【DAI】・【DeFi】のように、Ethereumのプラットフォーム上では、数多のプロジェクトやDAppsが開発され続けています。
改めて振り返ってみると、Ethereumという仮想通貨は、他の仮想通貨と比べて明らかに違う一面を持っています。
それは単に、スマートコントラクトを備えたブロックチェーンを、世界で初めて公開しただけではないように思えるのです。
このEthereumの独自性を解く鍵は、Ethereumの歴史が始まってすぐに起こった、ヴィタリック氏とホスキンソン氏の対立にあるような気がします。
分散性を優先したいヴィタリック氏と、収益性を優先したいホスキンソン氏が対立。
結果としてEthereumは分散性を選択し、開発力とプラットフォームを市場に提供し続けることに注力して、その代価として市場の信頼を手に入れました。
以前お伝えした開発者の数が、Bitcoinの2倍以上であるというEthereumの開発環境こそ、分散性にこだわったヴィタリック氏の目指したところだったのではないでしょうか。

その時ケンカ別れしたホスキンソン氏も、結局は開発に力を注いでおり、CardanoはBitcoinに次ぐ開発者数を誇っています。
分散性が全てを解決するために必要な環境だとは思いませんが、中央集権的組織に縛られない開発環境こそが、Ethereumの独自性を保っている要素だと言えるでしょう。
ITバブルとICOバブルが似ていることを示して、将来的に仮想通貨の価格はICOバブルのピーク時を超えると言われていますが、その意見には同意できます。
ですが、何が足りないのかを明確に指し示しているところはほとんどありません。
それは当然だと思います。
仮想通貨が一般に使われるようになるためには、何が足りないのかがまだ分からないからです。
それはインターネットの時もそうでした。
インターネットも一般に普及するまで、約20年の年月が必要でした。
そしてそのほとんどが、インフラ整備に費やされてきたのです。
以下のグラフは、インターネットバブル期の推移を示したナスダックのグラフですが、そこにインフラ整備を書き加えてみました。

インターネットに接続するためのインフラ整備は、まず電話回線を利用したものから始まりました。
最初に電話回線を資料した通信速度は、28.8kbpsでした。
その後、ISDN(64kbps:キロビーピーエス)が1995年頃から普及し始めています。
64kbpsがどのような感じかというと、ホームページに貼ってある写真を読み込むために、30秒程度待たなければならないというレベルでした。
1999年になると、Yahoo!ジャパンがYahoo!BBというADSL(mbps:メガビーピーエス)のセールを開始したこともあって、一気に普及しました。
そして2003年頃から光通信(gbps:ギガビーピーエス)へとネットの接続環境は進化し続けてきたのです。
時期を同じく普及したのが、携帯電話とWi-Fiです。
Wi-Fiは2003年頃から無線LANとともに普及し始め、2009年からは、初期ADSLと同等レベルの通信速度になりました。
そして2015年頃から、ほぼ今と同じ通信速度が可能になり、フリーWi-Fiの施設も増えてきたのです。
携帯電話も同様に、2003年頃には普及率が90%を超えました。
ただこのころの携帯電話では、処理能力の不足から、インターネットの世界に直接触れられていたのではなく、携帯電話用サイトを利用していたのが実情です。
携帯端末がインターネットの世界にアプロートできるようになったのは、iPhoneの発売からです。
iPhoneの発売は2007年で、iOSに名称が変わったのが2010年になります。
AndroidOSも発売開始は2007年でした。
そしてスマートフォンが携帯電話を抑えて、シェア7割超になったのは2015年になります。
パソコンから携帯電話へ、そしてスマホへと、それぞれのインフラが整備され、その度にインターネットに触れるユーザーは増え続けてきました。
インフラ整備と機器の整備。その両方が成り立たなければ、今のインターネットはなかったと言えます。
同じことが仮想通貨にも言えます。
多くの人が、仮想通貨を投機的な側面でしかものを見ていません。
ニュースを賑わすのも、金融関係者の発言だったり、今後の投機的な動きの発言ばかりです。
確かにそれも大事でしょうが、それ以上に大事なのは、一般の人たちが法定通貨やキャッシュカードを使うのと同じように、仮想通貨を使えるようになるインフラです。
そのインフラ整備にはまだまだ時間がかかると思います。
そして仮想通貨が本来の意味を発揮するのは、そのインフラ整備が整ってからでしょう。
ですがその時はもう、投機・投資的旨味は無くなっているでしょうけれど。
この『仮想通貨を一般の人が普通に使えるようになるインフラ整備』を、今担っているのが、Ethereumです。
インターネットが一般に普及するためには、各端末の通信速度という、まだ見え易い要素がありました。
しかし、仮想通貨のインフラというのが、インターネットの何に当たるのかはまだ分かっていません。
ただ一つ言えるのは、そのインフラベースとなるものが試されるプラットフォームは、Ethereumのプラットフォームであると断言しても問題はないと思います。
なぜなら、Ethereumのブロックチェーンプラットフォームには、他にはない開発力があるからです。
ヴィタリック氏が何よりも優先させたかった『分散性』は、他に類を見ない開発力をEthereumにもたらしました。
それがEthereumの特徴であるとともに、最大の武器だと断言できると思います。
まとめ

インターネットが、一部の研究者のものから一般人が手にするようになって、その本質が現れるまでに20年以上掛かりました。
インターネットバブルがはじけて、今の状態になるまでに約20年の年月が必要でした。
その結果としてGAFAのような企業が出てくるなどということは、誰も想像できませんでした。
同じように、仮想通貨が一般に広がるためのは、時間とインフラ整備が必要で、それができるプラットフォームは、Ethereumを置いて他にはないということになります。
そして仮想通貨が一般に使われるようになった時、どんな企業が現れているかは全く未知の世界だと言っても過言ではありません。
何より仮想通貨はまだ、本来の使われ方がわかっていない部分があります。
本来の使い方は、今はまだ誰にも分からないのかも知れません。
ですがその方向性を探り、仮想通貨のインフラ整備を行うのが、Ethereumのブロックチェーンとスマートコントラクトになるのは間違いないと考えています。
一つ言えるとしたら、DAppsの進化は今後、ユーザーインターフェイス(UI/UX)の使いやすさがメイン進化の方向性になるだろうと予想します。
より使い易いUI/UXを備えたDAppsが生き残っていくと思われます。
逆に、今の仮想通貨は投機的な注目度が高すぎて、本来の姿が見えにくくなっている一面もあります。
個人的には、投資に関して現在はショートではまるで考えていません。
ショート的な材料はほとんどないに等しいですし、実際にプロの投資家たちが様々な予想を立てていますが、そのほとんどが外れています。
なんどもお伝えしていますが、インフラ整備が整わなければ、市場価格の上昇もあり得ないのです。
それはインターネットと同じです。
つまらないかも知れませんが、もっともっと全体的な視点と、長期的な視点が必要だと思っています。
前回の特集で、データに通貨(モノ)としての価値を与えたBitcoin。
そしてデータに契約(コト)としての価値を与えたEthereumという内容をお伝えしました。
この方向性が違う2つの仮想通貨は、今後の仮想通貨社会を牽引する2大通貨となることは間違いありません。
そしてその中から生まれてくる、真にイノベーティブなものを探すことが大事です。
本当にイノベーティブであると感じたのならば、思い切って賭けてみるのも一つの投資だと思います。
筆者はETHは仮想通貨のもう一つの正常進化形態であると考えています。
BTCがサトシナカモト氏が示した方向に、常に進化を続けているように、ETHもヴィタリック氏が示す方向に、進化し続けているのです。
Ethereumをリサーチすればするほど、その独自の魅力に引き込まれていきそうな感じがします。
DAppsも、DEXも、DAIも、DeFiも始まりは全てEthereumから始まっています。
しかも、すでに様々な開発者ツールやライブラリがあり、多くのアプリケーションやミドルウェアが存在しています。
そこから獲得できるネットワーク効果は計り知れないものがあると思います。
何より、ETHが多数の取引所に上場していて、市場の信頼を得ていることは大きなバックボーンになります。
中でもDAIに代表される、ETHをスマートコントラクトの流動性プールに担保する形での経済圏の拡大という新たな試みは、Ethereumの新たな可能性を開くものです。
この後、PoSへと移行するハードフォークアップグレードのSerenityもあります。
Ethereumが開く新たな未来は、まだまだこれからだと感じています。
ただ、これらのトピックは市場では余り議論されていません。
逆にここに新たな投資機会があるのではないかと思えるほどですが、あなたはどのようにお感じになられたでしょうか。
『Ethereumの将来性と価格はこれからどうなる』と題してここまで記事を書いて参りました。







































