
仮想通貨ATMは、元々仮想通貨が今後普及することを先取りし、メンバーを募って販売網を広げる手法の中で生まれました。
現在では金融庁による規制の元、仮想通貨取引に仮想通貨交換業者としての登録が必要となったため、仮想通貨ATMが下火になりました。
それでも海外では、仮想通貨ATMは飛躍的に普及している実態があります。
ここでは仮想通貨ATMの国内及び海外での状況、さらには今後の日本での可能性について触れていきますので、今後の仮想通貨ATMの普及の可能性について参考にして下さいね。
仮想通貨ATMと普通のATMとの違い

仮想通貨ATMとは、ビットコイン等の仮想通貨の売買がATM機械を通して行われるもので、ATMの外観は通常のATMと比べて多少異なることはありますが、基本的には変わりません。
その為、無人の機械を通して仮想通貨を購入、売却する取引が行われる形をとっています。
強いて違いを挙げれば、普通のATMが法定通貨をベースとした電子上の信用取引に対して、仮想通貨ATMは、取引所の代わりに仮想通貨の売買を行うことです。
また仮想通貨ATMでは、スマホ及びスマホ上でやり取りできるモバイルウォレットが必要になります。
- 普通のATM:法定通貨での信用取引
- 仮想通貨ATM:仮想通貨の売買(モバイルウォレットが必要)
仮想通貨ATMの仕組みは権利収入でビットコインが手に入るって本当?

一時期、仮想通貨ATMの普及に関わることで、権利収入を得られるという話がありました。
株式会社ビットマスターが、ビットコインを広めるべく日本でビジネスパートナーを広く募集しており、その中にビットコインATMを普及させるべくメンバーを募っていたということです。
元々は株式会社BMEXというビットコイン取引所が、ビットコインATMであるBTMを開発(いわゆる自動販売機)していました。
そしてBTMを広めるに当たってビットマスターがメンバーを募り、メンバーがBTMを販売したり設置したりすることで、BTMの設置権利収入として、BTMの手数料から配当される仕組みがうたわれていました。
ビットマスターは、今後ビットコインが流行った場合に、BTMを数多く販売することで、将来はBTM手数料だけで莫大な利益が生み出されることがメンバーを募る際に大々的にアピール。
しかし、メンバーになるためには株式会社BMEXにお金を支払う必要があることや、設置権利収入のあり方が不明瞭であることが明らかに。
そして、設置権利収入自体は会社全体の売上の1割の中から、ピラミッド式に構成されているメンバーのレベル毎に配布する割合が決められており、
実際の収入の算出結果が個々の会員にとっては不透明なものになっていました。
さらには、金融庁により、国内での仮想通貨の取扱には、仮想通貨交換業の登録が必須となったために、数多くのBTMが営業を停止。
結果的に、ビットマスターの後ろ盾となっていた株式会社BMEXの業務停止・改善命令から、仮想通貨交換業の登録申請を取り下げることになり、事実上ビットマスターによる普及の動きも停止。
株式会社BMEXに対する行政処分について
1. 株式会社BMEX(本店:鹿児島県鹿児島市、法人番号 2040001085893 、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、法第63 条の15 第1項の規定に基づき、平成29年12月26日(火曜日)に当社の業務の状況等に関する報告徴求命令、平成30年2月1日(木曜日)にシステムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、3月5日(月曜日)に金融庁において立入検査に着手した。
BTMそのものが完全になくなったわけではないですが、2017年10月の資金決済法の改正により、BTMは金融庁に認可された仮想通貨交換業者よる直接の取扱となったのです。
仮想通貨ATMを利用した際の税金について

仮想通貨設置が仮想通貨交換業者に限定されたため、設置に一般の人が関わることがなくなりましたが、仮想通貨ATMの設置や利用など、ATMに特化した税金はありません。
しかし、仮想通貨ATMを利用することで、仮想通貨の売買を行った結果、利益が確定された場合に雑所得として金額に応じて税金が発生します。
海外で広まる仮想通貨ATMの利便性

日本国内では規制強化により仮想通貨ATMが下火になっていますが、海外では反対に仮想通貨ATMが広まりつつあります。
その理由として一番大きく考えられることは、法定通貨に対する信用といえるでしょう。
日本では円の信用は絶対です。
お札の印刷精度も世界一を誇り偽造そのものが不可能な域にあります。
それゆえ日本では仮想通貨も、日本円という絶対的存在価値と交換可能という信用の上に成り立っています。
それに対して海外では、国によって自国の法定通貨に対する信用が日本ほどではない場合が非常に多いのです。
典型的な例では中国の法定通貨でしょう。
中国では紙幣の偽造が蔓延しており、普段のお金のやり取りで紙幣が使われることはまずありません。
金融機関の中で流通する紙幣ですら信用はありません。
よって、法定通貨ベースの電子決済が早くから普及しています。
このように法定通貨の信用が弱い国では、仮想通貨に対して早くから決済の役割を求めており、今後もその傾向は続くでしょう。
特に商取引において自国の法定通貨よりも、仮想通貨による取引が求められ、結果として手軽に利用できる仮想通貨ATMがその後押しをする動きとなるはずです。
仮想通貨ATMは東京オリンピックを境に普及していくのか?
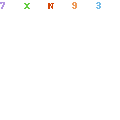
出典:Area.bot
日本では依然として仮想通貨ATMが鳴りを潜めていますが、今後東京オリンピックによって海外から人やモノ、カネの流れが入ってきたときに仮想通貨の役割は無視できないものとなるでしょう。
日本ではまだ日本円の現金によるやりとりが主流なため、海外から来た人もモノやサービスを購入する上で日本円を必要とする場合も多くなります。
そのような中で仮想通貨は日本円を得る上で絶大な効果を発揮するのです。
東京オリンピックでは、様々な国から選手団及びサポーターが来日する中、それぞれの国の法定通貨をあらかじめ仮想通貨として所持しておき、
日本の仮想通貨ATMから引き出すことで、日本円を取得できます。
銀行の為替業務と異なり、仮想通貨ATMでは24時間365日稼働するため、仮想通貨ATMに対するニーズは必然的に増えていきます。
現状では、金融庁による規制が厳しい中でも、仮想通貨ATMを導入する取引所は増えることでしょう。
場合によっては銀行が参入し、既存のATMに仮想通貨に対応する機能を付加することで、対処することも考えられます。
フィリピン最大の銀行が仮想通貨ATMサービスを開始
フィリピン最大の銀行としてしられるユニオンバンク・オブ・フィリピン(以下ユニオンバンク)が、サンドボックス制度の一環として、
国内で初となる仮想通貨ATMを開始することが発表されました。
ユニオンバンクは次のような声明を発表しています。
仮想通貨を利用するユーザーのニーズや嗜好に応えるため、我々銀行は継続的な探求を行っております。
その探求の中で、仮想通貨ATMはペソを仮想通貨に、またはその逆に変換するプラットフォームを提供します
ユニオンバンクが展開するのは、フィリピンの中央銀行が定める規制に遵守した双方向仮想通貨自動現金自動預け払い機(ATM)です。
フィリピン政府は、ユニオンバンクがBangko Sentral ng Pilipinas(BSP)と継続的に協力することを条件に、すべての規制に沿った仮想通貨ATMの提供を許可したといいます。
まとめ
仮想通貨ATMは、日本国内では、規制強化の元、仮想通貨交換業者としての登録が必須となったため、普及に歯止めがかかっていますが、海外ではむしろ飛躍的に広まっています。
これは今後において法定通貨に匹敵する役割を仮想通貨が担う前兆であり、東京オリンピックを迎える日本国内においては、ますます仮想通貨取引のニーズが求められます。
取引所を介することなく日本円との交換が可能な仮想通貨ATMが飛躍的に広まることは確実といえるでしょう。






































