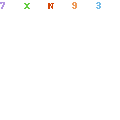
2018年1月に発生し、世の中に衝撃を与えたCoincheck(コインチェック)不正送金事件。
仮想通貨のNEM(XEM)が当時のレート換算で約580億円流出し世の中やメディアを賑わせました。
経済制裁を逃れるために北朝鮮が関与していたなどの報道もありますが流出したことは事実。
その後、金融庁の立ち入り調査や、財務省からの業務改善命令が出され、仮想通貨界への規制が厳しくなるきっかけとなりました。
金融庁による規制が厳しくなったと言われている仮想通貨界ですが、具体的にはどのようなガイドラインが設けられているのか、それをクリアしたホワイトリスト・登録業者は一体どこなのかをお届けします。
仮想通貨取引所の利用の際に参考にしていただけると幸いです。
この記事の目次
金融庁による仮想通貨交換業の定義とは

2018年はコインチェックの不正送金に始まり金融庁による取り締まりが一気に厳しくなった仮想通貨界。
2017年4月に施行された改正資金決済法により仮想通貨と法定通貨の交換事業をするには金融庁への登録が必要となりました。
これによって仮想通貨取引所を運営する会社は金融庁へ届出を提出することに。
金融庁からの登録許可が降りた業者を「登録業者」、施行以前から事業を行っており、金融庁に申請をしていれば仮想通貨交換業者とみなし、登録前の状態でも今まで通り事業を継続できる「みなし業者」という分かれ方をしています。
この仮想通貨交換業者とみなし業者を分ける定義はどのようになっているのでしょうか。
金融庁が発表している資料を元に、金融庁がどのような部分に着眼しているのかを見ていきます。
経営管理
仮想通貨取引所を経営していくに当たって守るべきことが記載されています。
- 財産の保護に努めているか
- 法令等を遵守するために、内部管理や内部監査部門の機能強化がされているか
- 経営陣は、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断し排除していくこと
これらについて詳しく書かれています。
これは仮想通貨を取り扱う会社だからというわけではなく、世の中の会社全てに言えることをしっかり守っている必要があるという基準が示されています。
反社会勢力との繋がりは持たない健全な経営をしていることが定義づけられています。
業務の適切性
この項目については細分化されており、コンプライアンス(法令遵守)やマネーロンダリング(資金洗浄)やテロへの対策、反社会的勢力による被害の防止、不祥事件に対する監督上の対応などの基準について記載されています。
どういう定義がされているのかもう少し細かく見ておきましょう。
コンプライアンス(法令遵守)
仮想通貨交換業者が法令や社内規則等を厳格に遵守し、適正かつ確実な業務運営に努めることは、利用者の仮想通貨交換業に対する信頼を向上させることになり、ひいては仮想通貨の更なる流通・発展を通じた利用者利便の向上という観点から重要である。
このような記載がされています。
これも仮想通貨交換業だからというわけではありませんが、仮想通貨に関しては、コインチェック事件や仮想通貨取引所Zaifのハッキング被害など、信用に欠けるという印象が世の中では強い傾向にあります。
そのため、他の業種の会社以上にコンプライアンスに重点をおく必要も。
業界全体の健全な経営が、仮想通貨の流通に大きな影響を与えていくということが金融庁の見解です。
取引時確認等の措置
仮想通貨の取引時における確認事項を定義しています。
主には、マネーロンダリングやテロに資金を流出させてしまわないように「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に記載されている措置を的確に行うため態勢が整って機能しているかどうかというもの。
マネーロンダリングは、麻薬取引や脱税、粉飾決算などの犯罪によって得た資金(汚れたお金)を、架空の名義などを利用して送金を繰り返したりして資金の出所をわからなくすることです。
仮想通貨の中には、匿名性の高いものも存在し、マネーロンダリングやテロに活用されるのではという懸念が以前から上がっており、その懸念点を排除しているかどうかが判断基準のひとつとされています。
現在は仮想通貨取引所で新規口座開設をする場合、KYCの提出(個人認証)がありますが、これはちゃんと本人が取引を行おうとしているかの判断で「取引時確認等の措置」を実施しているためです。
反社会勢力による被害の防止
近時反社会的勢力の資金獲得活動が巧妙化しており、関係企業を使い通常の経済取引を装って巧みに取引関係を構築し、後々トラブルとなる事例も見られる。こうしたケースにおいては経営陣の断固たる対応、具体的な対応が必要である。
仮想通貨取引所の口座開設は基本的にはネット上で行われ、銀行のように対面形式で行うことはありません。
そのため誰でも口座開設を申し込むことは可能です。
仮想通貨取引所としては誰が口座開設や取引を行うかの確認を徹底する必要があるということですね。
不祥事件に対する監督上の対応
不祥事が起こってしまった際のことに関しても記載されています。
不祥事の発覚後の対応は適切かどうか、不祥事への経営陣の関与はないか、利用者に与える影響はどうか、再発防止のための改善策十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているかなど、コインチェック事件の時にはこの辺りが話題となりました。
利用者保護のための情報提供・相談機能
取引所を利用するユーザーが画面の指示に従って、正確な取引が行えるかどうかを定義しています。
仮想通貨の取引はインターネット上で行われるため、画面の操作や取引方法などが、サイトにしっかりと明示されているかも判断基準となります。
また、一部の取引所で取引可能なレバレッジ取引では、大きな損失を被る可能性があることを示しておかなくてはなりません。
そして、取引所を利用するユーザーが必ず関係してくる手数料についても明記する必要があります。
その他に事務運営に関してや障害者への対応、監督手法などについての定義が記されています。
金融庁が認める仮想通貨交換業登録業者一覧

前述しました金融庁による仮想通貨交換業者の定義や基準をクリアすると「仮想通貨交換業者」として登録されますが、国内の取引所ではどこが登録業者となっているのでしょうか。
| 登録番号 | 仮想通貨交換業者名 | 取り扱い通貨 |
| 関東財務局長第00001号 | 株式会社マネーパートナーズ | BTC |
| 関東財務局長第00002号 | QUOINE株式会社 | BTC、ETH、BCH、QASH、XRP |
| 関東財務局長第00003号 | 株式会社bitFlyer | BTC、ETH、ETC、LTC、BCH、MONA、LSK |
| 関東財務局長第00004号 | ビットバンク株式会社 | BTC、ETH、XRP、LTC、MONA、BCC |
| 関東財務局長第00005号 | SBIバーチャル・カレンシーズ株式会社 | BTC、ETH、XRP、BCH |
| 関東財務局長第00006号 | GMOコイン株式会社 | BTC、ETH、BCH、LTC、XRP |
| 関東財務局長第00007号 | ビットトレード株式会社 | BTC、ETH、XRP、LTC、MONA、BCC |
| 関東財務局長第00008号 | BTCボックス株式会社 | BTC、BCH、ETH、LTC |
| 関東財務局長第00009号 | 株式会社ビットポイントジャパン | BTC、ETH、XRP、LTC、BCC |
| 関東財務局長第00010号 | 株式会社DMM Bitcoin | BTC、ETH |
| 関東財務局長第00011号 | TaoTao株式会社 | BTC |
| 関東財務局長第00012号 | Bitgate株式会社 | BTC |
| 関東財務局長第00013号 | 株式会社BITOCEAN | BTC |
| 関東財務局長第00014号 | コインチェック株式会社 | BTC、ETH、ETC、LSK、FCT、XRP、XEM、LTC(、BCH |
| 近畿財務局長第00001号 | 株式会社フィスコ仮想通貨取引所 | BTC、MONA、FSCC、NCXC、CICC、BCH |
| 近畿財務局長第00002号 | テックビューロ株式会社 | BTC、MONA、BCH、XCP、ZAIF、BCY、SJCX、PEPECASH、FSCC、CICC、NCXC、Zen、XEM、ETH、CMS |
| 近畿財務局長第00003号 | 株式会社Xtheta | BTC、ETH、BCH、XRP、LTC、ETC、XEM、MONA、XCP |
関東地区で仮想通貨交換業者として登録されている企業は14社。
関西地区では3社となっています。
金融庁のホームページには以上のように記載されていますが、取り扱い通貨においては現在と違う部分もあります。
また、テックビューロ株式会社は仮想通貨取引所Zaifを運営していましたが、現在は株式会社フィスコが運営しているなど。
現在の取引所運営会社や取り扱い通貨については各仮想通貨取引所のホームページなどで確認を行いましょう。
また、表の中でBCHとBCCの記載がありますが、これはどちらもビットコインキャッシュのことを示しています。
金融庁が認める仮想通貨のホワイトリストとは

金融庁や仮想通貨について調べていると「ホワイトリスト」という言葉が出てきます。
ブラックリストは聞いたことがある人が多いと思いますが、ホワイトリストはその逆です。
ブラックリストは取引が停止されるリストですが、ホワイトリストは取引が許可されるリストで、別の表現をすればホワイトリストにないものは取引できないということになります。
このホワイトリストですが、金融庁によって取引が許可・認可されている仮想通貨の銘柄のことを指します。
ホワイトリストに登録されていない仮想通貨は取引ができませんので、現在仮想通貨取引所で取引されている通貨はホワイトリスト入りしているということになります。
ホワイトリストに登録されるには匿名性の通貨の審査が厳しくなり、一時Coincheckで取引がされていたZcash(ジーキャッシュ)やMonero(モネロ)が取引所から消えたのはその影響があったためと言われています。
では、どの仮想通貨がホワイトリスト入りしているのでしょうか。
ホワイトリスト入りしている通貨は次の通りです。
| ビットコイン(BTC) | リスク(LSK) |
| リップル(XRP) | フィスココイン(FSCC) |
| ライトコイン(LTC) | ネクスコイン(NCXC) |
| イーサリアム(ETH) | カイカコイン(CICC) |
| イーサリアムクラシック(ETC) | カウンターパーティー(XCP) |
| モナコイン(MONA) | ザイフ(ZAIF) |
| ビットコインキャッシュ(BCH) | コムサ(CMS) |
| ネム(XEM) | ビットクリスタル(BCY) |
| ストレージコインエックス(SJCX) | ぺぺキャッシュ(PEPECASH) |
| ゼン(ZEN) | キャッシュ(QASH) |
以上の20通貨となっています。
金融庁が今後許可する仮想通貨は

これまで20種類の仮想通貨が金融庁のホワイトリストに入っていますが、今後はどの通貨が登録されてくるのか注目を集めます。
ホワイトリストに登録されると、金融庁も認めた通貨という見方ができるため通貨に対する信頼があがることに。
反対に、認められていないと日本国内では信頼が低いという見方ができます。
匿名性のある通貨は、マネロンやテロに加担する恐れがあったり審査が厳しいこともあって今後国内の取引所で扱われる可能性は低いでしょう。
これから取引所で扱われるものは一定の信頼度があると判断できるため、需要の増加や価格の上昇に繋がるかもしれません。
これまでもbitFlyetにリスク(LSK)が上場した時に、LSKの価格が上昇したという過去も。
現在は、仮想通貨市場は冷え込んでいるように見えますが、世界中で仮想通貨やブロックチェーンを使った技術の開発や実験が着々と進んでいます。
日本の金融庁がどれくらいのスピード感で、仮想通貨取引所への通貨の上場やブロックチェーンの採用に対応してくるかはわかりません。
しかし、送金や決済などでブロックチェーン技術の応用が進んでおり、新たな動きや規制、ルールなどが出てくるはず。
仮想通貨は金融庁の管理下にあるため、今後の情報は仮想通貨やブロックチェーンだけでなく、金融庁の動きにも注目が必要です。
金融庁の許可が下りている仮想通貨交換業者登録がされている取引所や、ホワイトリスト入りしている通貨、ホワイトリスト入りするのではないかと思われる通貨の情報にもアンテナを張って、仮想通貨投資に活かしていきましょう。







































