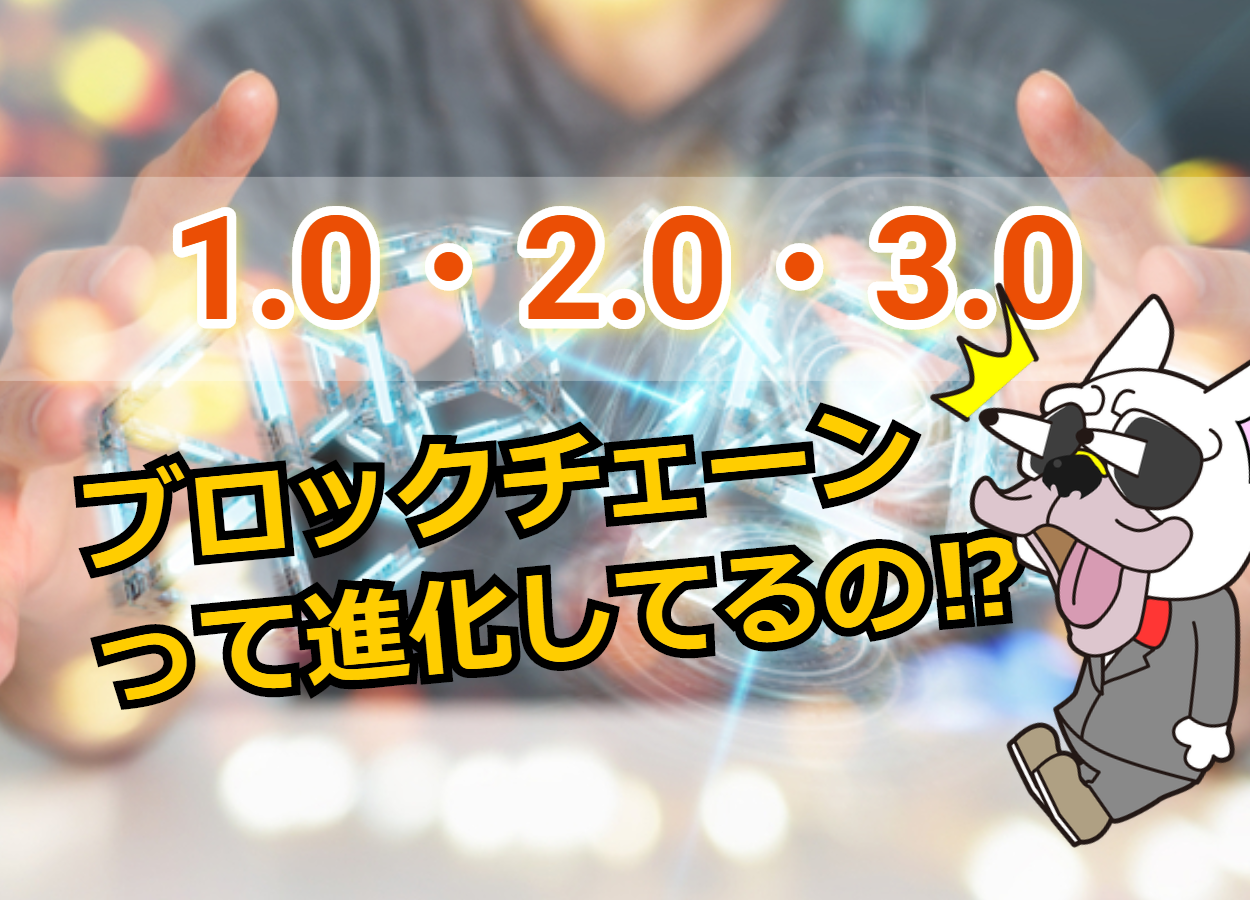
世界でも注目されているブロックチェーン技術ですが、2009年にビットコインが誕生してから、現在ではブロックチェーン3.0まで技術は進歩しています。
結論から言えば、
- 1.0は、仮想通貨を「通貨」として用いること
- 2.0は、通貨以外の金融分野への応用すること
- 3.0は、金融以外の生活分野へ応用すること
に分けることができます。
本記事ではブロックチェーン3.0について徹底的解説しますから、これからブロックチェーン技術はいかにして進歩していくのか参考にして下さいね。
この記事の目次
ブロックチェーン1.0・2.0・3.0の違いとは
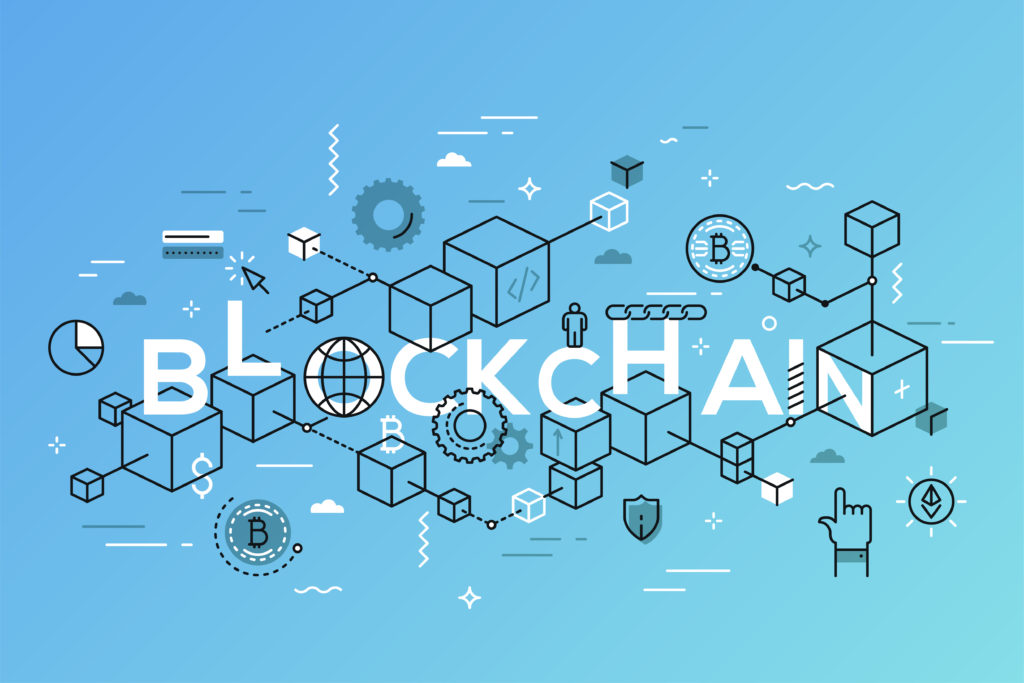
仮想通貨の根幹技術としてこれまで使われてきたブロックチェーン。
分散型台帳と呼ばれ、非中央集権型の管理システムを持ち、不正や改ざんが不可能とされている仮想通貨の取引を記録、管理する台帳です。
これまで多くの仮想通貨が誕生してきましたが、仮想通貨の種類によって利用目的に違いがあります。
その利用目的によって、第一世代・第二世代・第三世代と大きく3つに分けられています。
この世代の違いはブロックチェーンの進化によって世代分けされています。
世代ごとに、ブロックチェーン1.0、ブロックチェーン2.0、ブロックチェーン3.0に分かれています。
それぞれどのような違いがあるかを見ていきます。
ブロックチェーン1.0とは
ブロックチェーン1.0とは、第一世代のブロックチェーンのことを言い、仮想通貨を「通貨」として用いることを指しています。
一般的に仮想通貨に対するイメージがこのブロックチェーン1.0と言えるでしょう。
ビットコイン、ライトコイン、リップルなど認知度が高く、取引量も非常に多いのが代表的なコインとなります。
ブロックチェーン2.0とは
ブロックチェーン2.0とは、第二世代のブロックチェーンで、「通貨以外の金融分野への応用」として用いられます。
仮想通貨をお金としての使い方以外に金融分野で利用しようとする一歩進んだ仮想通貨の考え方です。
株式やローン、クラウドファンディングなどに利用されます。
ブロックチェーン技術を様々な業界の取引や契約の執行、権利の管理・証明などに応用するという考え方です。
イーサリアム、モナコイン、ネムなどが代表的な通貨と挙げられますが、このブロックチェーン2.0でのキーワードはスマートコントラクトです。
スマートコントラクトとは、イーサリアムを代表する技術の一つとして知られていますね。
簡単に言えば仮想通貨の取引情報を記録するブロックチェーン上に、「契約」を一緒に記録をしておく技術です。
例えば、「100円A社に送金したら、B社はドリンクを1本発送する」という契約があるとします。
この契約内容をあらかじめブロックチェーン上に書き込んでおきます。
A社がB社へ100円送金すると、書き込まれていた契約が自動執行し、ドリンクがA社へ納品されます。
このように当事者間であらかじめ結んでおいた契約が自動的に執行するという仕組みです。
このスマートコントラクトによって、これまでの紙媒体での契約書が必要なくなり、ブロックチェーンを利用していることで過去の取引履歴が記録されるため、不正に契約書や取引情報を改ざんすることはできなくなります。
また第三者機関が不要になるため、取引コストも大幅に削減できることが期待されます。
スマートコントラクトについてもっと詳しく知りたい人は下記の記事をご覧ください。
ブロックチェーン3.0とは
ブロックチェーン3.0とは、第三世代のブロックチェーンで、「金融以外の生活分野」でもブロックチェーン技術を応用するというものです。
具体的には、政府、健康、科学、工業、文化、芸術など多岐にわたります。
ブロックチェーン技術とスマートコントラクト技術を様々な分野に活用し、世の中をより便利にしていこうという考え方です。
代表的な仮想通貨は、
- ルートストック
- アイオン
- アークブロック
というような世間にはあまり知られていない通貨が多いです。
ブロックチェーン3.0に注目される理由

ブロックチェーン3.0の中心として期待されているのが、通貨としての機能+スマートコントラクト+IoTの3つを合わせたものです。
IoTとは、モノのインターネット化ですね。
あらゆるものをインターネットに繋げて、操作を行ったり、情報交換をする仕組みです。
簡単な例を挙げれば、外出先からスマホを使ってエアコンのスイッチを入れることができます。
医療分野では患者さんの健康状態の記録や管理・情報共有できる端末などが既に利用されています。
他にも自動車、交通機関、農業などの分野にも応用されるということで注目が集まっています。
IoTだけでは決済機能がないため、お金のやり取りは出来ません。
そのためIoTだけではサービスの幅が限定されてしまいます。
しかしブロックチェーン技術と融合させることで、通貨としての機能も果たせるため、サービスの幅が大きく広がると期待されています。
loT技術に着目した仮想通貨にジャスミーがありますが、まだ詳細は不明です。
スマートコントラクト技術
これは先述した通りなので省きますが、ブロックチェーン技術と共に最も注目される技術です。
Proof of Existence
Proof of Existenceとは記録システムのことで、たとえば身分証明書や卒業証明書、資格取得証明書などの証明事項をブロックチェーンに記録し、どこでも瞬時に確認することができるものです。
最近では偽造証明書などがネットで普通に売られているような時代です。
ブロックチェーンを活用することで偽造や改ざんすることが不可能なため、有効性が高いと言えます。
他にも、
- ライセンスなどの検証システム
- 住宅や土地の所有権の証明
- 相続証明書
- 車検証明
- 通関手続きの各書類証明
- 入国審査の自動化
- 偽物の発見システム
などがあります。
Traceability(履歴追跡)
Traceabilityとは、製品などの生産履歴をブロックチェーンに記録し、これまでの生産工程の全てを追跡することができます。
一般的に製品の生産工程には様々な仲介者が存在するため、原料や部品など細かな部分までを管理することは難しいとされていました。
消費者の食品安全意識や偽装問題などへの関心が高いため、これらの問題解決に繋がるとされています。
現在、ブロックチェーンを使って高級ワインの生産工程を記録する実証実験が行われています。
世界四大コンサルティングファームの一つ、EYアドバイザリー・アンド・コンサルティングは、ブロックチェーンを活用し、商品バリューチェーンを管理する「ワイン・ブロックチェーン」の実証実験を日本で始めた。
生産から販売までにさまざまな業者が関わり、モノの動きが国をまたぐために、管理や追跡が難しいワインや宝石、高級ブランド品などを対象とし、生産や流通の情報を一覧できる仕組みを構築する。
原料となるブドウの生産者、生産地、品種などはもちろん、熟成期間はどれくらいあったのか、輸送中の温度はどれくらいだったかなど様々な履歴が詳細に記録されます。
これらはコンピューターや自動車の生産工程にも応用されることが期待されています。
Tokenization(トークン化)
トークンとは仮想コインのことであり、履歴を追跡したいもの一つ一つに与えられます。
例えば、箱に入った品物を追跡したいのであれば、箱がどこへ行こうが、保有者が誰になろうが、トークンはその箱について回ります。
これまでの仕組みだと、各会社が出資しあい、第三者が中央集権型データベースを設置し、データを一元管理するのが一般的でした。
当事者同士のため信頼性は高いと言えますが、開発費、管理費などのコスト、管理責任が付きまといます。
トークンを利用することで、コスト削減につながり、問題が起こりやすい会社間でのデータの受け渡しを省略できるようになります。
Self Sovereign Identity(自己証明型身分証)
Self Sovereign Identityとはアイデンティティ(ID)の自己管理のことです。
IDをブロックチェーンで管理することで、ID管理する第三者(例えば役所)が不要となり、IDの漏洩や盗難のリスクが低減すると期待されています。
KPMGジャパンの豊田 雅丈氏も以下の様に語っています。
IDをブロックチェーンの分散型で管理すると、ID管理をする第三者が不要となり、IDの漏洩や盗難のリスクを低減すると期待されています。
また、個人についての情報、たとえば医療記録など、どの情報を公開するかしないかは(法律内で)その個人が決めることができることも、Self Sovereign IDの長所の一つです。
また医療記録などの個人についての情報を、どれだけ公開するかは個人で決めることができるのも長所の一つです。
Self Sovereign Identityは、入国審査の自動化、個人情報のコントロール、資金洗浄・テロ資金供与対策など多岐にわたりその応用性が考えられています。
仮想通貨3.0とブロックチェーン3.0の違い

平たく言えば同じことですが、厳密に言えば違うと言えると思います。
仮想通貨3.0は、金融以外の生活分野でブロックチェーンを活用するために必要な仮想通貨を指します。
ブロックチェーン3.0は、活用しようとする考え方そのものを指します。
つまり、通貨としての価値は仮想通貨。
技術としての価値はブロックチェーンと言えるでしょう。
仮想通貨3.0として注目されるNEOとは

NEOとは、中国版イーサリアムと呼ばれており、中国発の仮想通貨です。
時価総額は16位にランクインしており、人気のある通貨と言えます。
中国版イーサリアムと言われているだけに、スマートコントラクト機能を備えており、処理速度が早く、イーサリアムの50倍とも言われています。
多くのプログラミング言語に対応しており、多くの人が開発に参加しやすくなっています。
ちなみにイーサリアムはsolidtyというあまり一般的でない言語のみのため、参加ハードルが高いです。
NEOはDBFTというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、NEO保有者の投票によって、ブックキーパーと呼ばれる代表者を数名決めます。
この代表者は自身の本名あるいは団体名を公表しなければなりません。
ブックキーパーはNEOのアルゴリズムに則り、ブロックを承認してGASをマイニング報酬として入手することができます。
GASは、NEOのプラットフォームを動かすために必要なトークンです。
スマートコントラクトの作成や使用時にGASが必要となります。
NEOの送金手数料やNEOのブロック承認に貢献した人に対しての報酬として使われます。
PoWやPoSなどのマイニングと異なり、NEO対応のウォレットに預けることで、保有数に応じてGASをNEO保有者全員報酬として受け取ることができます。
もっとNEOについて詳しく知りたい人は以下の記事をご覧ください。
仮想通貨3.0を標榜するSkycoinとは

Skycoinとは次世代仮想通貨と呼ばれており、ビットコインの問題点を解決した設計を持つと言われています。
ビットコインの問題点とはスケーラビリティ問題です。
ビットコインが誕生した当初は、流通量、取引量共にそれほど多くはありませんでしたので、低い手数料で素早く世界中に送金することが出来ました。
しかし取引量が増えてくるにつれて、マイニングが追い付かなくなり、最終的にサーバーダウンなどの問題が発生しました。
これを解決するためSkycoinではオベリスクというシステムを採用しました。
オベリスクとはSkycoinで独自に用いられているマイニングを必要としない合意検証システムです。
そのため手数料の高騰や送金遅れを防ぐ効果などが期待されています。
ブロックチェーン3.0や仮想通貨3.0は今後どうなる?

仮想通貨そのものが通貨として活用されることは難しいと考える有識者が多く存在します。
しかしその仮想通貨を支えるブロックチェーン技術は今後様々なものに活用されると考えています。
効率的かつ低コストで、不正や改ざんが不可能なブロックチェーンであれば、生産性を最大限に引き出せる可能性があります。
しかしその分、ヒトの管理能力が衰え、全てブロックチェーン任せになってしまうと人間力の低下に繋がるのではないかとも感じます。
上手に共存・共栄が必要だと個人的には感じます。
まとめ
テクノロジーはものすごい早さで進化しています。
近い将来、なんでもスマホ一つで操作、管理する世の中がやってくるかもしれません。
また、ブロックチェーン技術は国会でも取り上げられた様に、国内でも注目されている技術です。
その点を踏まえると、ブロックチェーン技術は今後さらに期待されていくのではないでしょうか。












































