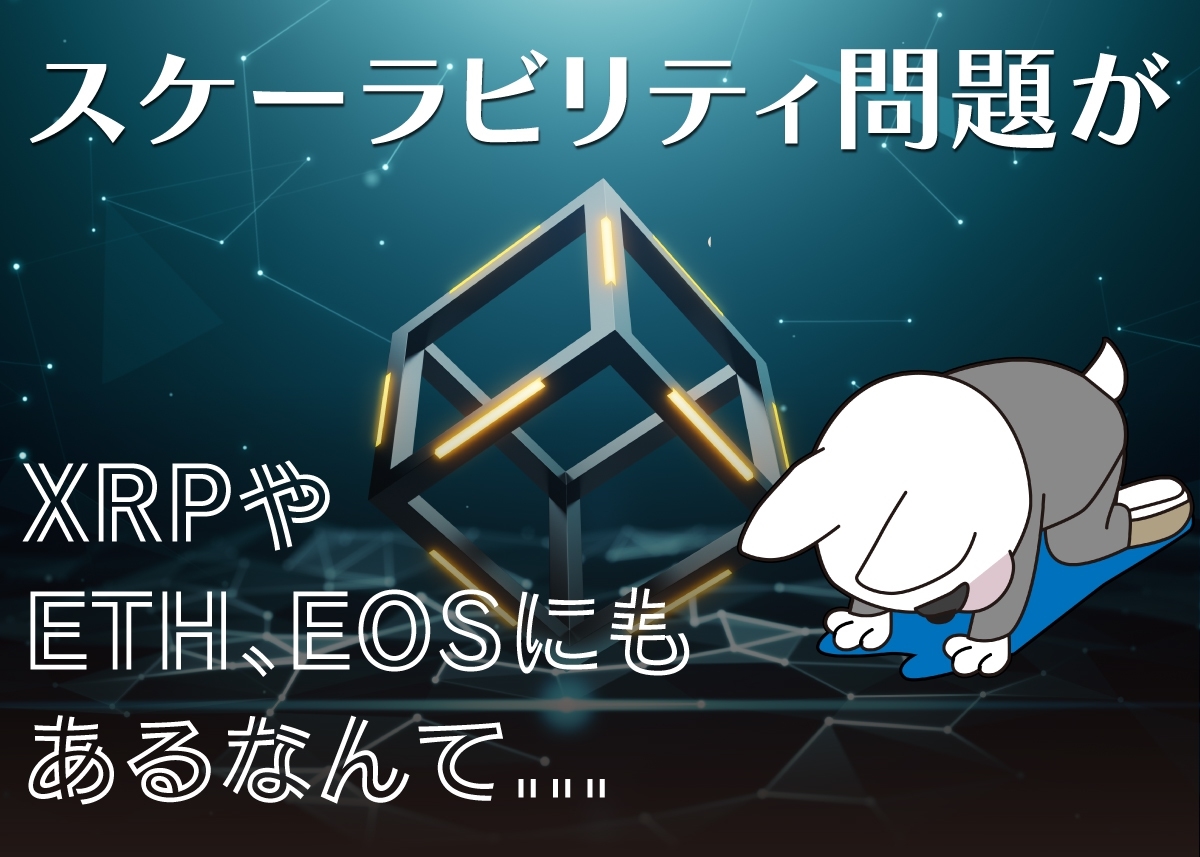
スケーラビリティとは、本来はコンピューター用語で『拡張性』とか『拡張可能性』を示しますが、元々は「scale(規模)」と「ability(能力・技量・力量)」を足した造語です。
システム利用者増に伴う負荷の増大や用途の拡大などに対して、柔軟に性能や機能を向上・拡張できるかを表した言葉です。
例えば、デスクトップPCであれば、メモリーやハードディスクを大きくしたり追加することができますし、モニターを大きくすることもでき、マザーボードやCPUの交換により性能を大幅にアップさせることも可能です。
これに対してノートPCは、デスクトップPCほどカスタマイズ性がないため、大幅な性能アップは望めません。
この場合、デスクトップPCはスケーラビリティが高く、ノートPCはスケーラビリティが低いということになります。
では、仮想通貨で使われる「スケーラビリティ問題」とはどういうものなのでしょうか。
この記事では『取引で損をしないために、知っておきたいスケーラビリティ問題』を取り上げます。
この記事の目次
仮想通貨で起こるスケーラビリティ問題とは?

仮想通貨で起こるスケーラビリティ問題は、
ブロックチェーンやマイニングと密接な関係があり、特にBitcoin(BTC)において取り上げられることの多い問題です。
『マイニング(採掘)とは?仕組みや種類、やり方を徹底解説』にも書かせていただきましたが、ここで簡単におさらいをしておきましょう。
ビットコインのスケーラビリティ問題
Bitcoinで取り上げられるスケラビリティー問題とは、
BTCのブロック生成時間(ブロックチェーンに新しいブロックがつながれる時間)が通常の承認時間である10分よりもさらに長く延びてしまうことにより、送金詰まりが発生する問題のことを指しています。
Bitcoinのブロックチェーンのトランザクション(承認)タイムは、1ブロックが10分と決まっています。
また、ブロックサイズも1MBと決まっており、1ブロックに収められるデータ量も決まっています。
取引データのサイズは、1つが平均250byteほどなので、1MB(100万byte)のブロックに収められる取引データの数は約4,000件ほどになります。
10分の間に、集まってくる取引データが4,000件未満なら問題はありませんが、4,000件を超えると、処理しきれなくなったデータが溜まってしまいます。

本来なら10分で承認されるはずの取引がなかなか承認されず、延々と待ち続けることになります。
承認を待っている間に価格が変動してしまい、取引において損失が出てしまう場合もあるのです。
過去には、最長で24時間以上待たされた例も報告されています。
このようにBitcoinは、対応できるキャパシティに限界があり、限界を超過するトランザクション量が発生した場合、キャパシティを超える分に関して、ブロック追加待ちが起こり、トランザクション(承認)詰まりが発生してしまうのです。
最初にスケーラビリティとは、システム利用者増に伴う、負荷の増大や、用途の拡大などに対して、柔軟に性能や機能を向上、拡張できるかを表したものであると説明しました。
つまり、利用者増に伴う取引件数の増加に対して、Bitcoinはブロックサイズやブロック生成時間の制約があるので、スケーラビリティに問題があるとされたのです。
これがBitcoinのスケーラビリティ問題です。
Bitcoinスケーラビリティ問題の現状

このスケーラビリティ問題は、取引においてどのような障害をもたらすのでしょうか?
答えを先に言うと、送金詰まり(送金できない状態)を起こしてしまうのです。
取引が新たなブロックに追加されない限り、その取引はトランザクション(承認)されません。
取引が承認されなければ、送金はできません。
送金できなくなると、待ち時間の間に相場が変動して、取引に何らかの損失が発生してしまうのです。
これが、スケーラビリティ問題の最大のポイントです。
ビットコインのスケーラビリティ問題の現状
Bitcoinのスケーラビリティ問題は、今現在はどうなっているのでしょうか?
Bitcoinの毎日の取引件数の推移グラフを見ながら、考えていきましょう。
上記グラフは、2009年から2019年現在までの取引量の推移を表したグラフで、下記のグラフはこの半年(180日)の推移を表しています。

ここ最近の価格上昇に伴い、Bitcoinの取引量が増えていることがわかります。
大体40万件ほどの取引量になってきており、これは2017年のバブル期に匹敵する取引量になっているのです。
先ほど、1ブロックに収められる取引データは、約4,000件であるとお伝えしました。
毎日の取引量が40万件になっていますので、400,000 ÷ 4,000 = 100で、毎日100個のブロックが新たにつながれていることになります。
Bitcoinのブロック生成時間(1ブロックを作る時間)は10分ですので、1日に144個までなら、その日中に承認を終えることができます。
ただ、これは1日24時間という時間枠で見た場合の話です。
リアルタイムの承認状況はchainflyerで
リアルタイムでトランザクションの状況が見たいという場合は、ビットフライヤーが提供するchainflyergが便利です。
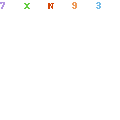
chainflyerでは、トランザクション(承認)の状況をリアルタイムで見ることができます。
今のところ、約3.84件/秒なので、ほぼ秒4件といったところでしょうか。
そうすると、4件 × 10分(600秒)= 2,400件 となり、想定の4,000件よりは少ないため、10分のブロック生成時間内に処理はできていると推測することができます。
ただし、これはあくまでも確認した時点(2019年5月初旬)での話であり、取引が活発な時間帯であれば、待ち時間が発生してもおかしくはない状態だとも言えます。
スケーラビリティ問題とマリアビリティ問題

ここからは、スケーラビリティ問題に対する解決策について見ていきましょう。
最も単純な解決方法は、下記2つのどちらかです。
- ブロックチェーンのブロックサイズを大きくする
- ブロック生成時間を短くする
ブロックサイズを大きくすれば、たくさんの取引情報を取り込めるので、取引データが溜まったとしても、規定のブロック生成時間内に処理することが可能になります。
また、ブロック生成時間を短くすれば、ブロックサイズは同じでも、繰り返しブロックを作る(承認する)ことができるので、取引データを溜めることなく処理が可能になります。
ただ、この2つの方法には、どちらも欠点があります。
スケーラビリティ問題の解決策の欠点
1つは、それまでの仕様と大きく異なるため、ブロックチェーンをハードフォークして、仕様変更しなければならない点です。
ハードフォークした時点で、それ以前のブロックとそれ以後のブロックには互換性がなくなります。
そしてもう1つは、トランザクションにおけるセキュリティの問題です。
ブロックサイズを大きくしたとしても、またブロック生成時間を短くしたとしても、1件の取引データに対して、そのデータが正式なものであることを確認する時間は短くなります。
何より、新しくブロックを繋げてしまうと、そのブロックに含まれるデータを修正することは、ほぼできない状態になってしまいます。
そのため、ブロックをつなげる際には、その内容に間違いがないかを、マイナーがいくつもの工程で確認し、その結果を他のマイナーが承認して、初めて新しいブロックをつなげる権利を得るのです。
しかし、ブロックサイズを大きくしても、ブロック生成時間を短くしても、そのデータの確認時間は減ることになります。
そうなると、ブロックチェーンのセキュリティが担保できない状態に陥りかねないのです。
マリアビリティ問題とは
このセキュリティの問題は、スケーラビリティ問題の対極にある、マリアビリティ問題と呼ばれるものです。
Bitcoinがブロックサイズとブロック生成時間を決めているのは、悪意あるユーザーが取引データを改ざんし、二重取引ができてしまう脆弱性を防ぐ狙いがあるからです。
このように、スケーラビリティとセキュリティは、トレードオフの関係にあるため、簡単にどちらかを優先すれば良いというものではないのです。
Bitcoinのスケーラビリティ問題に対する対策①

こうしたスケーラビリティ問題に対して、ビットコイン開発陣は何も対策を打たなかったわけではありません。
このBitcoinのスケーラビリティ問題が発生し、対策を迫られた開発陣の一部は、Bitcoinのブロックサイズを1Mbyteから8Mbyteに上げることを提案しました。
しかし、開発陣の過半数の賛成が得られなかったため、この一部の開発陣はBitcoinのブロックチェーンをハードフォーク(それまでの仕組みが使えなくなるアップグレード)を実行して、Bitcoinとは違う仮想通貨を作りました。
それがBitcoin Cash(BCH)です。
ブロックサイズを拡大したBitcoin Cash(BCH)
Bitcoin Cashは、ハードフォーク後から市場に受け入れられ、一時期は時価総額で3位の座を確保するほどでした。
特にブロックサイズを8Mbyteに拡大したので、トランザクション詰まりが起こりにくくなった点は、市場から高い評価を獲得しました。
しかし、Bitcoin Cashは、2018年10月に、再びハードフォークを行ない下記の2つに分裂しました。
- Bitcoin Cash ABC
- Bitcoin Cash SV
これは、新たなコインを生み出すことが目的ではなく、開発陣の考え方の違いから起こったものでした。
このハードフォークによって、BTCの価格が下落し、市場では混乱が引き起こされました。
その結果、Bitcoin Cashの仕様を受け継いだBitcoin Cash ABCがBitcoin Cashの後継として認められ、
一方のBitcoin Cash SVは、Binanceをはじめとする多くの取引所から、上場廃止を告げられたのです。
バイナンスがビットコインSVを上場廃止にする日は、日本時間4月22日(月)の19時。全てのトレーディングペアにおける取引を取りやめる。出金は、日本時間7月22日(月)の19時まで続ける予定。
バイナンスのCZは12日、「クレイグ・ライトはサトシじゃない。もう我慢の限界だ。上場廃止だ!」とツイート。ビットコインの創設者サトシ・ナカモトを自称するライト氏が、ビットコインコミュニティーのメンバーを名誉毀損で訴える構えを示したことがきっかけだ。
一方、CZのツイートがきっかけとなり、ツイッター上では「ビットコインSVを上場廃止にしよう」運動が広まっている。仮想通貨投資会社モルガン・クリーク・デジタルの創業者であるアンソニー・ポンプリアーノ氏は、「5月1日に全ての取引所が同時にBSVを上場廃止にすべき」と主張している。
このように、市場から受け入れられないハードフォークは、結果として自身の首を絞めることにもなり得るのです。
Bitcoinのスケーラビリティ問題に対する対策②

Bitcoinのスケーラビリティ問題を解決するために、一部の開発陣はハードフォークによってBitcoin cashを誕生させましたが、一方では、違った対策も考えられていました。
Bitcoin開発陣が考え出したその対策は、ブロックサイズを大きくするものでも、ブロック生成時間を短くするものでもなく、
「ブロックチェーンをハードフォークすることなく、ブロックに収めるデータを増やす」という方法でした。
Segwit(セグウィット)

従来のブロックチェーンにつながれているブロックは、上の図のようにたくさんの取引データが入っています。
その取引データの中は、取引の内容を示すデータと、署名が入っています。
開発陣が考え出した方法とは、この取引データを『データ』と『署名』に分けて、『データ』を圧縮して、ブロックに詰めるという方法です。
この方法は、Segregated(分離する・分解する) Witness(証明・署名)の略で、Segwit(セグウィット)と呼ばれるようになりました。
Segwitでは、取引データを圧縮することで1ブロックに記録される取引データが増加し、取引処理を早くすることが可能になります。
また、取引データを圧縮するので、確認時間を短くすることも可能になり、セキュリティ上の問題も起こりません。

Segwitは、署名をWitnessと呼ばれる領域(サブチェーン)に一時保管します。
これにより、ブロックサイズを変更せずに、約2倍の容量を確保することに成功したのです。
Segwitは、ハードフォークすることなく、スケーラビリティとセキュリティという、トレードオフの関係にある問題を、一度に解決したのです。
Segwitについてもっと詳しく知りたい人は下記の記事をご覧ください。
Bitcoinのスケーラビリティ問題に対する対策③

Lightning Network(ライトニング ネットワーク)
Segwitを活用した、もう1つのスケーラビリティ対策が、Lightning Network(ライトニング ネットワーク)です。
Lightning Networkとは、メインのブロックチェーン(オンチェーン)の外部に、決済用の外部ネットワーク(オフチェーン)を構築する技術のことです。
オフチェーンは、各端末ごとのノードが設置され、そのノード間でネットワークが形成されます。
そのネットワーク間で取引データがまとめられ、トランザクションが効率化されます。
まとめられた取引データがオンチェーンであるブロックチェーン上に送られる仕組みになっているのです。
Lightning Networkに参加するには、一定額のBitcoinがブロックチェーン(オンチェーン)上にプール(預金)された状態になっている必要があります。
そのプールされたBitcoinを預託金として、ノード間での取引を行うことができます。
Segwitにより決済と承認を分散
Lightning Networkの最大の利点は、決済と承認を分けて行える点にあります。
従来のBitcoin取引では、ブロックチェーンに記録されるまで取引の承認は行われず、それゆえ決済も行うことができないことでスケーラビリティ問題(送金詰まり)が発生していました。
これに対してLightning Networkは、
「取引の内容をデータと署名に分けて署名をオフチェーンに配する」というSegwitの特徴によって、決済と承認を分けることが可能となります。
オフチェーン上で取引の決済を行い、後からオンチェーン上で取引を承認することによって、従来の仮想通貨ではできない決済速度を実現したのです。
2ndレイヤーでスムーズな取引を実現
Lightning Networkで使用するオフチェーンは、2nd(セカンド)レイヤーとも呼ばれます。
この2ndレイヤーの特徴は、取引を行う当人同士がつながっていなくても、取引をする人のアドレスを知る他のノードを使って、ネットワークの経路を結べる点にあります。

上のイラストのように、AさんとBさんが取引をしたい場合、本来であればAさんとBさんを直接結ぶネットワークが必要になります。
しかし2ndレイヤーは分散型Networkなので、中間のノードを介してAさんからBさんまでの間を結ぶことができるのです。
中間のノードは、下記の図のように自動で選択されます。

AさんからBさんまでのノードが結ばれることで、取引が可能となります。

この時、Cさん、Dさん、EさんはAさんとBさんの間で行われている取引の情報を得ることはできません。
あくまでもノード間を結ぶ中間点(ノード)の役割を担っているだけなのです。
このように、自動的にAさんからBさんまでがノードで結ばれるため、取引がスムーズに行われ、送金詰まりも発生しません。
特にLightning Networkは、取引の決済を先に済ませることができるため、即時の送金が可能となります。
スムーズな取引により手数料も低減可能
またLightning Networkは、取引をスムーズに済ませることができるため、取引手数料を抑えられるというメリットも生まれるのです。
しかも、この手数料が抑えられるというメリットを活用して、マイクロペイメント(少額決済)も可能にしているのです。
このような特徴をもつことから、Lightning Networkは今最も注目されている技術の1つとなっています。
Lightning Networkの今後の展開
メリットの多いLightning Networkですが、ブロックチェーン上にプールされた資金がベースになっているため、多額の送金には対応できないという欠点がありました。
しかし現在では、Lightning Networkを活用して多額の資金を送金可能にする試みが行われています。
このLightning Networkについて、さらに詳しく知りたい場合は、Lightning Networkの送信方法について詳しく解説している下記の動画が参考になります。
Ethereum(ETH)のスケーラビリティ問題に対する取り組み

ここまでBitcoinのスケーラビリティ問題について触れてきましたが、ここからはBitcoinとは異なる特徴をもつEthereumのスケーラビリティ問題について見ていきましょう。
Ethereumのスケーラビリティ問題
Ethereumは多くのDapps(分散型アプリケーション)のベースとなっているため、トランザクションが集中すると、DAppsの処理が滞ってしまうという問題が発生します。
これによって、送金詰まりが起こるだけでなく、DAppsによる契約の履行が行われないという問題も起こってしまいます。
これはDAppsのgas(燃料)代としてETHが使われていることが原因となっており、Dappsによる契約を止めないためにも、このEthereumのスケーラビリティ問題への対策が急がれています。
またEthereumはマイニングにも問題がありました。
本来マイニングは、フルノードによってトランザクションの検証をする必要があります。
ところが、処理に時間がかかる低スペックのライトノードを使うマイナーが増加したことにより、トランザクションの処理・検証に時間がかかってしまうという問題が起きたのです。
それ以外にも、一時期はEthereumのブロックチェーンにICOが集中したことで、取引も集中してしまい、送金詰まりが起こるという事態も発生しました。
こういった問題によって、Ethereumのスケーラビリティ問題は、Bitcoin以上に厳しいものになった時期があったのです。
注目される4つの解決手段
Ethereumのスケーラビリティ問題の解決策として、現在注目されている主な手段が4つあります。
- Casper(キャスパー)
- Sharding(シャーディング)
- Plasma(プラズマ)
- Raiden Network(ライデン・ネットワーク)
ただ先ほど、「現在注目されている主な手段が・・・」とお伝えしたように、Ethereumは現在、スケーラビリティ問題に対して、有効な手段を打っていません。
Ethereumがスケーラビリティ問題に対する有効手段を打たない理由
というのも、Ethereumのブロック生成(承認)時間は15秒と非常に短く、ブロックサイズは常に変化しているからです。
Bitcoinは、ブロック生成時間が10分で、ブロックサイズの上限が1Mbyteで固定されています。
Bitcoin Cashはブロック生成時間は同じですが、ブロックサイズを引き上げて8Mbyteに変更(ハードフォーク)しました。
いずれも、ブロック生成時間とブロックサイズが固定されており、取引量が大幅に増加した場合、送金詰まりが発生し、スケーラビリティ問題が取りざたされるのです。
対してEthereumは、先ほどお伝えしたように、ブロック生成時間が15秒と非常に短く、ブロックサイズにおいては、常に変化しているのです。
Ethereumのブロックサイズを決めているのは、マイナー(採掘者)です。
フルノードマイナーの選挙によって、サイズ変更が可能になっています。
Ethereumのブロックサイズの変化は、etherscan.ioのサイトで確認できます。

そして上のグラフが、Ethereumのブロックサイズのチャートになります。
これで見ると、最近のEthereumのブロックサイズは、20Kbyte前後とBitcoinの1/50ほどです。
一方、秒間のトランザクション数は6.51件(CoinGecko調べ)ですから、1ブロックに約100件ほどのデータが収められていることになります。
これはBitcoinの1/40に相当しますが、ブロック生成時間もBitcoinの10分に対して、Ethereumは15秒ですから、こちらも1/40になります。
つまり、セキュリティにかけている時間は、理論値上はどちらも同じだと言えるのです。
ブロック生成時間も、収められるデータ数もほぼ同じ1/40であれば、処理できる取引数は、Bitcoinとほぼ同じだということになります。
しかし、トータルで見た時の数は同じですが、EthereumとBitcoinでは大きな違いがあります。
それはブロック生成時間の短さです。
Bitcoinが1つブロックを作る間に、Ethereumは40個のブロックを作ることができるという点は、大きな違いです。
Bitcoinが10分間のデータをまとめて処理するバッチ処理型だとすると、Ethereumは15秒ごとに細かくデータを処理するリアルタイム処理型だと言えます。
この場合、取引の流入数が同じだとすると、Bitcoinに比べてEthereumの方がスケーラビリティが高いと言えるのです。
理由は非常に単純で、取引データがたまる時間が短いからです。
Bitcoinのバッチ処理では、取引データがキャパシティを超えて溢れると、次のブロックチェーンができるまでに20分以上の時間が必要です。
一方Ethereumの場合は、ブロック生成時間が15秒ですので、次のブロックができるまでの待ち時間は30秒ほどです。
Ethereum本来の待ち時間からすれば長くなりますが、Bitcoinと比べれば遥かに短いものです。
このようにBitcoinと比べるとスケーラビリティの高いことが分かるEthereumですが、実際に市場で送金詰まりが起こった事実は変わりませんし、今後、送金詰まりが起こらないとも言い切れません。
そこで今後起こるであろうスケーラビリティ問題の解決策として下記の4つが提案されているのです。
- Casper(キャスパー)
- Sharding(シャーディング)
- Plasma(プラズマ)
- Raiden Network(ライデン・ネットワーク)
ではこの対策の内容を、簡単に説明していきましょう。
Casper(キャスパー)
1つ目の解決策はCasperです。
Casperとは、Ethereumの予定されているアップグレードハードフォークの1つで、トランザクションの検証をPoWからPoSに変更することが決まっています。
Ethereumは下記4つのハードフォークを予定しています。
- Frontier(フロンティア)
- Homestead(ホームステッド)
- Metropolis(メトロポリス)
- Serenity(セレニティ)
2019年3月に、3つ目のハードフォーク「Metropolis」の後半であるConstantinopleが実行され、ほぼ問題なく終了しました。
そして、4つ目のハードフォークである「Serenity」に組み込まれているのがCasperです。
Casperは本来、「Serenity」ではなく「Metropolis」で実装される予定でしたが、諸般の事情によりSerenityのハードフォーク時に延期されることになりました。
CasperがPoSを採用する理由
ではなぜ、Casperはトランザクション検証をPoWからPoSに変更するでしょうか。
PoWとPoSの最大の違いは、トランザクションのための計算を必要としないという点です。
PoWには、ブロックサイズやブロック生成時間という縛りがどうしても存在し、膨大な計算処理をしなければなりません。
そのためマイナーは、専用のマイニングマシン(ASIC等)を準備する必要があります。
こうしたコストは、ブロックチェーンを支えるために必要なものですが、こうした外的なコストには、膨大な電力も含まれるのです。
事実、Bitcoinのマイニングに使われる電力は、小国の消費電力を上回るとさえ言われていて、環境問題として取り上げられることさえあるのです。
しかしPoSの場合は、Stakeと呼ばれる掛け金を預金し、その預金額に応じてブロック生成の権利が得られる仕組みとなっているため、マシンコストや電力といった外部コストを必要としません。
これはPoSの利点でもありますが、『富の集中化』が起こり組織が中央集権的になってしまうという懸念もあります。
この件に関しては、Ethereum財団で様々な検証が行われており、独自のPoSになるとされていますが、どのような仕様になるかは、現在のところまだ不明です。
Sharding(シャーディング)
次はSharding(シャーディング)です。
Shardingは、ノードを『Shard(シャード)』と呼ばれるいくつかのグループに分け、各グループでグループに割り当てられたトランザクションのみを処理します。
こうすることで、トランザクションを並列処理することが可能となります。
各shardでトランザクションされ集められた取引データは、1つのブロックに格納され、さらにEthereumのブロックチェーンに追加されます。
そのため、トランザクション自体は全てをオンチェーンにします。
現在のEthereumは、全ノードが同じトランザクションを検証する必要があるため、ブロック生成に時間がかかってしまいます。
それを並列処理することで、複数のトランザクションを一度に処理することが可能となります。
処理されたトランザクションに関しては、定期的にShard同士で同期しあうようになっています。
このShardingは、PoWでは実行できません。
Shardにハッシュパワーの小さいノードが集まってしまった場合、簡単に51%アタックを仕掛けることができるからです。
そのためShardingは、先に挙げたCasper(PoSへの移行)とセットである必要があります。
PoSならば、ハッシュパワーの大小は関係なく、各Shardに振り分けるだけでアルゴリズムに従ったトランザクションが可能となります。
このShardingは、現在実装可能だと言われていますが、Casperとセットで延期になっているのは、こうした理由があるからです。
Plasma(プラズマ)とRaiden Network(ライデンネットワーク)
最後は、PlasmaとRaiden Networkについてです。
CasperとShardingは、Ethereumのメインチェーン上の処理速度向上を目指すものでした。
対してPlasmaとRaiden Networkは、BitcoinのSegwitやLightning Networkのように、トランザクションの一部をサイドチェーンで処理する方法です。
事実、このPlasmaがEthereumのスケーラビリティ対策の中では、最も注目されています。
Plasmaには、Plasma CashやPlasma XTなど様々な種類があり、それぞれ開発が進められています。
中でもヴィタリック・ブリテンとコア開発者らは、Plasma Cashを改善したPlasma Debitと呼ばれる新たなPlasmaを提唱しているようです。
BitcoinのSegwitは、署名とデータを分けて、署名をサブチェーンに格納して、メインチェーンブロックにはデータのみを格納する方式をとっていました。
対して、EthereumのPlasmaは、Plasmaがサブチェーンをツリー状に作って、その中にメインチェーンにとって不要なデータをサブチェーンに格納して、メインチェーンに必要な情報(データ)だけを、ブロックに格納するという方式です。
方式は違いますが、「ブロックに収めるデータサイズを小さくできるため処理速度は変わらずにデータの件数を増やせる」という点や「サブチェーンを作る」という考え方は、BitcoinのSegwitと同じです。
また、Raiden Networkは、考え方や構成がBitcoinのLightning Networkと同じとなっています。
違う点は、ERC20に準拠したトークンも使えるという点だけです。(Lightning Networkで使えるのはBTCのみ)
Raiden Networkでは、一定額のETHをペイメントチャネルにプール(預金)して、Raiden Networkに参加します。
その後はLightning Networkと同じように、ノードが直接つながっていなくても送金可能となります。
「送金の決済がオフチェーン状で完了しているため送金詰まりが起こらない」という点もLightning Networkと同じですし、「マイクロペイメント(少額決済)に対応している」という点も同じです。
しかし、これら4つの解決策(Casper、Sharding、Plasma、Raiden Network)の実装時期はまだ未定となっています。
ただし内容から考えれば、Serenityハードフォークの時期に重なることが濃厚と言えるでしょう。
Ripple(XRP)のスケーラビリティ問題に対する取り組み

スケーラビリティ問題を取り上げる時、非常にスケーラビリティの高い仮想通貨であるRipple(XRP)は外すことのできない存在です。
公式ページには下記のような画像があります。

この画像では、承認にかかる時間は3.3秒、1秒間に1,500件の取引を処理できることが記載されており、XRPの優位性を確認することができます。
実際にどのようなスペックがあるのか見ていきましょう。
Rippleのスペックを支えるアルゴリズムPoCとは
Rippleのスペックを支えているのが、Rippleが採用しているコンセンサス・アルゴリズム(検証の仕組み)『PoC:Proof of Consensus(プルーフ・オブ・コンセンサス)』です。
PoCは、Ripple社が決めたUnique Node(特殊な参加者)の8割以上が、取引を承認すると取引データをブロックチェーンに記録すると定められています。
このUnique NodeをRipple社が決めているという点が、XRPが他の仮想通貨と大きく違う点です。
また、Unique Nodeに流されるCandidate(候補者)と呼ばれる取引データも、先にRipple社が選別しているという声もあります。
事実、Ripple社が承認しているUnique Nodeの正確な数は不明ですし、取引データの流れもRipple社が掌握している部分が多すぎます。
これにより「XRPは仮想通貨(パブリックブロックチェーン)ではない」という意見が出ているほどなのです。
確かに、XRPが分散性を持っていないことはほぼ間違いありませんが、分散性を代償に、高いスケーラビリティとセキュリティを有していることも事実なのです。
しかし、このXRPが打ち出している優位性を、性能面で遥かに凌駕する仮想通貨があるのです。
EOS(EOS)のスケーラビリティ問題に対する取り組み

仮想通貨のスケーラビリティを語る上で、もう1つ外せない仮想通貨があります。
それがEOS(EOS)です。
EOSのコンセプトはEthereumに近く、汎用性の高いスマートコントラクトプラットフォームです。
約1年に渡るICOで4,000億円を超える資金調達を達成し、2018年6月にメインネットをローンチしました。
将来は、スマートコントラクト分野でEthereumに取って代わるのではという期待もされているほどです。
処理能力の高さがEOS最大の特徴
EOS最大の特徴は、処理能力の高さにあります。
スケーラブルなブロックチェーンであり、その能力はXRPを遥かに凌駕します。
ブロックタイムは0.5秒となっており、秒間数百万のトランザクションを処理できる(最大値)プラットフォームを有していると発表されています。
しかも、トランザクション手数料は無料(※1)です。
ブロックタイムとトランザクションの比較
これまで紹介してきたように、Bitcoinのブロックタイムは10分、トランザクションは秒間7件(最大値)です。
Ethereumがブロックタイムは15秒、トランザクションが秒間30件(最大値)です。
スケーラブルと言われるXRPでさえ、ブロックタイムは不明ですが、トランザクションは秒間1,500件(最大値)です。
対してEOSは、ブロックタイムは0.5秒、トランザクションは秒間数百万と言われています。

このように処理能力が高いEOSですが、当然、それはなにかしらのトレードオフの上に成り立ちます。
EOSのブロックチェーンは21の少数ノードがバリデータ(※2)となって運用されています。
このようにEOSは、無料で、早くて、スケーラブルなブロックチェーンなのです。
EOSはDPoSを採用
EOSは、コンセンサスアルゴリズムにBFT-Delegated Proof of Stake(以下DPoS)を採用することで、高速な処理速度を実現しています。
ブロックチェーンに限らず、処理速度というものは、性能の高いコンピュータを使用すればするほど向上します。
これは中央集権型も、分散型も変わりません。
高性能コンピュータで管理されたノードと、太い回線で結ばれたノード同士であれば、ブロックサイズが大きくても、ブロックタイムが短くても、高速での処理がが可能です。
そこで分散性の問題は横において、この前提であれば少数のノードでもうまくいくのではないかという仮説のもとに設計されたのがDPoSなのです。
PoSの仕組みを応用したアルゴリズムDPoS
DPoSは通常のPoSの仕組みを応用したアルゴリズムということになります。
通常のPoSは、ネットワーク上で使用される仮想通貨を多く保有した人が、ブロック生成に参加できるようにした仕組みです。
対してDPoSでは、ネットワーク参加者がEOSをプールして、各自が推薦するノードに投票し、21のノードが選ばれます。
この21のノードは、Block Producers(ブロック プロデューサー)と呼ばれ、投票で得た票数をベースに、ブロック生成の権利を得る仕組みになっています。
この21のノードを、高スペックのコンピュータと太い回線で結んで、高い処理能力を維持するのが、EOSのコンセンサス・アルゴリズムDPoSです。
時価総額ベスト10入り!注目度の高い仮想通貨EOS
EOSはローンチしてから、まだ1年も経っていない仮想通貨ですが、時価総額でベスト10に入っています。
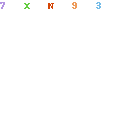
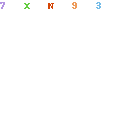
Coin Market Capで6位、Coin Geckoで4位と、非常に注目度も高いことがわかります。
そのベースにあるのは、他のコインを圧倒するスケーラビリティの高さと言えるでしょう。
まとめ
スケーラビリティに問題があると、送金詰まりにより取引で色々な弊害が起こってしまいます。
送金詰まりを避けるためにも「スケーラブルな仮想通貨を選びたい」というのが当然の心理であり、事実、スケーラブルな仮想通貨が高い人気を集めています。
特にEOSは、上場してからまだ1年も経っていない状況で、トップ10にランクインしていることからも人気度が伺えます。
記事内でも説明してきましたが、
スケーラビリティ問題を解決するためには、セキュリティか分散性のどちらかを犠牲にする必要があり、BitcoinやEthereumはバランスを取ることを考え、XRPやEOSは分散性を犠牲にする対策を選択しています。
それぞれの仮想通貨の開発陣が、送金詰まりを起こさないスケーラブルな仕組みを作るために日々研究を続けており、これからも新たな解決策が登場する可能性も大いにあるといえます。
スケーラビリティ問題の今後の展開に注目していきましょう。










































