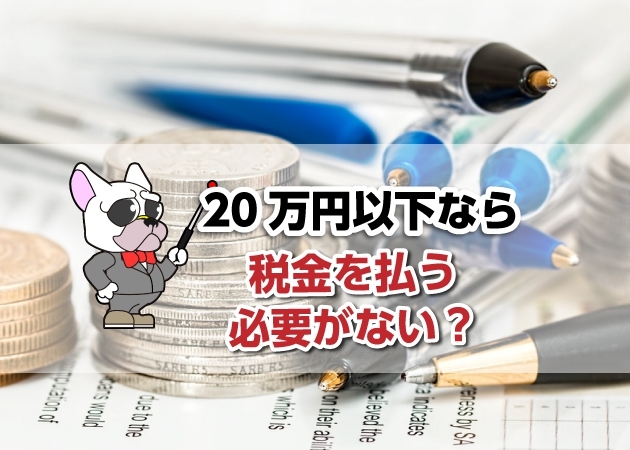
仮想通貨取引をしていれば、利益が発生しますし、税金のことも頭の片隅にありますよね?
しかし、利益が出てもバレないと思って、「脱税」をしようと思っても、結果的に仮想通貨の仕組み上、脱税はバレます。
本記事では、仮想通貨の利益に関する次の4つを徹底的に紹介します!
- 仮想通貨の利益は○○所得?
- 仮想通貨の利益が20万円以下なら確定申告はいらない?理由は?
- 仮想通貨の利益はなぜバレる?
- 仮想通貨の利益が発生した時にできる税金対策
最後まで読むと、「確定申告」に役に経ちますから、ぜひ最後まで読んで下さいね!
この記事の目次
仮想通貨の利益は雑所得に該当
税法上、所得は国税庁が発表している「所得の区分のあらまし」に沿って、次の10種類に分類されます。
【所得の種類】
1 事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得。ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得に分類。 2 不動産所得 土地や建物、不動産の貸付から生じる所得 3 給与所得 勤務先から受け取る給与、賞与などの所得 4 退職所得 退職により勤務先から受ける退職手当や、厚生年金保険法に基づく一時金などの所得 5 配当所得 株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託などの収益の分配などにかかる所得 6 利子所得 預貯金や公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。 7 山林所得 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得 8 譲渡所得 土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得 9 一時所得 生命保険の満期金など、営利を目的としない行為から生じる所得 10 雑所得 上記以外の所得。仮想通貨の利益はこの雑所得に分類。
上記の表から一番有名なのが、会社員が毎月会社から貰う給与で「給与所得」ですね。
そして、株の利益については、株を譲渡することによる利益のため、「譲渡所得」に分類されます。
平成30年4月に国税局は、仮想通貨による利益は、【雑所得】に分類されました。
[平成30年4月1日現在法令等]ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
このため、仮想通貨で利益を出した人は、「雑所得」として税額を計算して確定申告を行い、納税する必要があります。
仮想通貨の税金計算方法は詳しくは下記をご覧下さい。
仮想通貨の利益が20万円以下なら確定申告はいらない?理由は?
結論から言いますと、仮想通貨の利益が20万円以下なら、確定申告を行う必要がありません。
が、
利益が20万円以下でも確定申告が必要な人もいます。
というのが答えです。
まず仮想通貨の利益が20万円以下なら確定申告が必要がない理由について説明します。
仮想通貨の利益が20万円以下なら確定申告が必要がない理由
確定申告に行ったことがある人ならよく分かると思いますが、国税庁が定めた確定申告期間1カ月の間に税務署に申請する必要があるため、この期間の税務署は申請者が殺到することになります。
最近はインターネット上での申請も可能となってはいますが、税額の計算方法が複雑だったり、書類の記載方法を税務署で確認するため、大半の人が税務署に実際に来て確定申告を行っている現状があります。
私は毎年行っていますが、税務署の開門の約1時間近く前から申請者の行列ができているような状態で、確定申告をする時期は非常に込み合っています。
こんな現状もあり、税務署としても確定申告業務にかかる作業をなるべく減らしたいという思いがあります。
そのため「少額であればわざわざ確定申告は必要ありませんよ」というメッセージ(少額不追及)が税法のルールの中に含まれています。
少額不追及とは
Q.現物給与については、少額不追求の観点から課税されないものがあるそうですが、この「少額不追求」とはどのような意味ですか。
また、少額不追求とされる金額について説明してください。
A.現物給与で法令上非課税とされているもの以外のものは給与所得として課税するのが原則ですが、現物給与の特質を考慮した場合、少額なものまで強いて追求し課税することは必ずしも妥当ではないというものがあり、これを少額不追求といっています。
これは、いわば免税点のようなものですから、一定限度額以下の少額なものならば課税しなくても差し支えありませんが、この一定限度額を超えるものについては、その超える部分だけでなく、その現物給与の全額が課税対象となります。
この少額の目安が、20万円になっているため、20万円以下の利益の場合には確定申告が必要なくなります。
仮想通貨の利益が20万円以下で確定申告がいらない人の条件
ただし、20万円以下で確定申告が不要になる場合は、条件があります。
1か所だけからの給与収入がある人、いわゆる会社員の場合だけ、確定申告を行う必要がありません。
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
引用:国税局:給与所得者で確定申告が必要な人
これは、勤めている会社が年末調整を行い、税金の管理を正しく実施してくれているため、給与所得以外の所得が少ない場合(20万円以下)には、税務署における事務処理の負荷簡素化のために、わざわざ確定申告をする必要がありません。
一方、フリーランスや個人事業主など、年末調整を行ってくれる会社に勤めていないような人は、利益の額によらず確定申告が必要となり、仮に仮想通貨の利益が20万円以下であったとしても、確定申告を行う必要がとなります。
仮想通貨の利益はなぜバレる?
仮想通貨が利益があるかないかは必ずバレます。
なぜなら、仮想通貨の仕組み上、簡単に調べることが可能だからです。
例えば、代表的な仮想通貨のビットコインはブロックチェーンという仕組みで通貨の取引台帳を管理しています。
このブロックチェーンには、「誰から誰にいくらの仮想通貨が支払われた」という情報がチェーン上に記録されていきます。
そして、この取引情報を不正に改竄されないよう、ブロックの継ぎ目に改竄チェック用の暗号計算を入れたり、全く同じ全取引データを、世界の膨大なPCでコピーして持つ仕組みをとっています。
ですから、ビットコインでは、その仕組み上「誰から誰にいくらの仮想通貨が支払われた」を後から確認することができます。
結果的に、仮想通貨の利益が発生し、脱税しようと影を潜めていても、国税庁に目をつけられた時点で全てを調査され、脱税したことがバレてしまいます。
また、税務調査は過去3年分を遡って追及することが出来ます。
確定申告をせずに、税金を支払わずに1年が経過したとしても、次の年に調査をされて脱税がバレた場合には、1年前の分まで遡って税金を支払わないといけません。
場合によっては、税金が支払いできないくらいの税額になってしまう可能性もあります。
このため、利益が出た年には、確実に確定申告を行い、納税しておきましょう。
仮想通貨の利益が発生した時にできる税金対策
仮想通貨の利益が発生したら、税金はなるべく安くしたいものです。
結論から言いますと、税金を安くする方法は【必要経費を計上する】方法です。
税法では、利益を出すために支払わなくてはならない出費は、経費として所得からマイナスすることができます。
必要経費に算入できる金額
事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
企業でいえば、営業のための交通費や接待費などが一般的に経費として知られていますよね。
では、仮想通貨の場合には、どのようなものが経費として計上できるのでしょうか?
仮想通貨取引を行うにあたり、何か金銭を支払った記憶を思い出してみましょう。
まずは仮想通貨取引を始めようと思った時に、色々と仮想通貨のことを調べませんでしたか?
参考書を購入したり、より深く知るために有料のセミナーや講演会に参加した方もいるかと思います。
これらは必要経費として計上することができます。
また、仮想通貨取引はどのように行っていますか?
スマホやパソコンでインターネットに接続して行っていますよね。
もしインターネットがなければ、仮想通貨取引は出来ませんよね?
このため、インターネット料金も必要な経費として計上することができます。
ただし、インターネット料金の全てを計上出来るかというと、そうではありません。
仮想通貨取引以外の普通の生活でも、インターネットは利用しますよね?
そこで、実際には、月のどのくらいの時間を仮想通貨取引に使用したのかについて割合を概算で見積もり、その割合分だけ経費として計上することになります。
また、本やセミナー料金についても、気を付けなければならないことがあります。
本当にその本を買ったのか?あるいは購入金額が正しいのか?について、証拠を示すために領収書が必要となります。
ですから、本屋さんで仮想通貨関連の本を買った場合には、レシートを必ず取っておく必要があります。
インターネット料金についても、証拠を示すために毎月の請求書のコピーや印刷物を、確定申告の際に参考資料として提出する必要があります。
つまり、仮想通貨取引でも、必要経費を掲出する為には、【証明できるもの】が必要になります。
仮想通貨の税金を安くする為に、1年間分のレシートや請求書を準備するのは面倒な作業となります。
しかし、法律に違反しないよう、しっかりと納税するためには必要な作業となり、さらには、税金を安くする為には必要なことです。
ですから、面倒くさがらずに、しっかりと準備をしてくださいね。
仮想通貨の利益に関するまとめ
仮想通貨の利益は確かに、取引をしているととても嬉しいものです。
しかし、仮想通貨取引をしているなら、利益が出た後のことも考える必要があります。
ですから、仮想通貨の利益が出た時には、きちんと税金や確定申告のことは覚えておきましょう。











































