
アジア最大のブロックチェーンカンファレンス|IBMの高田氏が登壇

2019年1月30日~1月31日にかけて行われた、『JAPAN BLOCKCHAIN CONFERENCE 2019 YOKOHAMA』にて、日本IBM社の高田 充康氏(以後 高田氏)が登壇し、
同社が展開するブロックチェーン事業の事例を紹介するとともに、自身の見解を述べました。
高田氏は、日本IBM社のブロックチェーン・ソリューション事業部長で、同社のブロックチェーン事業の中核を担う人物です。
今回のカンファレンスには、高田氏を含め、以下のような多くの著名人が出席しました。
- ブロック・ピアース/ビットコイン財団 会長
- ロジャー・バー/bitcoin.com CEO
- 松田洋平/経済産業省 商務情報政策局 情報経済化 課長
- 室山真一郎/LINE株式会社 事業戦略室室長
1月30日~1月31日にかけて、パシフィコ横浜にて開催されたアジア最大のブロックチェーンカンファレンスです。
仮想通貨の知名度向上とともに、今勢いを増しているのがブロックチェーン技術。
同カンファレンスでは、ブロックチェーン技術の未来を担う国内外の有力企業・団体が集まり、相互に情報交換や、国内外に向けたグローバルな情報発信が行われます。
IBMのブロックチェーン活用事例
世界には、ブロックチェーンを応用した商品やシステムが存在しますが、最もポピュラーなものは「仮想通貨」や「ビットコイン(BTC)」です。
以下の画像をご覧ください。

最近、ブロックチェーン技術を採用し、システム構築や商品開発を行う企業が少しずつ増加してきています。
企業がブロックチェーンの利用する場合は、パブリックネットワークだとパフォーマンスやセキュリティ面での欠陥が多くみられるため、
通常はプライベートネットワークを使用するケースが多いです。
事実、xRapidやxCurrentなど、新たな国際送金規格として注目を浴びているリップルや、R3社が主導となり開発された「corda」などはプライベートネットワークです。(上記画像参照)
高田氏は以下のような表を用い、IBMのブロックチェーンネットワーク導入状況について説明しました。
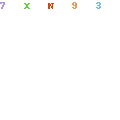
ここからは、以下2つの事例について、高田氏の発言をまとめていきます。
- 国際貿易
- 食の安全
国際貿易
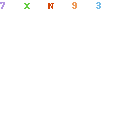
まず高田氏は、ブロックチェーン未導入の国際貿易の現状を次のように説明し、IBMの指針も交えながらブロックチェーン導入がもたらす可能性について次のように解説しました。
まず国際貿易の例で挙げると、一つのチューリップの花をアフリカからヨーロッパに流すだけでも、実際には30もの企業間でやりとりが行われ、100人以上もの人員、200以上もの書類のやりとりが必要となる。
しかしその過程にブロックチェーンを導入することで、関係者が瞬時に全ての情報を共有することが可能となる。
これまで貿易で紙媒体でやりとりをしていたものを全て電子化し、関係者が瞬時に情報を共有するにはブロックチェーンの利用に適しているとIBMは考えている。
多くの関係者が携わっており、情報がバケツリレー方式で伝わっていき、ブロックチェーンを使用すれば電子化されていたものが瞬時に伝わることとなる。
また、導入企業例として、世界最大の船会社「マースク社(デンマーク)」が中心となりブロックチェーンネットワークを構築していることを明らかにし、
ブロックチェーン技術導入後の現状について次のように説明しました。
このブロックチェーンネットワークでは、1日に100万件のイベントが処理され、これまでの時点で3億件のイベントをブロックチェーン上で処理している。
このように確認すると、ブロックチェーンは実証利用を超えて、国際貿易の分野では頻繁に活用されてきた。
取引の透明化によりコスト削減効果や情報共有プラットフォームを活用し、業務プロセスを効率化していく事例も見られている。
食の安全
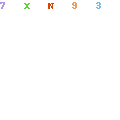
日本は世界でもトップレベルで”食の安全に厳しい国”として知られています。
しかし、そんな日本でも2007年のミートホープ事件をはじめとする偽装問題や、2008年の中国輸入餃子・殺虫剤事件をはじめとする食中毒問題が起きており、
日本より規制が緩い海外では、それらの問題が日本以上に存在しています。
高田氏によると、IBMはそれらの問題をブロックチェーン技術を応用することにより解決するべく、ネットワークの開発を進めているといいます。
また、すでに商用化されているプラットフォーム「IBM Food Trust」については次のように言及しました。
IBM Food Trustでは、トレーサビリティのモジュール、証明書管理、鮮度分析などが行われています。
よって、いつ、どこで、誰によって行われたが改竄されることなく記録されている。
そのため、食の安全分野においてもブロックチェーン技術は非常に有効だと言えるだろう。
【参考文献】







































