
仮想通貨に代表される投資情報を調べていると「ポンジスキーム」という言葉を耳にする機会があります。
大きな儲けが期待できるという謳い文句でポンジスキームの素晴らしさを訴える広告や記事が見られますが、甘い言葉に騙されてはいけません。
投資に必勝法がないように、仮想通貨にも絶対はありません。
儲かるという言葉に誘われてうっかりを手を出そうものなら痛い目にあってしまいます。
大切な資産を守るためにも、ポンジスキームとは何なのかを知っておきましょう。
この記事の目次
ポンジスキームとは

ポンジスキームは詐欺の一種
ポンジスキームとは、結論から言うと詐欺の一種です。
高配当・高利回りが実現するという謳い文句で出資を募りながら実際には運用は行わず、出資金の中から配当金を工面して表面上は実績をあげているように見せかけるような詐欺的手法のことをポンジスキームと呼びます。
ポンジスキームとは、 名目は高配当の利回りを実現できる投資案件としながらも、実際は出資者から募った資金で配当を賄っていく詐欺のことを指します。 当然、実際に資金を運用していないので、新しい出資者がいなくなると高配当な利回りを実現できなくなってしまい案件は破綻することになります。
引用:ポンジスキームは詐欺案件の常套手段?投資詐欺に騙されないためには
ポンジスキームは、あらゆる投資を対象に実行される古典的な詐欺的手法で、株式投資や共同事業などを謳い文句にするケースが多かったのですが、近年は仮想通貨投資を舞台にしたポンジスキームが急増しています。
仮想通貨市場でポンジスキーム被害が拡大
仮想通貨バブルにより億万長者が何人も誕生したこともあり、一般的な投資ではありえないような高配当高利回りも「仮想通貨投資」というだけで信じてしまう人が多いため、ポンジスキームによる詐欺被害が拡大しています。
ポンジスキームは高い収益を掲げて多くの出資者から出資金を集めますが、実際には集めた資金が運用に回されることはありません。
出資金の一部は運用益が上がっているかのように見せかけるためのニセの配当金原資に使用されますが、その他の大部分に関しては詐欺師である運営者が詐取しています。
気づいたときには時すでに遅し
出資からしばらくの間は見せ掛けの配当金により運用がうまくいっているように装いますが、時間が経つにつれ配当が遅れるようになりある日を境に全く分配金が支払われなくなります。
支払いがとど凝っていることに不信感を抱いた出資者が運営を問いただそうとしても、その頃には姿をくらませてしまっているので連絡がつきません。
出資者はこの段階になってポンジスキームによる詐欺であることに気づきますが、すでに出資金の大部分は使い込まれてしまっており回収は困難です。
計画的に進められた悪質な投資詐欺
ポンジスキームは投資を装った詐欺に過ぎません。
運用が全く行われていないので収益が上がることはなく、最初から計画的に進められた犯罪行為です。
運用はしたが失敗して損失が出てしまったというケースとは全く異なる、悪質な投資詐欺なのです。
ねずみ講とポンジスキームの違い

出資を募る詐欺と聞くと「ねずみ講」が思い浮かびます。
不特定多数の人間からお金を集めて騙し取るという点ではねずみ講とポンジスキームは似ているように思えますが、両者は同じ詐欺行為でありながら全く異なるものです。
ねずみ講はピラミッド式に集金するシステム
ねずみ講はピラミッド式に集金するシステムで、上位の者が下位の者からお金を集めることで収益を得る構造です。
上位にいる人間は利益を得られますが下位に行くほど利益を得るのが困難になる点で、頂点に立つ人間だけが独占的に詐欺による収益を得るわけではありません。
集金の方法も、投資や仮想通貨による運用益をかたるケースもありますが、多くは商品やサービスの販売や利用を通じてお金を集めます。
新たに会員を勧誘したり紹介するほど報酬がアップするといったねずみ講独特のシステムも存在し、本人の努力次第で利益が大きくなるという点が特徴です。
ポンジスキームの資金はトップに集中する
ポンジスキームでは、詐欺によって集められる資金はトップに集中します。
出資者は勧誘した個人ではなくプロジェクトに対し出資する形になるため、ねずみ講のように上位の人間に利益が生じることはありません。
詐欺によって集められる資金はポンジスキームで提示された投資案件に集中するので、運営者である詐欺師が出資金を独占します。
ポンジスキームの参加者には配当金を語った分配金という形でいくらか還元されますが、これは運用が行われていると偽装するためのもので利益とは全く異なる性質です。
配当金の額は出資金のごく一部であり、大部分は詐欺主体によって詐取されてしまいます。
ねずみ講が参加者全体が何らかの形で詐欺に加担しているのに対し、ポンジスキームは運営者が詐欺師で加害者で出資者の全てが詐欺の被害者となります。
ねずみ講は加害者と被害者が同一人物になることもありますが、ポンジスキームでは明確に区別されています。
ポンジスキームはタコ足配当
ポンジスキームではいわゆるタコ足配当によって配当金が支払われます。
タコ足配当とは、タコが自分の足を食べてしまうことになぞらえた表現で、投資などで運用益で分配金が賄えないときに自己資本を配当金にあてることを指します。
運用益が1億円で分配金が8千万円であれば運用益だけで分配金をまかなえますが、分配金8千万円に対し運用益が5千万円しかなければ3千万円の不足が発生します。
この3千万円の不足を自己資金によって賄い、約束した配当額を維持するのがタコ足配当です。
タコ足配当は自己資金を減らす行為なので、長期間続ければ投資元本にあたる自己資本が目減りし続け食いつぶしてしまう恐れがあります。
タコ足配当が行われているということは、期待した運用益がでていない証拠であり、長期的な危険性を抱えている投資と判断できます。
ポンジスキームではそもそも運用が行われておらず、分配金はすべて自己資本から支払われるタコ足配当で賄われます。
長期的には自己資本を食いつぶすだけですが、当初は運用益があることを装うために見せかけとして数回の支払いを行います。
数回支払った後で分配金は打ち切りとなり、集められた出資金の大部分は詐欺師によって詐取されてしまいます。
そもそもポンジスキームは違法ですよね?

ポンジスキームは出資してもらった資金を元に投資を実行し運用益を分配する、と言っておきながら実際には投資行為が行われません。
実態としては「投資を騙って資金を集め運用益があるかのように装っている」だけに過ぎず、刑法249条の詐欺罪に該当する行為です。
第249条
- 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
- 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用:wikiBOOKS
出資金をもとに実際に投資が行われた結果として損失が出ている場合は単なる投資の失敗ですが、そもそも投資が行われていないのであれば明確な詐欺行為です。
詐欺罪が成立するためには「出資者が事前に真実を知っていれば財産を預けていなかった」と認定される必要がありますが、投資による運用が行われていないという実態が知られていれば誰もお金を出資していなかったであろうことは明らかです。
その点においてもポンジスキームは明確な詐欺であり違法行為に該当します。
仮想通貨のポンジスキームの詐欺事件の事例

2017年 韓国で仮想通貨投資詐欺が発生
過去に実際にあったポンジスキームとしては、2017年に韓国で発生した仮想通貨投資詐欺が有名です。
この事例では、仮想通貨投資による高利回りを名目に500人以上から合計で3億円以上の出資金が騙し取られました。
少額の出資を重ねているのが特徴で、ポンジスキームによる詐欺被害は合計で1000件以上になります。
個々の被害は少額ながら被害対象は国際的な広がりを見せ、韓国国内だけにとどまらず欧米や日本でも被害が発生しました。
2019年5月 33億円規模の資金不正使い込み
2019年5月、米国証券取引委員会(SEC)が日本円で33億円規模のポンジスキーム詐欺を停止させたというニュースが報じられました。
このポンジスキームで告発されたのはアーガイルコイン社代表のホセ・エンジェル・アマン氏です。
告発状によると、アマン氏はた仮想通貨アーガイルコインへの投資名目で集めた資金を不正に使い込んだとされています。
アーガイルコインはダイヤモンドを価値の裏付けとしており、リスクが少ないと説明していました。
しかし、実際には出資で集められた資金は運用されておらず、家賃や馬の購入代金など私的に流用していたことが明らかになりました。
この事件では、ポンジ・スキームであることが明るみに出ないよう複数の証券会社を経由するなど複雑な形態が用いられており悪質さが指摘されています。
プラストークンはポンジスキームなの?
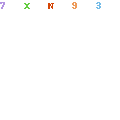
仮想通貨界隈で話題となっている仮想通貨ウォレットのひとつ「プラストークン」には、当初からポンジ・スキームなのではないかという疑惑がささやかれています。
プラストークンはアービトラージによる運用益が分配原資とされていますが、実際にアービトラージだけで過去の分配実績を達成するのは困難であるという味方が優勢です。
これまでの実績をアービトラージだけで実現するのはほぼ不可能であることから、出資金を分配原資に充てるタコ足配当ではないかという疑惑が持たれています。
仮にタコ足配当が事実だとすれば、運用益が好調であるかのように装っているポンジスキームである可能性が濃厚ですが、現在のところ決定的な証拠はありません。
状況証拠から判断すればクロに近いグレーですが、決定的な証拠はまだ見つかっておらず判断は利用者に任されています。
プラストークンの最新情報は下記の記事をご覧ください。
ポンジスキームを見極める方法

利回りが高過ぎる
高利回り高配当はポンジスキームの常套句です。
高い収益が期待できる仮想通貨投資でも常識で考えて無理な水準を達成することは不可能で、あまりにも高過ぎる利回りを掲げての出資募集はポンジスキームである可能性を疑う必要があるでしょう。
利回りが年6%を超えるとかなりの高水準で、年10%を超えるとポンジスキームの疑いは濃厚です。
年20%を超えているようなら詐欺の疑いはほぼ確実で手を出すべきではありません。
運用の詳細が明らかにされていない
運用の詳細が明らかにされていないのも危険な兆候です。
投資プロジェクトではどこにどれだけ投資しているのかが最重要ポイントです。
それを明らかにしていないということは運用実態そのものがない可能性が高く、ポンジスキームの疑いは濃厚です。
運用について説明されていてもあやふやな部分が多かったり複雑な説明でわかりにくいようであれば要注意です。
第三者によるチェック体制が無い
第三者によるチェック体制がないのも危険です。
運営だけが出資金を自由に出来る体制では使い込みを防げません。
第三者による監査や定期的な情報開示などきちんとしたチェック体制がないのはポンジスキームである疑いを拭いきれません。
ポンジスキームのまとめ
ポンジスキームは古くからある古典的な詐欺ですが被害は後を絶ちません。
手を変え品を変え行われるポンジスキームですが、現在は仮想通貨での被害が多数報告されています。
大切な資産をだまし取られないためにも、高利回り高配当といったうまい話にはくれぐれも注意しましょう。


























-150x150.jpg)













